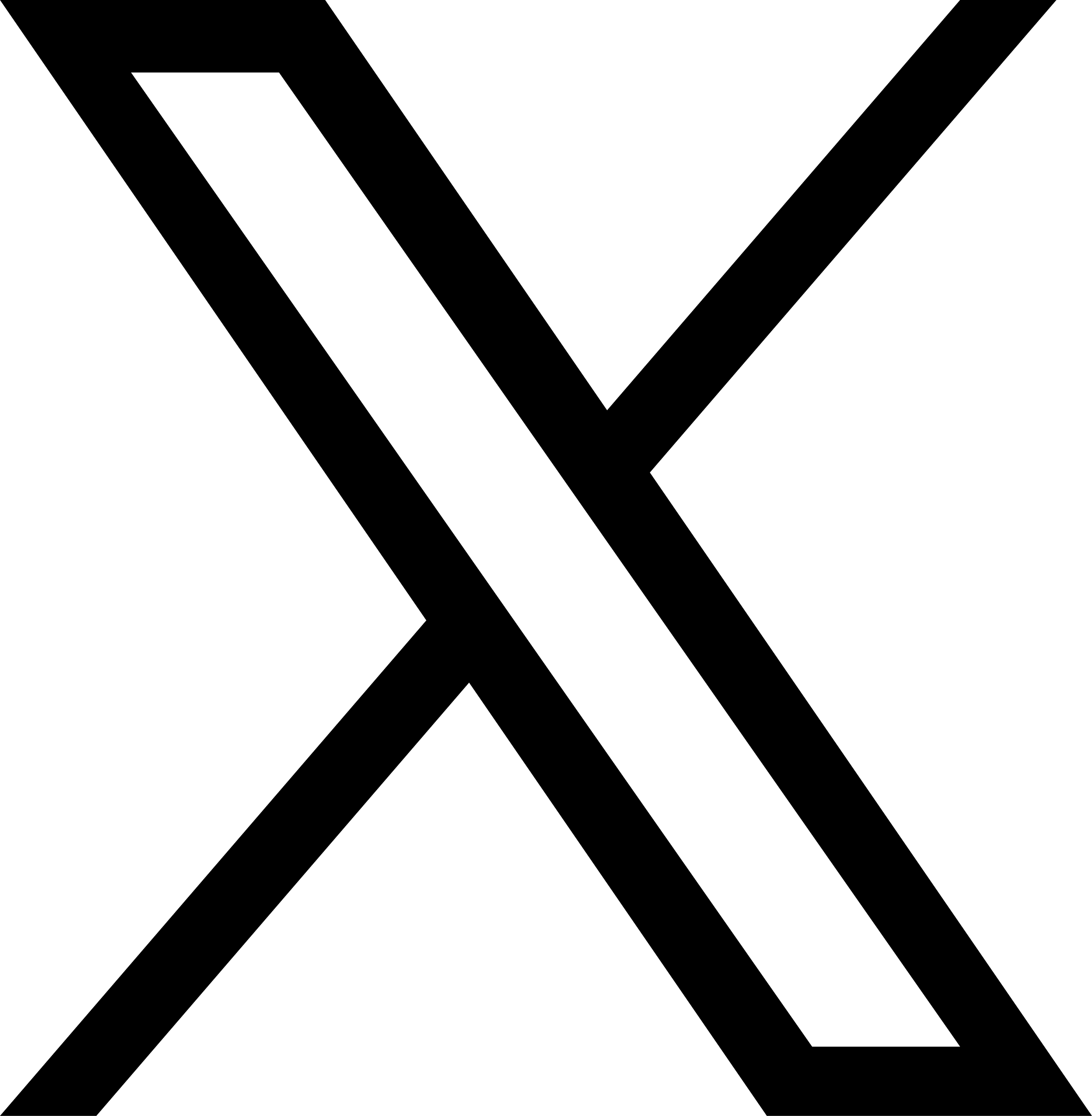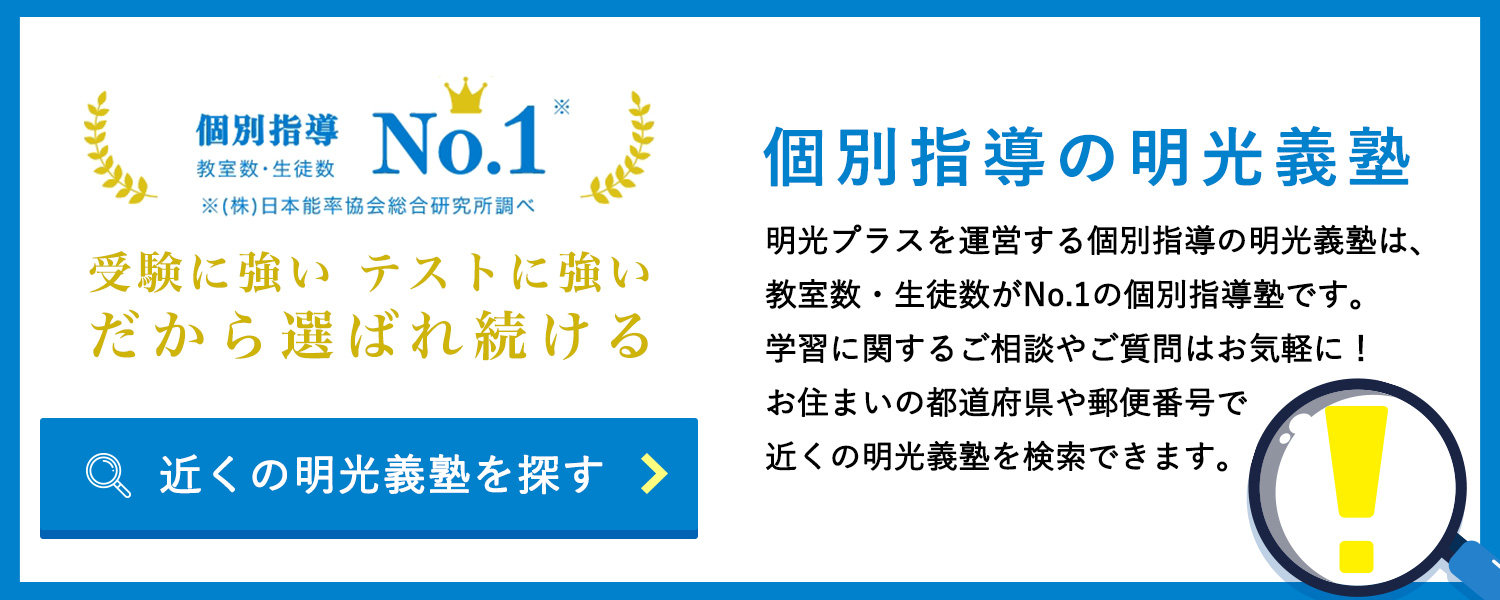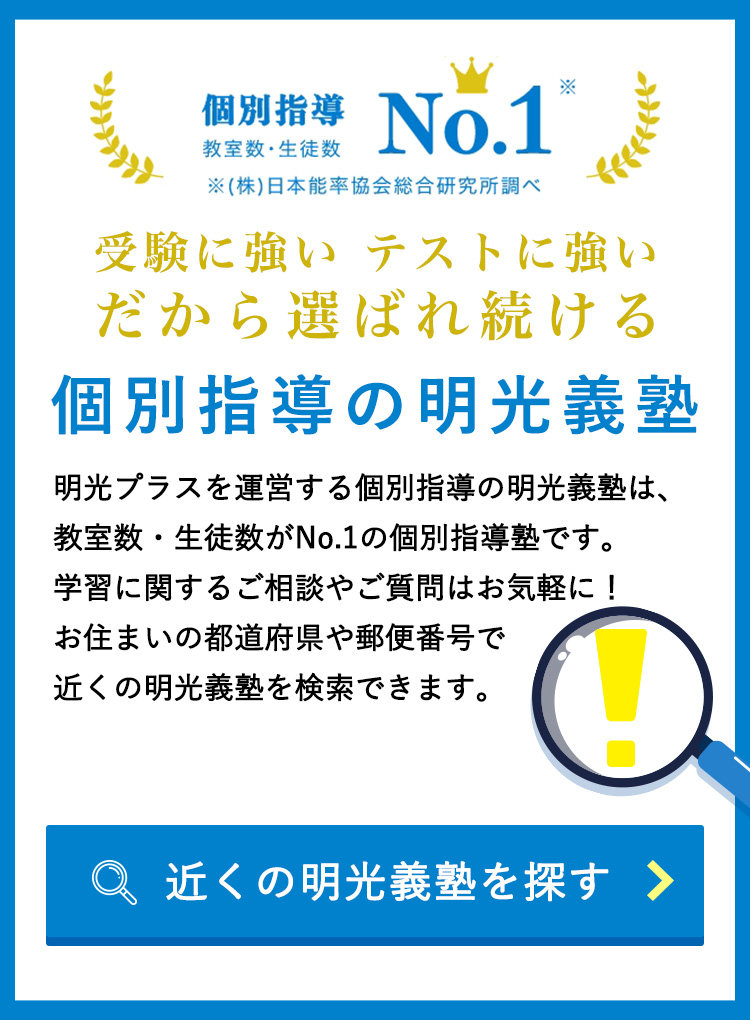2020.09.28
勉強のモチベーションを維持するには?やる気を引き出す方法10

「勉強のモチベーションが上がらない・・・」「どうすればモチベーションを上げることができるのだろう・・・」と悩んでいる人は多いでしょう。勉強が好きな人は少ないので、やる気が出ないのは当然のことと言えます。
この記事では、勉強のモチベーションが上がらない理由に触れながら、やる気を引き出す方法を長期的な勉強の場合と短期的な勉強の場合に分けてご紹介します。
勉強のモチベーションが上がらない理由とは?
勉強のモチベーションが上がらない理由はいくつかあります。主な理由を5つご紹介しましょう。
勉強したいと思えない
誰でも「勉強したくない」という気持ちはあるものです。「基本的に勉強が好きではない」という人も多いでしょう。勉強したくないという気持ちが強いのに「仕方なく勉強させられている」と感じれば、モチベーションが上がらないのも無理はありません。
勉強する意欲が出ないときは、「志望校合格のため」など勉強する目的に立ち返ってみましょう。自分が将来なりたい姿を意識することで、モチベーションは自然と上がるでしょう。
毎日が忙しくて疲れている
「勉強しよう」と思っていても、疲れが溜まっていればモチベーションは上がりません。疲れているときは、学習効率を上げるため、しっかり休んでから勉強するように努めましょう。 睡眠不足も勉強のモチベーションを下げる要因になります。受験生の場合は、最低でも6~7時間は睡眠をとるようにしましょう。
勉強以外のことが気になって集中できない
勉強道具以外のものが机や部屋にあると気になってしまい、なかなか勉強に集中できません。特に普段自宅で勉強している人は、注意が必要です。
スマホやタブレットの通知があるたびに触ってしまったり、ちょっとした気分転換でゲームを始めたりすると、勉強のモチベーションは下がってしまいます。
目標までの道のりが遠くてイメージができない
受験日までの期間が長いと、ゴールがイメージできず勉強のモチベーションが上がりません。受験勉強の場合は半年後、1年後がゴールになるため、模試での点数を目標とするなど短期的なゴールを設定するといいでしょう。
勉強しても成果が感じられない
目に見える成果が出るとやる気が出ますが、思うような結果を得られなければモチベーションは下がります。
なかなか成果が出ない場合は「勉強方法の調整ができていない」か「勉強方法そのものが間違っている」可能性があるので見直しましょう。また、優等生タイプの人は、ハードルを上げすぎることで手ごたえを感じなくなっているケースもあるので注意しましょう。
特に受験生のやる気が出ない・モチベーションが上がらない理由とその解決方法については以下の記事で紹介しています。ぜひご覧ください。
勉強のやる気が出ない受験生はどうすべき?すぐできることから本質的な解決方法7選
勉強するモチベーションを上げるためのコツとは?

勉強のモチベーションを上げるためには、どうすればいいのでしょうか?ここでは、具体的な方法を3つご紹介します。
勉強する目的を明確にする
何よりも、「勉強する目的をハッキリさせる」ことが大切です。「絶対に志望校に合格したい」「絶対に模試で○位以上になりたい」というように、具体的な目標を掲げればモチベーションアップにつながります。
自分の意思で行動しなければ、ちょっとしたことでもモチベーションは下がってしまうものです。他人に言われたからやるのではなく、自分のために自分で目標を決めましょう。
無理のないスケジュールを立てること
やる気になるのは良いことですが、無謀なスケジュールを立てると自分で自分を苦しめることになります。無理なスケジュールは疲労や睡眠不足の原因にもなり、結果的にモチベーションを下げてしまいます。
勉強が計画どおりに進まないと、「自分が決めたことさえ守れないダメな人間なんだ」と自己嫌悪に陥ってしまうこともあります。「継続は力なり」という言葉があるように、無理のないスケジュールを立てて継続できるようにしていきましょう。
勉強に適した環境を作ること
勉強道具以外のものが机の上や部屋にあると、気が散って勉強に集中できなくなってしまいます。自分の部屋を勉強に適した環境にするためには、「部屋の整理整頓」や「気が散る原因になるものを視界に入れない」といった対策が必要です。
勉強に適した自宅以外の場所としては、塾の自習室や図書館などがおすすめです。
塾に通うこと
自分で勉強スケジュールを立てたり、勉強の自己管理をしたりすることが苦手という方は塾に通うこともモチベーションを上げるために有効な手段の一つです。
塾ではあらかじめ決められたカリキュラムのもと、講師が予習・復習・宿題など生徒の取り組むべきことを提示してくれます。「授業ごと」という短いスパンでやるべきことが明確化されるため、勉強方法や勉強内容に悩むことなく、勉強するモチベーションを保つことができます。
また、塾は生徒のフォローも手厚く、もしわからない問題があっても先生に質問することですぐに解決することができます。つまり、塾に通うことで「理解できないから勉強したくない」というモチベーション低下の原因をなくすことも可能になるのです。
成績アップが実感できる
明光義塾のメソッドをご体験ください!
【長期間の勉強向け】勉強のモチベーションをアップさせる5つの方法
ここでは長期間勉強に取り組む場合のモチベーションの上げ方を5つご紹介します。
ライバルを見つける
勉強の目的が何であれ、ライバルの存在はモチベーションを高めることにつながります。学習におけるライバルは、仲がいい人や自分よりも少し成績が良い人の中から見つけるといいでしょう。
ライバルが勉強に取り組んでいる姿は、自分をやる気にさせてくれるものです。「負けていられない」という気持ちも強くなるので、モチベーションをキープできます。お互いに高め合っていけるような相手を見つけましょう。
勉強した量を可視化する
自分がこなした勉強量がわからないと、モチベーションは上がりにくくなります。勉強した量を目に見える形にして、勉強量を実感できるようにしましょう。
可視化の方法としては、「覚えた単語の数だけ10円玉貯金をする」などが有効です。過去の勉強量が見ただけでわかるようになれば、「もっと勉強量を蓄積しよう」という心理が働き、モチベーションの維持・向上につながります。
「勉強ができる」という感覚を身につけること
「自分は勉強ができる」という感覚をつかめると自信がつき、勉強自体が楽しいと思えるようになります。ただし、最初からこの感覚をつかむのは難しいかもしれません。そもそも、モチベーションが上がらなければ「勉強ができる」という感覚にならないからです。
ある程度モチベーションを維持できるようになって、勉強に対する興味や関心が高まってくれば「勉強ができる」と感じられるようになり、その自信がモチベーションアップにつながるはずです。
成功体験や有名人の名言を読む
志望校に合格した先輩たちの体験談を読むことは、やる気につながります。体験談を読みながら合格した後の自分を想像するだけでも、モチベーションが上がってくるはずです。
また、有名人の名言を読むこともモチベーションを上げるのに有効です。言葉の力は絶大であり、他人の言葉がきっかけでやる気が出てくることもあります。好みの有名人や著名人がいるなら、その人が書いた本を購入するのもいいでしょう。
勉強しない日を作る
勉強が続くとストレスが溜まり、モチベーションが上がりにくくなるので、定期的に半日または1日、勉強から離れてリフレッシュできる時間を作りましょう。
「勉強から逃げ出したい」と思うときは、誰にでもあります。そのような辛い気持ちを抱えたまま勉強しても、学習効率は上がりません。「遊ぶときは全力で遊び、勉強するときには徹底的に集中する」このような切り替えができれば、学習効率は飛躍的に上がるでしょう。
【短期間の勉強向け】勉強のモチベーションをアップさせる5つの方法
ここからは、短期的な勉強に取り組むときのモチベーションの上げ方を5つご紹介します。
とにかく勉強する
やる気が出なくても、とにかく机に向かってみましょう。少しずつ勉強に取り組んでいる間に「ドーパミン」という物質が脳内で分泌され、次第にやる気が出てきます。行動を起こすことによってやる気が湧き、勉強を進めていくうちに集中力が高まるという正の連鎖が起こるのです。
英単語の暗記なら、最初は1つか2つでも構いません。続けているうちにモチベーションが上がり、たくさんの単語学習を進められているということにつながるでしょう。
勉強場所を変える
「同じ環境で勉強を続けるほうが集中できる」という人もいますが、マンネリ化してしまい、勉強のモチベーションが下がる人もいます。
同じ場所だと飽きてしまう人は、予備校や塾の自習室や教室、図書館、ファミレス、カフェなど、そのときの気分によって勉強する場所を変えてみましょう。いつもとは違った場所で勉強すると気分がリフレッシュし、モチベーションアップにつながることがあります。
カフェインを摂取する
モチベーションが下がってきたり、集中力が切れてきたりしたときには、カフェインを摂取して気分を切り替えるという方法もあります。カフェインを摂取すると頭がすっきりするので、眠気防止にもなります。
カフェインを摂取するなら、コーヒーやエナジードリンクがおすすめです。ただし、カフェインの覚醒効果は4~5時間続くこともあるため、夜に摂取する際は注意してください。
休息をとる
眠たいときや疲れているときは、どうしても勉強のモチベーションが下がります。
眠たいときは、15〜30分程度の短い仮眠をとることがおすすめです。眠気が消えて頭もすっきりするので、無理をして勉強を続けるよりも効率的でしょう。
また疲労が溜まっている日は早めに寝て、翌日の朝早くから勉強を始めるほうがはかどります。
誰かに監視してもらう
誰かに見られていると、「やらなければいけない」「サボれない」という意識が芽生えます。このような強制力がある状態では「作業興奮」の状態になりやすいため、勉強に集中しやすくなります。
課題が終わるまで親にスマホを預けておくなど、家族に協力してもらうのもいいでしょう。集中力に自信がない人や、勉強する習慣がついていない人にもおすすめの方法です。
まとめ
勉強する習慣がついていない人や、勉強で成果が出にくい人、勉強のやり方がわからない人にとって、勉強のモチベーションを維持することは簡単ではありません。しかし、受験勉強は自らの意思で行うもの、自制心が必要になります。
勉強への意欲を高め、維持するためには、まず疲れを溜めないようにすることが大切です。睡眠不足にも注意してください。どうしてもモチベーションが上がらない場合は、学習塾などの仲間と切磋琢磨できる環境を利用して、やる気を高めてみてはいかがでしょうか。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは
2025.07.03
「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
2025.06.26
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...