2021.03.23
受験生にスマホはNG?受験に効果的なスマホの活用術を解説

現在は、中学生の多くがスマホを持っていますよね。
スマホは便利で楽しいアイテムなので、生活に欠かせない存在になっているのではないでしょうか。
しかし、受験生になるとスマホが勉強の邪魔になることもあるので、スマホを断とうと考える人もいるでしょう。
受験生の敵と思われがちなスマホですが、上手に使えば受験勉強に役立つこともあります。
この記事では、受験期間にどのようにスマホと付き合ったらよいかを考えて、上手なスマホの活用術を解説します。
スマホがもたらす受験生への悪影響とは?
確かにスマホは受験勉強の邪魔になることもあります。
どのような場合に悪影響を及ぼすのでしょうか。
集中力が低下する
まず、スマホが手元にあると勉強中に集中力が途切れてしまいがちです。
メッセージの通知がきたり、友達のSNSが気になってしまったりと、スマホがない状態と比べると圧倒的に集中力が低下します。
メッセージを確認したり返信したりして勉強を再開したとしても、その後も返事が気になったりやり取りが続いたりして、勉強に戻れなくなってしまうものです。
勉強時間が減ってしまう
メッセージのやり取りもそうですが、休憩のため「ちょっとだけSNSや動画を見よう」「ゲームしよう」と思ったら、ついついスマホから離れられなくなってしまったということもよく起こります。
SNSや動画、スマホゲームは、確かに楽しくてリフレッシュできますが、それらは受験勉強の妨げになり、貴重な勉強時間が減ってしまいます。
勉強した気になってしまう
スマホを使って効率のよい勉強方法やノウハウを調べることもあるでしょう。しかし、勉強方法を調べるだけでは成績は上がりません。
調べただけで満足して勉強した気になってしまうので、むしろ注意が必要です。
調べた内容を即実践し、実際に勉強が快調に進めばよいのですが、往々にして勉強には反映されないことが多いといえます。
ネガティブな気持ちになる情報に触れやすい
スマホを見ると、余計な情報も入ってきます。
自分の成績が思うように上がらないときに、友達がSNSで「成績が上がった」とか「勉強がはかどっている」といった投稿をしているのを見ると、不安になってしまうでしょう。
自分と友達の状況を比べてあせりを感じ、ネガティブになってしまうのです。
スマホを見ると、余計な情報で心を揺さぶられてしまい、勉強に集中できなくなってしまいます。
受験勉強を妨げないためにも「スマホのルール」を見直そう
スマホと上手に付き合い、勉強の妨げにならないようにするためには、スマホのルールを見直すことが大切です。まず、受験勉強に有効な以下の3つのルールを決めます。
・スマホを見えるところに置かない
・よく使うアプリは非表示にする
・スマホを見てもよい時間帯を決める
そして、ルールを守るために以下の2つを実行します。
・スマホを見なかった時間をアプリで記録する
・スマホを触れない環境で勉強する
スマホを見えるところに置かない
机に向かって勉強しているときに、スマホの通知音が鳴って集中力が途切れてしまうのは、とてももったいないですよね。
集中力を維持して勉強するためには、スマホを自分の目に入らない場所に置き、スマホが気にならない状況を作るのが有効です。
例えば自分の部屋で勉強するときは、スマホをリビングに置くといったルールを決めましょう。
スマホが気になったとしても、「わざわざ別の部屋に行ってまで見なくてもいいや」と思えることがほとんどなので、勉強中はスマホを別の部屋に置くのがおすすめです。
よく使うアプリは非表示にする
スマホを触るとつい開いてしまうアプリや、気づけば長時間使ってしまうアプリは、受験勉強の間はフォルダに入れて見えないようにしたり、スマホの機能を制限したりして、ホーム画面に出てこないようにしておくのがおすすめです。
さらに、アプリの通知をオフにしておけば、通知の内容が気になってアプリを開いてしまうことを防げます。
アプリを削除してしまうという方法もありますが、削除することでデータが消えてしまい、受験後に不便になってしまうケースも考えられます。
スマホを見てもよい時間帯を決める
「スマホを見るのはこの時間だけ」と、自分でルールを決めておきましょう。
例えば「食後の30分間」や、「1日の勉強ノルマが終わったら1時間」などがおすすめです。
勉強の妨げにならないタイミングで、スマホタイムを設定しましょう。また、1日の利用時間の上限も決めておくと、さらに効果的です。
スマホを見なかった時間をアプリで記録する
スマホは、用もないのについつい手に取ってしまい、気づいたら見ていることが多いものです。
そのため、1日の利用時間を決めてアプリに記録し、スマホの利用時間を管理しましょう。実際の利用時間を数字で把握すると、時間のルールを守りやすくなるのでおすすめです。
自分で利用時間をコントロールするのが難しい人は、1日の利用時間の上限を超えるとロックがかかるアプリもあるので、上手に活用しましょう。
スマホを触れない環境で勉強する
自分で決めたスマホのルールを確実に守るためには、スマホを触れない環境で勉強をするのもおすすめです。
塾や予備校など、スマホを触りたくても触れない環境なら、集中して勉強を進められるでしょう。
スマホを触れない環境で集中して勉強し、1日のノルマを達成すれば、スマホタイムを存分に楽しめるはずです。
受験生がスマホ断ちする際のポイント

「スマホ断ち」といっても、現代においてスマホは生活必需品の1つになっています。
スマホをまったく使わない生活は不便も多く、必要な連絡が取れないことなどからストレスにつながる可能性もあるでしょう。
そのため、受験生がスマホ断ちをするときは、完全にスマホを持たない生活にするのではなく、受験勉強の妨げにならない程度にスマホを控えることを意識するとよいでしょう。
スマホ以外の誘惑で勉強時間を減らさないようにする
受験生にとって、勉強の妨げになるものはスマホだけではありません。
長時間勉強をしていると集中力を切らしてしまい、つい他のものに意識が向いてしまう、という経験をしたことがある人は多いでしょう。意識が向く先はスマホではないこともあります。
したがって、「スマホさえ別の部屋に置いておけばOK」というわけではありません。
勉強するときは、自分の目に触れ、手が届く場所には、スマホをはじめ気が散るようなものを一切置かないようにしましょう。
スマホ以外の気分転換の方法を考えておく
受験勉強の合間には、気分転換も必要です。
脳は働かせるうちにパフォーマンスが低下してくるため、いずれ集中力の限界を迎えます。オーバーワークにならないよう、勉強の合間に気分転換をすることが大切です。
しかし。気分転換の際にスマホを使用すると、通知の確認や動画の再生をするうちについ長くなってしまい、時間の浪費につながります。また、脳を休めたくてもスマホの画面の強い光によって休まらず、むしろ自律神経が乱れてしまい、十分な気分転換にならないこともあるでしょう。
勉強の合間の気分転換では、音楽を聴いたり、ストレッチや散歩などの軽い運動をしたりするのがおすすめです。また、20分以内の短い昼寝をするのも脳のリフレッシュになり、受験勉強に効果的でしょう。
受験生もスマホ断ちせずに勉強効率をアップ!スマホの上手な活用法とは
受験生でもスマホ断ちをせず、むしろスマホを上手に使いこなすことで勉強の効率をアップすることができます。
ここからは、受験生におすすめのスマホ活用術をご紹介します。
受験勉強のスケジュールをカレンダーで管理する
受験勉強のスケジュールはどのように管理していますか?
手帳や専用のノートに書いて管理している人もいるかもしれませんが、一度書いたものは後で変更しにくく、情報の整理もしづらいですよね。おまけに、紙や手帳はかさばります。
スマホのカレンダーでスケジュールを管理すれば、変更も簡単で、情報もきれいに整理できます。
受験日をはじめ、模試の日や願書の締め切り日など、受験に関する大事な日程も管理しやすくなるでしょう。
アラート機能で勉強時間と休憩時間を管理する
スマホのアラート機能を使って、勉強時間や休憩時間を管理することも可能です。
例えば勉強時間や休憩時間をスケジュールとして登録しておくと、開始時間や終了時間にアラームが鳴ります。
なかなか勉強が続かない人には、目標達成をサポートしてくれるアプリがおすすめです。
例えば勉強内容や目標、制限時間を設定して、集中して勉強に取り組むためのアプリなどがあります。制限時間になると記録され、目標をどれだけ達成できたか一目でわかるので、とても便利です。
わからないことをすぐに調べて解決する
スマホを使えば、わからないことをすぐに調べることができます。受験勉強においては、わからないことを放置することは避けるべきでしょう。スマホがあれば、調べてその場で解決できるため便利です。
例えば英単語であれば、スペルや意味を調べることはもちろん、発音を音声で確認することもできます。教科書を見たり辞書を引いたりしなくても、スマホを使えば必要な情報をピンポイントで見つけられるため、時間を節約して効率よく受験勉強を進められるでしょう。
勉強した内容をスマホに記録する
勉強の記録を残したいと考える受験生も多いのではないでしょうか。
実際に、勉強した内容を記録すると勉強の効率がアップするといわれています。
勉強した日数や時間、問題数やページ数などを記録することで、もっと記録したいという欲が出てきて、勉強に対するモチベーションが上がるのです。
スマホを使えば、アプリで簡単に勉強の記録ができます。
勉強した内容を記録すると、勉強の進み具合も一目でわかります。そのため、苦手な単元なども把握しやすく、効率よく勉強を進められるでしょう。
暗記した内容を記録しておいて、移動時間などを利用して復習することも可能です。
まとめ
スマホは受験勉強の邪魔になるといわれていますが、スマホのない生活をすれば、成績が上がるわけではありません。
スマホは、使い方によっては受験勉強にプラスに働くことさえあります。
受験勉強のためにスマホ断ちをするのもよいですが、スマホを味方につけて上手に活用してみてはいかがでしょうか。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

勉強のやる気が出ない受験生はどうすべき?すぐできることから本質的な解決方法7選
2022.07.01
「受験生なのに勉強のやる気が出ない……」と、なかなか勉強に気持ちが向かず集中できないことを悩むお子さまは多いようです。保護者としても、そんなお子さまの様子が心配でつい口を出してしまうことがあ...
-

記述問題とは?苦手を克服して差をつけるための解き方と記述方法
2021.10.14
記述問題とは、問いに対して文章や計算式での解答が求められる出題形式のことです。 記述問題を勉強したくてもどこから手をつけてよいのかわからず、苦手とする人は多いでしょう。 しかし、近年では中学...
-
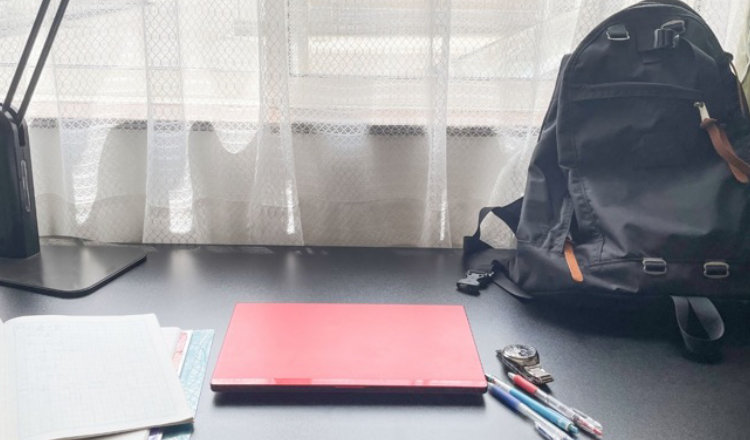
受験生の持ち物を徹底解説!必携アイテムから勉強グッズまで
2021.09.03
学校に入学するための受験の機会は、中学受験から大学受験までありますが、入試当日の持ち物に迷う受験生や保護者は多いでしょう。 受験に何を持って行くべきか把握できていないと、準備しながらも不安に...









