2021.07.26
受験生のケアレスミス対策!なくすためにできることとは?

志望校への合格に近づくためには、受験の際に1点でも多く得点することが重要になります。そこで注目すべきなのが「ケアレスミス」です。ケアレスミスによる小さな失点は重なることで合否にも影響し、今後の進路を大きく変える可能性があります。
そこで本記事では、ケアレスミスが起こる理由や具体例、それらを防ぐための対策を詳しく紹介します。ケアレスミスによる失点に悩んでいる受験生は、ぜひ参考にしてください。
対策したい「ケアレスミス」とは?
受験勉強やテストにおいて「ケアレスミス」という言葉を耳にしますが、そもそもどのような意味なのでしょうか。ここでは、ケアレスミスの意味や語源、類義語について解説します。
ケアレスミスの意味
ケアレスミスとは、「知識や能力の不足ではなく、不注意による誤り」「そそっかしい間違い」のことです。
受験勉強やテストにおいては、ケアレスミスという言葉は「知識は身についており十分勉強していたにもかかわらず、問題の読み違えや答え方の認識違いなどの小さなミスで失点する」という意味で使われます。そのため、知識不足や勉強不足による失点は、ケアレスミスには該当しません。
ケアレスミスの語源
ケアレスミスという言葉を英語だと思っている人もいるでしょう。しかし、実はケアレスミスは「careless mistake」を略してできた和製英語です。
「careless」という単語は「care」と「less」に分けられ、それぞれ「注意」と「失う」という意味です。「mistake」は「間違う」という意味です。
よって「careless mistake」は「注意不足によるミス」と訳せます。日本では広く、この言葉を略した「ケアレスミス」が同じ意味で使われています。
ケアレスミスの類義語
ケアレスミスには、以下のような類義語があります。
・うっかりミス
・凡ミス
・へま
・過失
共通点は、実力不足によって起こったミスではなく、不注意によって引き起こされたミスであることです。1点の失点が合否を左右する受験においては、訓練や意識の持ちようでケアレスミスを防ぐことが大切です。
受験でよくあるケアレスミスはどのようなもの?
ケアレスミスを防ぐには、まずどのようなケアレスミスが起こる可能性があるのかを知る必要があります。一口にケアレスミスといっても、科目や解答方法などによって種類が異なるからです。
そこで、受験において起こりやすいケアレスミスを5種類紹介します。ケアレスミスに悩んでいる受験生は、まず自分が起こしやすいケアレスミスを把握しましょう。
単位を書き忘れた
「単位を書き忘れた」というケアレスミスは、起こりやすいといえます。計算結果は合っていても、単位を書き忘れると減点の対象になり、場合によっては0点になることもあります。
また逆のパターンもあり、単位を書く必要がないのに書いてしまうと減点されます。
これは、数学や理科の記述式問題で起こりやすいケアレスミスです。問題文や解答欄をよく見て、単位を書くかどうかを判断しましょう。
漢字を書き間違えた
「漢字を書き間違えた」というケアレスミスもよく起こります。例えば、「価値観」と書いたつもりが「価値感」と書いてしまうようなミスです。
受験本番の焦りや緊張で起こることもありますが、間違って覚えてしまっている可能性もあります。上記のようなミスは多いため、辞書を使って正しい漢字を確認し、覚えるようにしましょう。
解答欄を間違えて記入してしまった
「解答欄を間違えて記入してしまった」というミスも少なくありません。せっかく時間をかけて正解を導いても、違う解答欄に記入してしまうと点数をもらえません。
試験中にその間違いに気づけば、訂正をするためのタイムロスだけで済みますが、気づかずに提出してしまうと他の問題の解答もずれてしまっている可能性が高いため、大きな失点につながります。
問題文を読み間違えた
「問題文を読み間違える」というケアレスミスもあります。例えば、問題文に「選択肢の中から正しくないものを選びなさい」と書かれていたのに、「正しいもの」を選択してしまうというミスです。
これは、先入観を持って問題文を読んでしまっていることや、問題文の読み込みが甘いことが原因で起こります。どんな場面であっても、問題文はしっかりと読み込むようにしましょう。
ケアレスミスで20点近く落とすことも
ケアレスミスによって、20点近く落とす可能性があることをご存じでしょうか。ある調査によると、「1回の試験のケアレスミスによって16~20点の失点をした人は、全体の受験者の約3割にも上った」という結果が出ています。
受験の終盤に差し掛かった受験生であれば、16~20点上げるのは至難の業です。しかし、ケアレスミスをなくすことができれば、他の受験生に大きな差をつけられる可能性があります。
ケアレスミスはなぜ起こる?
ここまでケアレスミスの具体例を紹介してきましたが、そもそもケアレスミスはなぜ起こるのでしょうか。ここからは、ケアレスミスが起こる原因を4つ紹介します。
作業に「慣れ」が出てしまっている
原因の1つ目は、作業に「慣れ」が出てしまっていることです。普段から同じようなことを繰り返し行うことに慣れてしまうと、自分を過信し、緊張感がなくなります。その結果注意が散漫になり、ケアレスミスに気づかなくなってしまうのです。
受験勉強においても、答えの出し方や考え方がパターン化している場合は、ケアレスミスが起こりやすいといえます。
体調が万全でない
2つ目は「体調が万全な状態でない」ことです。例えば、試験中に頭痛や腹痛に襲われると、試験どころではなくなります。
試験に備えてどれだけ勉強していたとしても、試験本番で体調が万全でなければ本来の力を発揮できないだけでなく、試験に集中できずケアレスミスが起こる可能性が高まります。
集中力が切れている
3つ目は「集中力が切れている」ことです。受験当日は、1日のうちに複数の科目の試験を受けることになります。特に午後の科目では集中力が弱まり、いつもなら見落とさないようなところを見落とすといったケアレスミスが発生しやすくなります。
そのため、試験時間中しっかり集中できるよう、日頃の勉強で訓練しておきましょう。また、試験中に集中力が切れてしまった場合の対処法を考えておくことをおすすめします。
作業に効率を求めている
「作業に効率を求めている」こともケアレスミスの原因です。受験当日は時間との戦いでもあるので、より効率的に問題を解きたいと考える受験生は少なくないでしょう。
しかし、得意な問題や解ける自信のある問題を一気に解いたり、時間を気にして早く終わらせようとしたりすると、ケアレスミスが起こりやすくなります。
戦略的に問題を解いていくのもよいことですが、ケアレスミスで失点してしまってはもったいないので注意しましょう。
ケアレスミスをしやすい人
性格によって、ケアレスミスをしやすい人もいます。ここで紹介する性格が自分に当てはまるかどうか、確認してみましょう。
せっかちな人
ケアレスミスをしやすい人として、まず挙げられるのは「せっかちな人」です。「早く問題を解き終わりたい」「早く次の作業に移りたい」と考えながら問題を解いている受験生は要注意です。
このように考えていると、大切な記述を見落としたり、解答欄や解答方法を間違えたりといったケアレスミスが起こりやすくなります。
適当・おおざっぱな人
「適当・おおざっぱな人」もケアレスミスをしやすいといえます。問題を解き終わった後に見直しをせず、「多分解けているだろう」「疲れたし、もういいや」と思ってしまう受験生はケアレスミスを起こす傾向にあります。
おおざっぱで小さいことを気にしない性格であったとしても、勉強では細かいところまで目を向けるように意識しましょう。
自信過剰な人
試験のケアレスミスにおいて特に危険なのが「自信過剰な人」です。試験勉強を頑張ったことが自信につながっているのはよいことですが、それが過剰だと裏目に出るおそれがあります。
問題を解くときに「この科目は得意だから大丈夫」「この問題は簡単に解けるから余裕!」などと考えてしまうと気が抜けてしまい、ケアレスミスをしてしまうことがあるので注意しましょう。
ケアレスミスを減らす・なくす対策【受験生編】
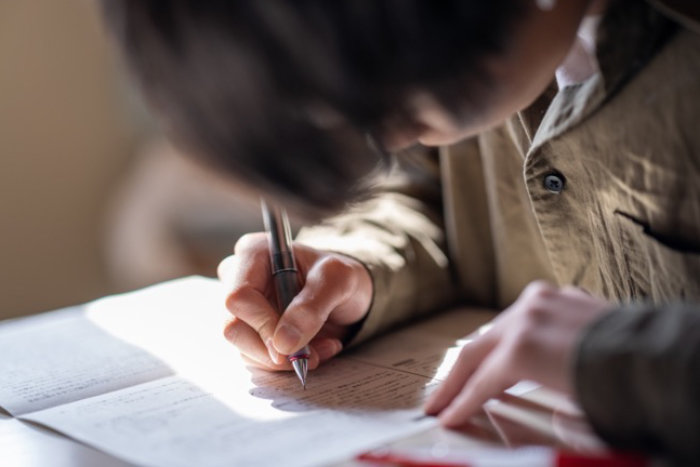
ここからは、受験生ができる「ケアレスミスを減らす・なくす対策」を7つ紹介します。はじめからすべて実践するのは難しいですが、受験当日には習慣になっているように、少しずつ身につけていきましょう。
文章は2回読む癖をつける
1つ目の対策は「文章を2回読む癖をつける」ことです。普段から2回読む癖がついていれば、1回目に見落としてしまった重要な情報も、2回目でしっかり押さえることができます。
「2回読むということは、時間も2倍かかるのでは?」と思った人もいるでしょう。しかし習慣になっていれば、2回読んだとしても時間内に解き終わるスピードになっているはずです。
大事だと思う部分に線を引く
2つ目は「大事だと思う部分に線を引く」ことです。この方法は、国語や英語で出題されるような長文問題を正確に読み取る際に非常に有効です。
線を引かずに読んでも内容は頭に入りますが、重要なことがどこに書かれていたかわからなくなるため、いざ解答する際に苦戦します。そのため、キーワードや重要な文には線を引くようにしましょう。
また、ケアレスミスが起こりやすい「正しくないものを選びなさい」「当てはまらないものを選びなさい」といった部分は線を引いておくだけで、ミスが少なくなります。
指さし確認をする
3つ目は「指さし確認をする」こと。例えば、国語の読解問題で長文をただ目で追うのは危険です。気づかない間に1行飛ばして読んでしまう、重要な部分を見落としてしまうといったケアレスミスが起こりやすくなるからです。
指さし確認をすると、確認の精度が高まります。日頃から問題を読む際は、指さし確認をするように心掛けましょう。
字をていねいに書く
4つ目は「字をていねいに書く」ことです。時間がない中で解答しようとすると、字が走り書きになってしまっていることもあります。しかし、採点者が読めないほど字が汚いと、減点されたり誤答と判断されたりするおそれがあります。
また、解答を導く過程で書いたメモの字が汚いと、自分でも読めなかったり、誤読したりするおそれがあります。常日頃から字はていねいに書き、誰でも読める字を意識しましょう。
解いた後は必ず見直しをする
5つ目は「解いた後は必ず見直しをする」ことです。見直しの時間は、自分の解答を客観的に見つめることができる貴重な時間です。「完璧に解けている」「間違っているはずがない」などと思わず、他人の解答用紙を見るつもりで見直しましょう。
また、客観性を保つために少し時間をおいてから見直しをすると、間違いに気づきやすくなるのでおすすめです。
算数や数学では検算をする
6つ目は「算数や数学では検算をする」ことです。検算とは、一度解いた問題を別の方法で計算し、解答の正しさを確かめることです。検算をしっかり行えば、計算においてはほとんどのケアレスミスを防ぐことができます。
例えば、「38-9=」という問題の答えは29ですが、検算ではこれを確かめるために「9+29=」を計算し、38になることを確認します。検算を学ぶことは他の解答プロセスを学ぶことにもなるので、基礎的な学力の向上にもつながります。
体調を管理する
最後に紹介するのは「体調を管理する」ことです。体調管理は、受験生にとって勉強と同じくらい大切といっても過言ではありません。自分のベストパフォーマンスを発揮するために、睡眠時間や食事、息抜き時間などを管理しましょう。
体調を整えておくことで、試験本番でも集中力をキープでき、ケアレスミスを防ぐことができます。また、「試験の日の朝食はコレ!」「試験会場に行くときはこの音楽を聴く」など、自分のモチベーションを高められるルーティンを作るのも有効です。
ケアレスミスを減らす・なくす対策【保護者編】
保護者の言葉や振る舞いは、受験生に大きな影響を及ぼします。ケアレスミス対策も同様で、受験生だけが対策を行えばよいというものではありません。ここからは、「保護者ができるケアレスミスを減らす・なくす」対策を3つ紹介します。
ケアレスミスをしたことを責めない
1つ目は「ケアレスミスしたことを責めない」ことです。模試などでケアレスミスを見つけると、つい「これは解けたはず」と助言したくなるものです。
しかし、ケアレスミスを見つけて一方的に指摘されたお子さまは責められた気持ちになり、「ケアレスミスをしたら怒られる」「次もしてしまったらどうしよう」という気持ちになり、さらに緊張したり不安になったりします。
ケアレスミスを見つけたときは責めるのではなく、原因と改善策を一緒に考えるようにしましょう。
速く解けたことをほめすぎない、無理に速さを求めさせない
2つ目は「速く解けたことをほめすぎない、無理に速さを求めさせない」ことです。保護者からの承認は、お子さまの安心感やモチベーションにつながります。しかし、解答の速さをほめすぎるのは禁物です。
解答の速さをほめすぎてしまうと、お子さまは「速く解けること=よいこと」と思い込み、解答プロセスや正答率よりも速さを重視してしまいます。
ケアレスミスが起こる原因でも説明したとおり、スピードや効率を追求しすぎると、見落としや見間違いといったケアレスミスが起こりやすくなります。
お子さまの体調を管理する
3つ目は「お子さまの体調を管理する」ことです。大人でも気を抜くと生活リズムが乱れてしまうものですが、お子さまの生活リズムを本人任せにするのはさらに危険です。そこで、最低限管理しておきたいことを紹介します。
・睡眠時間を確保するために夜遅くまで勉強させない
・適度に息抜きの時間を設けて、その時間をだらだらと長引かせない
・栄養バランスの取れた食事を用意する
保護者が口を出しすぎるとお子さまはストレスに感じることもあるため、お子さまの反応や様子を見ながらサポートの方法を工夫しましょう。
体を動かすことはケアレスミスを減らす近道
ここまで、ケアレスミス対策について解説してきましたが、それ以上に効果的なケアレスミス対策があります。それは「体を動かすこと」です。ここからは、体を動かすことによってケアレスミスを減らす方法を紹介します。
なぜ体を動かすとケアレスミスが減るのか
「体を動かすこととケアレスミスは関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、実は大いに関係があります。特に効果的なのが、「指さし呼称」です。
指さしを行うことによって筋肉が刺激され、声を出すときに口の周りが動くことで咬筋が刺激されます。すると、体内の血流が増加します。それに伴って前頭葉の血流も増加するので、ケアレスミスを自ら発見できる可能性が高まります。
指さし呼称は鉄道機関士が考えたもので、乗客を安全に目的地まで送り届ける際、集中力を切らさないために行われます。現在では医療現場や建設現場など、ケアレスミスが許されない現場で広く取り入れられています。
指さし呼称を行うとミスが約6分の1になる!
指さし呼称はケアレスミス対策として、非常に効果があります。
1994年に財団法人(現、公益財団法人)鉄道総合技術研究所が行った実験によると、「指さし+呼称」を行った際のボタン操作ミス発生率は0.38%、何もしなかった場合は2.38%でした。
指さしと呼称を行った場合、何もしない場合と比べるとミスの発生率を約6分の1に抑えられるのです。
勉強をする環境にもよりますが、日頃からケアレスミス対策として、指さしと呼称を行いながら勉強を進めるとよいでしょう。
指さし確認だけでもケアレスミス対策になる
先ほど紹介した実験には、別の報告もあります。それは「指さし」だけの場合でも、ボタン操作ミスの発生率は0.75%になるというものです。
「指さし+呼称」を行った場合と比べるとミスの発生率は上がりますが、何もしなかった場合と比べると、ミスの発生率を約3分の1に抑えられるのです。
試験中に声を出すことはできませんが、指さし確認だけでも行って、ケアレスミスを減らすようにしましょう。
ケアレスミスをなくすには徹底した対策が大切!
ここまでさまざまなケアレスミス対策を紹介してきましたが、それらは一朝一夕で身につくものではありません。そのため、日頃からケアレスミス対策を徹底することが大切です。
ケアレスミスはいくら対策をしてもゼロにはできない
ケアレスミスを完全になくすことはできません。どれほど注意していても、人間はミスをします。また、ケアレスミスを起こさないよう慎重になりすぎると、すべての問題を時間内に解ききれないかもしれません。
ケアレスミスは過剰に警戒するのではなく、日頃から対策を行って習慣化することが大切です。
大事なときにミスをしない対策をしよう
受験生なら誰でも「1点でも多く取りたい」と思うでしょう。そんな受験生を助けてくれるのは、地道に取り組んできたケアレスミス対策です。普段からできるケアレスミス対策には、以下のようなものがあります。
・ケアレスミスが起きた問題や思考のプロセスを書き出し、原因を分析する
・ケアレスミスの内容をノートにまとめたり周囲の人に伝えたりして、思い出しやすい環境を作る
これらを日常的に行っていれば、自分のケアレスミスの傾向や、ケアレスミスが起きやすい時間・科目・解答形式といった重要なデータが手に入ります。
まとめ
今回はケアレスミスの理由や具体例、それらを防ぐための対策を紹介しました。
どんなに勉強熱心な受験生でも、ケアレスミスを完全になくすことはできません。しかし、日頃からケアレスミス対策を行っていれば、本番での致命的なケアレスミスを防ぎやすくなるはずです。
過去問を解くことも大切ですが、ケアレスミス対策も日々の勉強の中に取り込んでいきましょう。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

勉強のやる気が出ない受験生はどうすべき?すぐできることから本質的な解決方法7選
2022.07.01
「受験生なのに勉強のやる気が出ない……」と、なかなか勉強に気持ちが向かず集中できないことを悩むお子さまは多いようです。保護者としても、そんなお子さまの様子が心配でつい口を出してしまうことがあ...
-

記述問題とは?苦手を克服して差をつけるための解き方と記述方法
2021.10.14
記述問題とは、問いに対して文章や計算式での解答が求められる出題形式のことです。 記述問題を勉強したくてもどこから手をつけてよいのかわからず、苦手とする人は多いでしょう。 しかし、近年では中学...
-
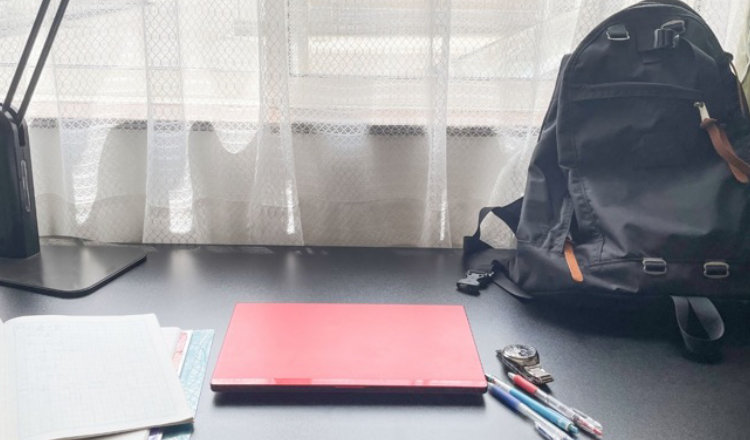
受験生の持ち物を徹底解説!必携アイテムから勉強グッズまで
2021.09.03
学校に入学するための受験の機会は、中学受験から大学受験までありますが、入試当日の持ち物に迷う受験生や保護者は多いでしょう。 受験に何を持って行くべきか把握できていないと、準備しながらも不安に...









