2021.10.14
記述問題とは?苦手を克服して差をつけるための解き方と記述方法

記述問題とは、問いに対して文章や計算式での解答が求められる出題形式のことです。
記述問題を勉強したくてもどこから手をつけてよいのかわからず、苦手とする人は多いでしょう。
しかし、近年では中学受験から大学受験まで幅広く記述問題の出題が増え、その重要性は増すばかりです。
今や、記述問題の対策を行わずに受験を突破することは不可能だといっても過言ではありません。
この記事では、記述問題を得点源に変えるために知っておくべき解き方や記述方法、学習方法を解説します。
記述問題とは
記述問題とは、問題の答えを単語だけでなく「文章」で答える問題形式のことです。
受験に出る問題形式は、大きく「記述式」「短答式」「選択式」の3つに分かれます。
短答式は数値や用語を単語で答える形式、選択式は複数の選択肢から解答として当てはまるものを選択する形式を指します。
また、文や文章を書かせる「文章記述問題」を単純に記述問題と呼んでいる場合もあります。
記述問題の重要性
「国語の記述問題ができない」と記述問題に対して苦手意識を持つ受験生が多く、中には白紙で提出する人も少なくありません。
しかし、ほかの形式の問題に比べて配点が高いことが多く、また、近年、教育改革の一環で出題傾向に変化が見られ、中学受験から大学受験まで多くの学校が記述問題を重視するようになってきています。
このような背景から、記述問題は周りとの差をつけやすい問題であり、多くの学校が採用しだした問題形式なので、しっかりと対策を行っていく必要があります。
記述問題が出題される理由
今までは必要な知識を使いこなせるかを問う選択式の問題が主流でした。
しかし、「先行きが予想しづらいこれからの社会では、知識の量だけでなく、自ら問題を発見し、答えや新しい価値を生み出す力が重要になる」という国の考えから、記述問題こそないものの「思考力・判断力・表現力」を総合的に評価する大学入学共通テストが2021年度から採用されました。
記述問題はそれらの能力が求められる問題で、解答そのものだけでなく、その解答に至るまでのプロセスまで評価されます。
このような背景から「自ら考えることのできる人」を求めて、難関校ほど記述問題が出題される傾向が高くなっています。
記述問題を巡る動向|入試への影響は?
上述のように、入試における記述問題は増加傾向にあり、この背景には文部科学省によって進められている大学入試改革が関係しています。
大学入試改革では、入試においてこれまでの知識偏重型から「思考力・判断力・表現力」が重視されることとなり、生徒たちの「書く能力」を試すために記述問題が推進されることとなりました。
その一環として大学入学共通テストでは、センター試験時代にすべてマークシート形式だった問題形式を一部変更し、国語と数学への記述問題の導入が検討されました。
しかし協議の結果、文部科学省は「採点ミスを完全になくすことは難しい」「自己採点の不一致を改善できない」と判断し、記述問題の導入は見送られることとなったのです。
大学入学共通テストで記述問題は導入されなかったものの、文部科学省が打ち出した今後の教育方針は変わらないため、各学校の入試での記述問題重視は着実に進行しています。
実際、これまで記述問題の出題が比較的少なかった中学入試や難関私立大学でも記述問題の採用が進んでいます。
したがって、今後の学習では記述問題対策をしっかりと行い、臨機応変にさまざまな問題に対応できるだけの学力を身につけることが求められます。
記述問題の基本的な解き方とは?
記述問題を解くためには、まず基本的な解き方を知っておく必要があります。
順番に見ていきましょう。
問題文を正確に読み取る
まず、出題された問題文は必ず一字一句、正確に読み取りましょう。
設問を読み、問われている内容の意味を理解することが大切です。
理解できないまま進めると、設問に関係のないところを読むのに時間がかかったり、問題を読んでから再度本文を読む必要があったりします。
これではかえって時間がかかるため、問題を読み取れるまでは解答を始めないのが賢明です。
また、設問に条件が設けられている場合は、見落としてしまうと失点につながるため注意しましょう。
課題文や資料などがある問題であれば、問題を理解してから読むようにしたほうがスムーズに解答できます。
解答文全体の見通しを立てる
解答を作る際、いきなり文章を書き始めるのは禁物です。
記述に入る前に、解答全体の見通しを立ててから臨むようにしましょう。
見通しを立てずに解答し始めると、字数制限内に必要な内容が入らない、設問の趣旨から外れた内容になるなど、うまく解答を作れないことがあります。
まずは、求められる解答の結論は何なのか、「ゴール」をきちんと見据えることを心がけましょう。
日本語は文末で結論を書くのが一般的です。
したがって、記述問題を解く際は、文末に来る結論を決めて全体の見通しを立てるとよいでしょう。
結論を決めてから逆算して文章を組み立てることで、間違った解答を書く可能性を減らせます。
解答に盛り込むべき要素をメモする
解答の見通しが立ったら、本文を読んで解答に入れるべき項目を探しましょう。
その際、解答に含める内容をメモとして書き出すことが重要です。
記述問題にはそれぞれ採点基準があり、字数によって必要な項目の数が決まっていることが多く、一般的にその項目ごとに部分点が与えられます。
意識しておくことは、記述問題の答えは「自分で考え出すのではなく、文章中から探し出す」ということです。
最難関レベルの入試の記述問題でない限り、ほとんど文章中の言葉を抜き出して解答を作ります。
解答に必要な要素を考え、重要なキーワード、人物、出来事は何かを探し、1つ1つメモに書き出しましょう。
文章として組み立てる
解答を作るためのメモを過不足なく書き出せたら、はじめに立てた見通しに沿って文章として整えていきましょう。
文章を組み立てる際は、いきなり書き始めるのではなく、書き出したメモを図のように書き出し、それぞれの関係を客観的に見てみると内容がわかりやすくなります。
文章は基本的に頭から書いていきますが、まずは見通しを立てたときと同じように、結論から組み立て始めることが大切です。
結論を決めたあと、主語や述語を把握して字数に合わせて文章を調整すると、解答ができあがります。
最後に全体を見直して、意味が通っているか確認するとよいでしょう。
文章のテーマごとのコツ
国語は主に「小説文」、「説明文・論説文」の2つに分けることができます。
以下では記述を解くうえでのコツをテーマごとに紹介します。
小説文は「気持ち」と「理由」セットで組み立てる
小説文の記述問題を解くうえで抑えておくべきコツがあります。それは「気持ち」と「理由」の構成で組み立ていくことです。
まずは、傍線部の「気持ち」が「プラス」か「マイナス」かを読み取って、記述の最後の部分をどのように書くかを決めましょう。
(プラスの場合)
・~うれしく思う気持ち。
・~幸せに思う気持ち。
(マイナスの場合)
・~悲しく思う気持ち。
・~はかなく思う気持ち。
この次に、なぜそのような「気持ち」になったのかという「理由」を本文から探し出しましょう。その「理由」となることは「出来事」が原因となることが多いです。
どのような「出来事」により、登場人物の「気持ち」が変化したのか注目するようにしましょう。
(解答例)
・算数のテストで100点を取ることができたのでうれしく思う気持ち。
・雨が降ったせいで、体育祭が中止になってしまい悲しく思う気持ち。
説明文・論説文の記述は3つのタイプに分ける
説明文・論説文の記述は以下に紹介する3つのタイプにまとめることができます。
・ 傍線部の指示語の指すところを探す
傍線部に「このような」や「そのような」などと書かれている場合、このタイプに当てはまります。
このタイプのコツは答えが基本的に傍線部の「直前」に書かれているので、そこから探し出しましょう。
・傍線部の理由を探す
問題文に「なぜですか」や「理由を答えよ」と書かれている場合、このタイプに当てはまります。
答えとなる部分は傍線部より「後」に書かれていることが多いです。「から」や「ため」を含む部分を探し出すことがコツです。
・傍線部の言いかえを探す
上記の2つのどちらにも当てはまらない場合、このタイプの問題に当てはまります。
傍線部の「言いかえ」となるところを探していきます。傍線部と同じ「内容」、「形式」の語句を傍線部の「前後」から探し出しましょう。
減点されない記述方法
記述問題は、意識していないと細かいところで減点されてしまうことがあります。
ここからは、どのようなことが減点対象になるのか、どうすれば減点を防げるのかを説明します。
設問に文末を合わせる
記述問題はある程度設問の形が決まっており、解答を作る際は、その設問が求めていることに対応した文末にしなければなりません。
例えば、設問が「~なのはなぜか」と理由を聞くような問題であれば、「~だから」と、理由を答える文末で終える必要があります。
他にも、設問が「目的は何か」であれば、「~ため」といった文末にしなければなりません。
形式的で堅苦しく感じるかもしれませんが、記述問題では「設問を正しく理解している」ことを採点者に示すことが重要です。
設問に合わせた文末で答えることで、設問の意図を理解できていることを採点者に伝えましょう。
主語と述語を完全に対応させる
記述問題を解く際は、文章の主語と述語が正確に対応するように書く必要があります。
特に指定文字数の多い問題になると、主語と述語が一致しないことが多くなるので注意しましょう。
主語と述語が遠くなると間違えやすいため、極力主語と述語は近くに置くことがポイントです。
日本語は主語を省略できることも多く、必ず主語を書かなければいけないわけではありません。
しかし、主語がはっきりと書かれた解答には矛盾が生じにくく、採点者にも内容が正確に伝わりやすくなります。
また、設問で求められているものとは異なる主語の解答を書いてはいけません。
例えば、「AがBは怒ったと感じたのはなぜか」という問題が出たときに、記述問題に慣れていないと「Bが○○をしたから」とだけ答えを書いてしまいがちです。
しかし、設問文の主語はAなので、「AがBは怒ったと感じたのは、Bが〇〇をしたから」と、Aが主語になる解答を作る必要があります。
説明不足を残さない
記述問題は、採点者が文章の内容を知らないものとして、解答文だけで文章の因果関係がわかるようにしなければなりません。
本文に記載があるから説明しなくてもわかるだろうと省略して書くと、何を伝えたいのかがわからない文章となり、点数がもらえなくなります。
解答に必要な要素は隅々まで説明しましょう。
また、指示語が多いと意味が伝わりづらくなるため、失点につながります。
「そのような」や「この」などを多用すると、その文章だけでは意味がわからない文章になるため、あいまいな指示語は残さずに解答しましょう。
一文は短く抑える
解答文に書く文章は一文を短くすることを意識しましょう。
一文を区切らずに長い文章を書くと、主語と述語の不一致が原因で論理が崩れやすくなります。
短く句点で区切り、接続詞を用いて文章を構成するほうが失敗は減ります。
記述問題に慣れていない人は、特に一文を短くすることを心がけて答えを作りましょう。
内容を重複させない
記述問題はその場の思いつきで書き始めると、文章内で同じ内容が重複してしまうことがよくあります。
一文の中に同じ単語や表現が何度も使われていないかどうかを確認しましょう。
同じ内容が重複している場合、文章として無駄があるだけでなく、本来書くべき必要な事柄が抜けてしまっている恐れがあります。
そのような事態を避けるためにも、必ず解答を書き出す前に要素を洗い出してから書き始めましょう。
誤字脱字をなくす
誤字脱字は当然ながら減点対象になるため、極力減らさなければなりません。
特に漢字の間違いは、線が1本足りないだけで減点されてしまうこともあるため注意したいポイントです。
受験は1点の差で合否が変わってしまうため、そのような防げるミスは確実に防ぎましょう。
必ず解答を読み直して推敲する
解答を書き終えたら見直して、文章に減点ポイントがないか入念にチェックしましょう。
先ほど紹介した誤字脱字も、見直しで気づけば失点を防げます。
見直しをするためには、あらかじめ見直しする時間を計算して問題を解いていく必要があります。
ただし、見直したときに見当違いな答えを書いていることに気づいて、文章を丸々書き直さなければならなくなってしまった場合、やり直すのは時間的に厳しいでしょう。
見直しの際に確認するのは誤字脱字や「てにをは」レベルで済むように、事前に解答の全体をイメージして、計画性を持って記述問題に取り組むことが重要です。
記述問題の字数制限
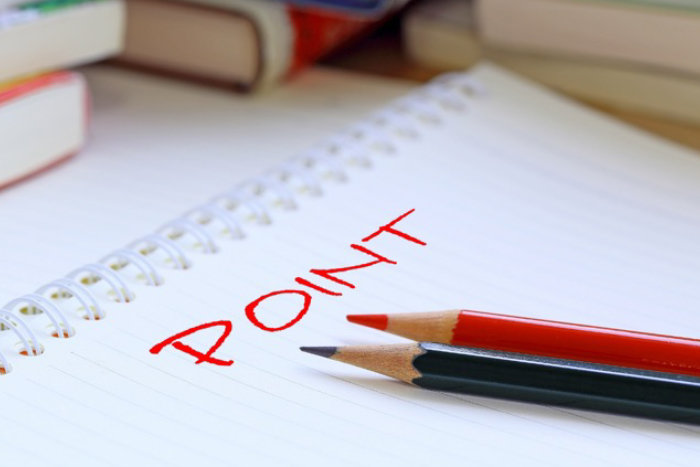
記述問題の多くには「字数制限」が設定されています。
字数制限のある問題を解く際に注意すべき点を確認しておきましょう。
字数制限は厳守する
記述問題では「〇字以内」や「〇字程度」と、字数制限を設けているものが多くあります。
解答欄にマス目が用意されている場合、単純に文字数をカウントする用途のものと考え、原稿用紙のように段落や句読点などのルールを適用しないよう気をつけましょう。
「〇字以内」と字数が指定された場合は、その字数の「8割以上」書く必要があります。
字数制限がなく、マス目のない解答欄が用意されている場合もありますが、その場合も過不足なく要素を盛り込むことが重要です。
常識の範囲の文字サイズでちょうど収まるように解答を書きましょう。
字数制限は大ヒント
実は字数制限があることこそが、解答のヒントになります。
指定された文字数が少なければ簡潔で的を射た解答が、文字数が多ければ情報量の多い解答が求められている、というように、字数制限から出題者が何を求めているのかを推し量ることが可能です。
したがって、字数が少ないから簡単だというわけではありません。
字数が少ないと、短い文章で要点を伝えなければならないため、入れ込む要素の選択や書き方が難しくなります。
大学によっては字数を明確に指定せずに、マス目のない解答欄が用意されるような問題もあり、臨機応変な対応が求められます。
日ごろの学習で、解答欄の大きさに合わせてどの程度の文字数が必要なのかの感覚をつかんでおきましょう。
字数から逆算して解答を組み立てる
そもそも記述問題に字数が指定されていることが多いのは、出題者が想定した模範解答がその文字数で用意されているからです。
したがって、記述問題を解く際は、字数から逆算して解答を組み立てることができます。
記述問題ではおおむね20字に1つ盛り込むべき要素が存在し、1つの要素ごとに部分点が与えられることが一般的です。
つまり、指定字数を20で割ると、盛り込む要素の数が大まかにわかります。
例えば「80字以内でまとめよ」という問題では、盛り込む要素が4つあると考えられ、その4つを本文から見つけ出すのが記述問題の解き方です。
基本的に字数制限通りに書けば過不足のない解答となるため、字数の8割に満たない解答になった場合、必要な要素が不足している可能性があると考えられます。
まずは字数に応じて必要な要素を集め、それらをつなげて文章化する解き方を身につけましょう。
記述問題ができないときの対処方法
記述問題に慣れていないと、どうしても解答を書けないときもあるでしょう。
ここでは、そのような場合どうすればよいのかを解説します。
書けそうになくても解答欄は埋めよう
記述問題でうまく解答ができない場合は、「いかに部分点を取るか」が重要です。
整った文章に仕上げられなくても、必要な要素が入っていると部分点がもらえることがありますが、白紙で提出した場合は必ず0点です。
白紙で提出するぐらいであれば、苦しまぎれでも何か書くことで部分点がもらえるかもしれません。
満点を取れるに越したことはありませんが、記述問題では、まずは部分点を取ることを意識しましょう。
1点でも多く取ることができれば、白紙の受験生とは確実に差がつきます。
字数制限がある場合は、なんとかして字数分を埋めるようにしましょう。
採点者に少しでも「理解できている」ことを伝える
記述問題では、解答そのものだけではなく、「どこまで理解できているのか」も見られます。
したがって、解答を作る際は、解答に辿り着くまでのプロセスを採点者に示すことが重要です。
設問について何がわかったか、どのような解法を考えたかなどの跡を残していきましょう。
例えば、数学であれば図を書く、国語であれば整った文章にこだわらずに見つけた要素を入れ込むだけでもよいでしょう。
完璧な解答を目指すのではなく、途中段階でも考えていることを書き出して解答することで得点につながります。
記述問題に強くなるには
記述問題を得点源にできれば、受験で有利になるでしょう。
最後に、記述問題に強くなるために必要な考え方や学習方法を紹介します。
各教科の内容をしっかり理解する
記述問題を解くにあたり、まずは各教科で習った内容をしっかりと理解することを意識しましょう。
記述問題で必要なのは「教科ごとの知識」と「その知識を文章で表現する力」です。
つまり、その教科の知識がなければ、どれだけ文章で表現する力を磨いても得点にはつながりません。
まずは教科書の内容を理解し、問題演習を重ねて教科ごとの知識を完全に理解することに努めましょう。
国語・現代文を勉強する
記述問題は出題者の意図を正確に読み取り、わかりやすい言葉で解答を作らなければなりません。
この能力は国語・現代文で学ぶ内容そのもので、記述問題を解く力は国語力に比例します。
文章を書く力だけでなく、語彙力や読解力も身につくため、基本的な国語力を高めることは非常に有効です。
国語をしっかり学ぶことで、数学を含む全教科の記述問題にも対応できるようになります。
もちろん、国語では早期から記述問題が多く出題されるので、まずはその対策から始めて、記述問題への苦手意識を克服していきましょう。
普段から自分の考えを言葉にする習慣をつける
記述問題の本質は「考えや理解したことを言葉で人に説明すること」です。
解くためにはさまざまなテクニックや考え方がありますが、文章・口頭を問わず、自分が考えていることを言葉にすることが、何よりのトレーニングになります。
作文、読書感想文、HR、部活動など、自分の考えを伝える機会は積極的に活用しましょう。
あらゆる機会で自分の考えを発信し、表現することへの苦手意識を取り除くことが大切です。
実用文から学ぶ
記述問題では、「簡潔で論旨がはっきり伝わる文章」を書くことが求められます。
文学作品のようないわゆる「名文」は読み手に解釈を委ねる部分もあり、要点がうまく伝わるとは限りません。
そのため、名文のような文章を書くことが、記述問題が求める条件を満たすことにつながるわけではないことを覚えておきましょう。
無味乾燥に見えますが、新聞記事のように事実を確実に伝える実用文のほうが、記述問題の文章を書くうえでは参考になります。
日ごろから新聞や論説文を読んで、記述問題で参考となる文章の書き方に慣れていきましょう。
教科書に出てくる説明文も、模範解答そのものです。学校で学んだことを自分のものにしていきましょう。
演習問題を解く
記述問題の特徴は、自分で勉強することが難しい点にありますが、上達するためには実際に書いて慣れることが一番です。
何度も解答を作っていくことで、答えの書き方のパターンが理解できるようになるため、記述問題を解くための思考回路が養われていきます。
記述問題の上達には時間がかかるので、できるだけ早い段階から取り組みましょう。
早めから対策を行っておくことで、解答に必要な要素の抜き出し方などが身につくため、そのほかの問題形式の対策にもなります。
良質な問題集や志望校の過去問などを1つ1つ解いていくことが近道です。
記述問題は添削してもらう
記述問題の勉強のしづらさには、「自己採点が難しい」という理由が挙げられます。
問題集を解いて答え合わせをする際、自分の解答と模範解答を見比べても、自分がどれだけ書けたのか、部分点がどれぐらいあるのかが判断できません。
実際、記述問題の採点の難しさは、大学入学共通テストで記述問題の採用が見送られた理由の1つにもなっています。
したがって、記述問題は書き方を知っている第三者に客観的に評価してもらわないと、なかなか力が向上しません。
問題を解いたら、学校の先生や塾の講師に添削してもらいましょう。
添削してもらった内容を復習し、次に生かして繰り返し問題を解くことが重要です。
まとめ
記述問題は苦手とする人が多いからこそ、得点源にできれば周りとの差をつけられます。
まずは教科ごとの知識をしっかりと学び、実際に記述問題を解いて演習を繰り返すことが重要です。
ただし、記述問題は自己採点が難しく、自分1人ではなかなか勉強が進まないものです。
この記事で紹介した勉強法を参考にしながら、学校や塾の先生に添削を依頼して、客観的な視点を取り入れながら記述力を高めていきましょう。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

勉強のやる気が出ない受験生はどうすべき?すぐできることから本質的な解決方法7選
2022.07.01
「受験生なのに勉強のやる気が出ない……」と、なかなか勉強に気持ちが向かず集中できないことを悩むお子さまは多いようです。保護者としても、そんなお子さまの様子が心配でつい口を出してしまうことがあ...
-
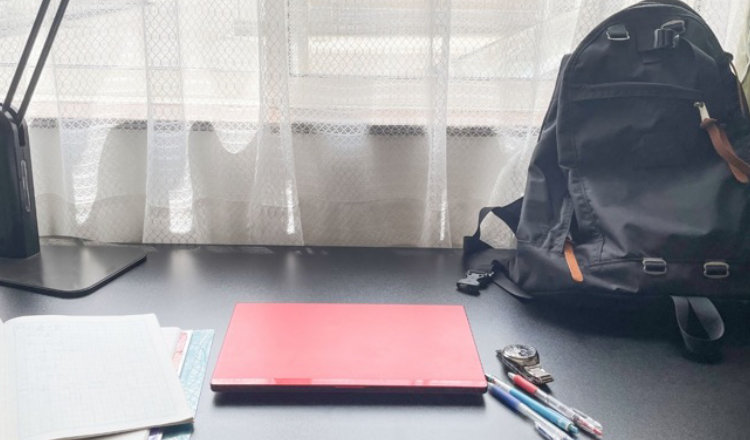
受験生の持ち物を徹底解説!必携アイテムから勉強グッズまで
2021.09.03
学校に入学するための受験の機会は、中学受験から大学受験までありますが、入試当日の持ち物に迷う受験生や保護者は多いでしょう。 受験に何を持って行くべきか把握できていないと、準備しながらも不安に...
-

すぐに緊張をほぐす方法!面接や試験で実力を発揮するためのコツを紹介
2021.08.31
「試験のとき、どうしても緊張してしまう…」 受験や面接は、慣れていないと誰でも緊張するものです。 しかし、緊張はちょっとした考え方やコツでほぐすことができます。 本番で実力を発揮するためにも...









