2022.01.10
【小学生からの英語学習のススメ】なぜ早期からの英語学習が必要なの? 小学生から「フォニックス」を学ぶメリットとは

2020年度に改訂された学習指導要領により、小学校での必修化やコミュニケーション能力の重視など、学校での英語学習に大きな変化が起きました。将来のために英語力を身につけてほしいと願う一方で、実践的な英語学習にお子さまがついていけるかどうか、不安を感じている保護者も多いでしょう。
この記事では、現在の英語学習がどのように進められているのか、小学生からの英語学習の重要性を踏まえて解説します。さらに、小学生におすすめの「フォニックス」や自宅でもできる「シャドーイング」といった学習方法に加え、保護者がお子さまのためにできることを詳しくご紹介します。
小学生から始まる実践的な英語学習
はじめに、現在お子さまが小学校で取り組んでいる英語学習の具体的な内容と中学校への準備として必要なことをご紹介します。
コミュニケーション能力の基礎を養う小学生の英語学習
現在の学習指導要領では、小学生から高校生まで、一貫した英語教育をするために必要な要素が示されています。
小学3年生から外国語活動が始まり、小学5年生からは国語や算数などと同様に、教科として外国語科の授業で英語を学びます。
3,4年生では年35単位、5,6年生では年70単位の学習時間の中で「英語によるコミュニケーション能力の基礎を養う」ことを重視した、実践的な学習を行っています。
実践的な英語力を身につけることが重視される
英語をコミュニケーションツールとして身につけるためには、インプットとアウトプットを意識した段階的な学習が必要です。特に実践的な「使える英語」を習得するにはアウトプットが非常に重要です。英語でいうアウトプットとは、英単語や英文を書く、声に出して発音するなど、インプットした英語を会話や文章で表現することです。
しかし、これまでの日本の英語学習では英単語や文法の知識習得といったインプットに重きを置いていたことから「使える英語」の習得には至らず、英語を「読める」ようになるだけで、コミュニケーションツールとしては不十分な傾向にありました。
そのため、今後ますます進むグローバル化を見据えて国際的に活躍できる人材を育てるべく、現在の英語学習ではリスニング(聞く)、スピーキング(話す)、リーディング(読む)、ライティング(書く)の英語4技能の育成が重視されています。
3・4年生の外国語活動の内容
小学校の英語学習は、リスニングとスピーキングからスタートしています。3年生から始まる外国語活動では、あいさつや身のまわりに関する簡単な質問のやりとりを行うなかで、楽しみながら英語でのコミュニケーションに親しんでいきます。
具体的には、アルファベット(大・小文字)の読み書きに始まり、色やスポーツなどの単語や100までの数を言えるようにするレベルの内容です。さらに、時間や日付を答える、自分や家族の紹介をするなど、英語での簡単な会話からコミュニケーション能力の基礎を養います。
5・6年生の外国語学習科の内容
5年生から始まる外国語科は教科なので、国語や算数などの他の教科と同様に授業では教科書が使われ、成績がつきます。
外国語科では3年生から親しんできたリスニングとスピーキングの力を伸ばすことに加え、リーディングとライティングの基礎力も身につけます。外国語活動で親しんだ簡単な対話を土台として、1つの質問についてさまざまなやりとりを通して自分の考えを伝えるといった、発展的なコミュニケーションを学びます。
具体的にはアルファベット(大・小文字)の読み書きを習得し、単語を聞いたら最初のアルファベットが分かるようにするということから、月日や曜日、天気を答えるといった内容にまで踏み込みます。さらに、自分の誕生日やほしいもの、将来の夢を伝えるなど、これまで学んだ語彙を使って自分の思いを表現しつつ、相手にも尋ねることで会話力を高めていきます。
中学校準備として必要な学習
中学校では小学校で培ったコミュニケーションを通した学びを基盤に、英単語や文法学習が加わります。 3年間で学習する語彙数は1,600~1,800語です。
中学1年生の英語の授業は、小学校で学んだことが理解できていることを前提として進められます。最初の定期テストではアルファベットからではなく、be動詞・一般動詞などの文法問題やリスニング問題が出題されます。そのため、小学生のうちにたくさんの英語に触れながらリスニング力やスピーキング力を身につけていくとともに、中学生になるための準備として、小学校で学習した内容を定着させておくことが重要です。
個別指導の明光義塾と株式会社文理のコラボ教材「毎日ちょっと365日ドリル」では、1日1ページの無理のないペースで、小学校で習う700語の学習を進めることができます。すべての単語に音声がついているため、発音しながら練習することでリスニング力やスピーキング力の向上にもつながります。
▷明光義塾×文理コラボ教材『毎日ちょっと365日ドリル 英語』のご紹介動画を見る
早期英語学習の重要性
言語は若いほど習得しやすい
言語は、幼少期に極めてスピーディーに吸収されます。そのため、ネイティブスピーカーのように流暢に英語を話せるようになるには、10歳頃までに学習を始めることが望ましいと分かっています。
「人は、発音できない音は聞き取れない」という説もあるほど、英語学習において「話す」と「聞く」は密接な関係にあります。
大人になると、英語の音をもともと知っている日本語の音に置き換えてしまいがちになり、日本語にない「f」「v」「th」の発音や「l」と「r」の区別などが難しく、発音しづらく感じてしまいます。
しかし、幼少期は柔軟性があるため、英語を聞いたときに日本語の音に置き換えることなく、聞こえたとおりに吸収します。そして、聞こえたそのままの音を真似して、正確な発音ができるようになります。
また言語の習得には、学習時間の積み重ねが重要です。日本人が日常会話レベルの英語力を身につけるには、諸説ありますが、約3,000時間の学習が必要だといわれています。
小学生から本格的に英語を学ぶことで、「使える英語」の習得に欠かせないリスニング力・スピーキング力を効率よく高められるとともに、必要な学習時間を早くから確保することができます。
英語圏の子どもたちが英語の音を身につけるメソッド「フォニックス」とは?
小学生から英語を学ぶ際に効果的な学習方法の一つとして、フォニックスが挙げられます。フォニックスとは、『英語を正しく読み、発音するためのルール』のようなものです。英語圏の子どもたちはこのフォニックスにより、文字と発音の関係を学びます。
英語にはアルファベット発音があり「a」なら「エィ」、「b」なら「ビー」と読みます。しかし、あくまでアルファベットの読み方であり、これを使って英単語を発音しようとしてもできません。その一方で、日本語は五十音を覚えればひらがなの組み合わせをほぼ読めるようになるため、英語と日本語には言語として大きな違いがあります。この違いこそが、日本人が英語を難しいと感じる理由のひとつです。
たとえば「bag」という単語は、アルファベット発音のとおりに「ビー・エィ・ジー 」とは読みません。ある程度の規則性はあるものの、英語はスペルによっても発音が変わるので「a」と書いてあっても常に「エィ」と発音するわけではないのです。フォニックスでは「a」を「ェア」、「b」を「ブ」…というように一音ずつ読み方を覚えます。これを組み合わせることで「b=ブ」「a=ェア」「g=グ」で「bag」と英単語を正しく発音できます。
こうした文字と発音の関係を学ぶことにより、初めて見た英単語でも正しく発音できるようになります。また正しく読み、書くこともできるようになります。つまり、フォニックスを学ぶことで、英語4技能の土台が身につくのです。英語圏の子どもたちと同様に小学生のうちからフォニックスを学び、英語を正しく読み、発音する力を養っていきましょう。
個別指導の明光義塾では、フォニックスのメソッドを取り入れた学習プログラム「明光みらい英語」をご用意しています。楽しく学べるため、初めて英語学習に取り組むお子さまでも安心してスタートできます。
自宅学習にもおすすめ! 英語力を向上させる練習法「シャドーイング」とは?
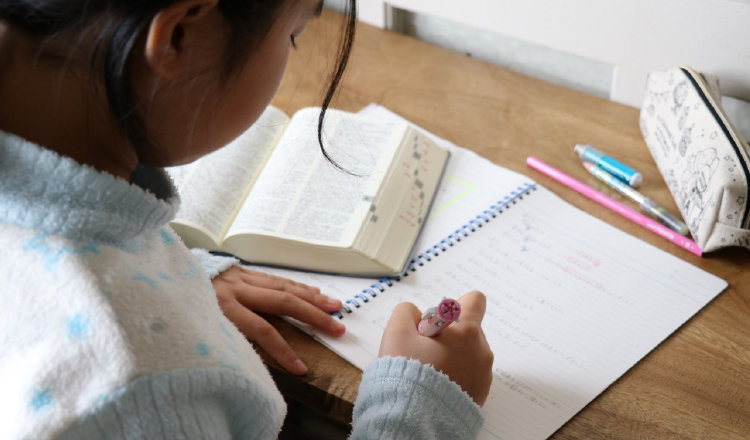
音声のついている教材があればどこでも実施可能
英語力向上に効果的な練習法として「シャドーイング」があります。シャドーイングとは、英語の音声を聞きながら、1~2語遅れて影(=shadow)のように追いかけて発音する練習です。
シャドーイングを行うことで、リスニングした英単語や英文を即座にアウトプットする力が身につきます。またシャドーイングは、スピーキング力を高めるためにも有効です。
シャドーイングで意識してほしいポイントは、2つあります。
1つ目は、聞こえてくる音をよく聞き、聞こえたとおりに真似をして発音することです。細かい発音に注意することで、英語の音を正確に掴めるようになっていきます。
2つ目は、内容をイメージすることです。英文を聞き取る際は日本語に訳そうとせず、頭の中に映像を思い浮かべるようにイメージして、英語を英語のまま理解するようにしましょう。
シャドーイングは、音声がついている教材があれば自宅でも実施することができます。いきなり長い英文をシャドーイングすることは難しいため、個別指導の明光義塾と株式会社文理のコラボ教材「毎日ちょっと365日ドリル」を使って、英単語のシャドーイングから始めてみてください。
▷明光義塾×文理コラボ教材『毎日ちょっと365日ドリル 英語』のご紹介動画を見る
小学生からの英語学習における保護者の役割
保護者がお子さまの将来のために、実施していただきたいことを2つご紹介します。
絶えず英語に触れる家庭環境作り
耳から英語に親しむことで、お子さまはぐんぐん吸収していきます。日常生活のなかで常に英語に触れられる環境を保護者が積極的に作っていきましょう。身近にあるものには自然と興味が持てるものです。
英語の歌を流す、英語番組や映画を一緒に見る、英語の絵本を置いておくなど、生活の中で取り入れることができそうなことから始めてみましょう。
お子さまと「一緒に」勉強する
遊び感覚で暮らしのなかに英語を取り入れる方法もおすすめです。お子さまは、新しく習った内容は使ってみたいと考えるものです。「どういう意味? 教えてほしいな!」と問いかけて学習したことを説明させたり、クイズを出すように英語で質問して答えさせたりといったやりとりで、より理解が深まります。
スピーキングやリスニングについては、保護者も一緒に学ぶつもりで取り組んでみてください。お子さまにとって保護者が楽しく英語を学んでいる姿は何よりも刺激になります。
お子さまができたことは積極的に褒めて、英語学習を楽しいと感じてもらうことも大切です。
まとめ
小学校からの英語学習の重要性を具体的な内容とともに解説しました。若いうちほど吸収力が高く、言語を習得しやすいため、リスニングやスピーキングを中心にできるだけ早くから英語に触れる機会を多く持つことが大切です。また早くから始めることで、必要な学習時間の確保につながります。
柔軟性のある小学生のうちから「フォニックス」を学び、英語を正しく読み、発音するための土台をつくっていきましょう。
個別指導の明光義塾では、本記事で紹介したフォニックスのメソッドを取り入れた学習プログラム「明光みらい英語」や株式会社文理とのコラボ教材「毎日ちょっと365日ドリル」の他にも、英語学習のための効果的な学習プログラムや教材をご用意しています。「本物の英語を身につけたい」、「英語で自分の思いを表現したい」など、ご要望をぜひお近くの教室にてお聞かせください。
▷明光義塾×文理コラボ教材『毎日ちょっと365日ドリル 英語』のご紹介動画を見る
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは
2025.07.03
「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
2025.06.26
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...









