2020.12.08
2021年度からの大学受験はどうなる?コロナの影響は?
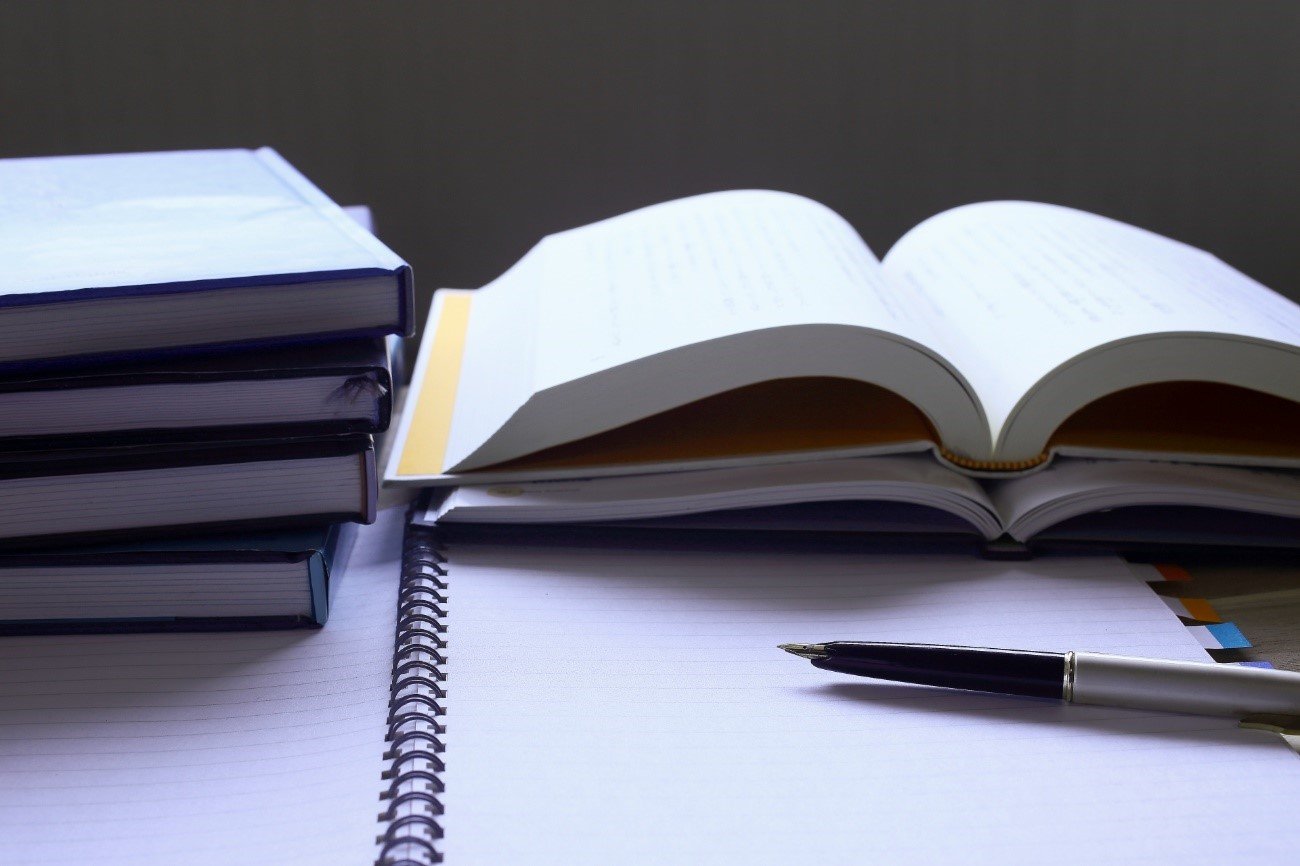
2021年度からの大学受験の新制度は、今までの制度から大きく変わります。これまでの「大学入試センター試験」は、「大学入学共通テスト」に移行し、出題傾向が大きく変更されます。また、新型コロナウイルスの影響により、大学入試の日程にも変動があるなど、2021年度の大学入試は異例づくしです。
今後の大学受験はどうなっていくのでしょうか?この記事では、2021年度以降の大学受験について解説します。
2021年度から大学受験が大きく変わる理由
2021年度の大学受験がこれまでの大学受験とは大きく変わるのは、「高大接続改革」の影響によるものです。「高大接続改革」とはいったい何なのでしょうか?
以下の項目にて詳しく解説します。
高大接続改革とは
高大接続改革とは、高校教育と大学教育、またそれらをつなぐ大学入学者選抜を、ひとつのつながりとして捉えた教育を行うことを目的とした取り組みのことで、文部科学省が推進しています。
これまでの高校教育では、優れた成績や大学入試で高得点を獲得して大学へ入学することが大切だと考えられていましたが、本来高校教育や大学教育というものは、社会で生きる力を学ぶものであり、大学受験における点数の良し悪しだけで評価されるものではありません。
こういった考えから、高校と大学の接点を増やし、高校生・大学生の学習意欲を高めるために高大接続改革の必要性が議論されるようになりました。
そのため、これまで高校と大学をつないでいた「大学入試」という存在も、大幅に見直されることとなったのです。
「学力の3要素」とは?
高大接続改革では、「学力の3要素」を育成することを目的とします。
まず1つ目が、「知識・技能の確実な習得」です。これまでの教育課程を見直し、育成すべき資質を捉えた学習指導への改善を行うというものです。
2つ目は、「思考力・判断力・表現力」の育成です。パターン化した問題を読み解く力よりも、自らが思考した上で判断し、表現する力を養うことを目的とします。
最後の3つ目が、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」です。自らの意思を持って活動する学生に対して多面的な評価を行うために、既に「高校生のための学びの基礎診断」という制度や「キャリア・パスポート」が導入されています。
いずれも、学生たちの個性を尊重した要素といえるでしょう。
高大接続改革で大学受験はどうなる?
高大接続改革の影響は、大学入試にも及びます。
まず大きく変わるのが、大学入学共通テストの導入です。これまで「大学入試センター試験(以下、センター試験)」が実施されていましたが、2021年度より「大学入学共通テスト」が始まり、内容も変わります。
また、各大学が独自の基準に基づいて実施していたAO入試・推薦入試の見直しも高大接続改革の1つとなります。
AO入試は総合型選抜、推薦入試は学校推薦型選抜と名称が変わり、学力の3要素を適切に評価し、また多面的に受験生を評価するため、大学入学共通テスト・小論文・プレゼンテーション・口頭試問・実技・各教科や科目に係るテスト・資格・検定試験の成績から1種類以上を評価方法試験として活用することが義務づけられます。
このように、従来の大学入試と審査基準が大きく異なる制度が、2021年度の入試からスタートしています。
大学入学共通テストは従来のセンター試験からどのように変わる?
2021年度からの大学入試において、注目すべきは「大学入学共通テスト」という存在です。
従来のセンター試験と大学入学共通テストの違いについて解説します。
出題傾向の変化
はじめに、センター試験と大学入学共通テストとでは、問題の出題傾向が変わります。
高大接続改革が掲げる「学力の3要素」の1つである思考力と判断力の重視に基づいた新しい問題が増えるようになります。
計画の一部は延期、2021年度実施日程は変更
大学入学共通テストでは、「国語」と「数学Ⅰ」、「数学Ⅰ・数学A」への記述式問題の導入が予定されていましたが、記述式の問題は採点に時間がかかるという懸念や、公平な採点ができるのかという不安が大学・高校の双方から寄せられた経緯もあり、実施が先送りとなりました。
しかし、大学や社会生活において必要となる問題を発見する能力や、問題解決のための構想力や解決能力をはかるため、設問文が長文化したり、出題傾向が変化したりと、出題内容の難易度はあがることが予想されます。
また、大学入学共通テストにおいては、「読む」「書く」能力に「話す」「聞く」を加えた4技能を評価するため、英検🄬やGTEC🄬などの国が認定した英語4技能試験を導入することも予定されていましたが、こちらも延期して再検討することが決まりました。
国公立大学受験に必須ではなくなりましたが、英語4技能試験を活用する大学は年々増加しています。スコアを取得していると受験に有利に働く場合が多いので、目標スコアにむけて繰り返し受験しておくことをおすすめします。
2021年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、大学入学共通テストの日程が当初の発表から大きく変更されました。
・第一日程 2021年1月16日(土)、17日(日)
・第二日程 2021年1月30日(土)、31日(日)
・特例追試験 2021年2月13日(土)、14日(日)
第二日程は、新型コロナウイルス感染症の影響で学業の遅れがある、と在籍する学校長に認められた現役生、および、第一日程の追試験として設定されています。
特例追試験は第二日程の追試験として実施され、試験内容は従来のセンター試験を踏襲したものとなると発表されています。
2021年度の大学入学共通テストでは、第一日程の出願者が531,118人、第二日程の出願者が789人であると、2020年10月15日に大学入試センター から発表されました。
今後さらに大きく変わる可能性も
上述の通り、一部延期された計画もあります。またこれからも感染症拡大の影響によって、従来の予定や内容から大きく変更になる可能性もあります。
大学受験を少しでも考えている人は、大学受験の概要に変化がないか、こまめにチェックしておくことをおすすめします。
AO入試・推薦入試はどうなる?

2021年度以降の大学受験では、これまでのAO入試・推薦入試にも違いが生じます。
AO入試や推薦入試がこれからどうなっていくのか、詳しく解説します。
AO入試から総合型選抜へ
AO入試は、2021年度以降「総合型選抜」と呼ばれるようになります。学校長の推薦は不要な場合が多く、基本的に誰もが自由に出願できるという特徴があります。(学校長の推薦が必要な大学もありますので、必ず受験要項を確認してください)
従来のAO入試では書類や面接のみで選考・合否判定をしている大学もありましたが、これからは学力をはかる試験が必須となり、出願書類の他に、小論文や口頭試問、大学入学共通テストの得点・実技・科目試験による評価など、何らかの試験が課されるようになります。
また、入試スケジュールも今までの日程から変更になりましたので注意しましょう。
今までよりも合否が判明するのが遅いので、必ず一般選抜の対策と並行して行う必要があります。
推薦入試から学校推薦型選抜へ
次に推薦入試ですが、2021年度以降は「学校推薦型選抜」という名称に変更されます。学校長の推薦が必要な入試方法で、指定校推薦と公募制推薦に分かれるのが特徴です。
総合型選抜と同じく、学校推薦型選抜にも学力をはかる試験が導入されるため、入試の基準が大きく変わります。学校推薦型選抜も入試スケジュールが変更になりました。
合格発表が12月以降と遅くなるため、学校推薦型選抜を目指す場合も、一般選抜に備えた受験勉強が必要です。
大学受験の志望状況はどうなる?
大学受験の仕組みや試験内容が大きく変わるということは、当然受験生たちの大学の志望状況にも変化をもたらします。
大学受験における志望状況の変化について解説します。
再び文低理高へ
一時期は好景気の影響で文系の人気が高まりましたが、近年の不景気から就職を見据えた大学選びも増え、文系の志願者は減少傾向にあります。一方で、専門的な理系に人気が再び集まり、工学系を中心に安定の兆しを見せています。
さらに、新型コロナウイルスの影響で就職に不安を感じる受験生も多いことから、今後は文系から理系に志望を変える受験生も増え、より一層文系人気の低迷が予想されます。
医学部は減少傾向
医学部の志願者はこの数年、減少傾向にあります。2014年度の国公立大の医学部医学科の志願者は約1万9900人いましたが、2020年度には約1万4700人と、ピーク時の3/4ほどの志願者数となっています。
さらに浪人生が少ない現状に加え、新型コロナウイルスの影響を受けた医学系の就職先に対する敬遠などにより、医学部の競争率は低下傾向にあります。
高まり続ける情報系の人気
文系や医学系の人気が低迷する一方、近年急速に人気が高まっているのが情報系の学部です。情報化社会を生き抜くためにも有効と考え、志願する人が増えていると見られます。
実際に情報系の就職先も多く、情報科学やAIなどの成長分野に秀でた学生が大学に集まるようになっているようです。
新型コロナウイルスによる大学受験への影響は?
2020年は新型コロナウイルスの感染拡大により、世界中が大きな影響を受けました。
残念ながら、大学入試も新型コロナウイルスによる影響を受け、試験の出題範囲の変更に留まらず、試験自体を中止する大学も出るなど、受験生にとって想定外の事態が発生しています。大学入学共通テストの日程にも大きな影響がありました。
新型コロナウイルスによる大学受験への影響を見てみましょう。
出題範囲の制限
新型コロナウイルスの影響により、長期休校を余儀なくされた受験生に配慮し、文部科学省は各大学に対して、高3で学ぶことが多い地理歴史、理科などの科目における出題範囲の配慮を求めました。
制限を求める内容は、学習指導要領の範囲を超える発展的な学習内容を出題しないことや、発展的内容を出題する際は補足説明を書くこと、解答する問題を選べるよう選択問題を設けること、そして大学入学共通テストの成績の活用を2科目にせず1科目にすることの4つです。
ただし、各大学に強制するものではないため、上記の出題範囲の制限を実施している大学もあれば、実施せず従来の入試内容を用いる大学もあるので、確認することが必要です。
入試や試験を取りやめる大学や学部・学科も
大学によっては、新型コロナウイルスによる影響に配慮し、入試そのものを中止する大学も存在します。
例えば難関校としても有名である横浜国立大学では、2021年度の一般選抜の個別学力検査を実施しないことを発表しています。個別学力検査を取りやめる代わりに、すべての学部で自己推薦書の提出を求め、大学入学共通テストの得点を用いて合否を判断するとのことです。
個別の大学の対応状況は必ず大学に照会を
新型コロナウイルスへの対応状況は、大学によってさまざまです。
大学や学部・学科によっては一部入試や試験の内容を変更している場合や、試験そのものを取りやめるケースがあるため、2021年度の大学入試を受ける方は、志望校がどのような対応状況にあるかすぐに確認してください。
受験予定の大学の公式サイトを確認するか、大学に直接問い合わせをするなど、確かな情報を得られるよう行動しましょう。
まとめ
2021年度からは、大学入試のシステムそのものが大幅に変化します。
特に2021年度は新型コロナウイルスの影響が重なったため、これまでの大学受験とは大きく環境が異なり、新しいシステムに合わせた受験対策が求められます。個人では対応できる範囲が限られてしまうため、これまで以上に塾や予備校の存在が重要となるでしょう。
明光では、最新の大学入試情報をもとに、受験生一人ひとりに合わせた学習プランを作成します。2021年度以降の新しい大学入試システムにも、不自由なくチャレンジできるよう、手厚くサポートいたします。新たな大学受験に対応するべく、塾への入会をご検討中の方は、ぜひ明光にご相談ください。
この記事を家族や友人に教える
関連タグ
あわせて読みたい記事
-

2026年(令和8年)の共通テストで知らないとまずい情報を紹介!
2025.07.08
2020年度まで実施されていたセンター試験に代わって、導入されるようになった試験である大学入学共通テスト(以下、共通テスト)。2026年度の共通テストからは出願がwebになるなど変更点がいくつかあり...
-

近年の大学の選び方は?調査で判明した実態も紹介!
2024.05.16
大学にはそれぞれの特色があり、選択肢となる学部や学科も近年ますます多様化しています。また、志望校を選ぶポイントも知名度、偏差値、キャンパスの雰囲気など多岐にわたり、何を重視して志望校を決めればいいの...
-

総合型選抜とは?AO入試との違いや受かる人の特徴をわかりやすく解説!
2024.03.28
総合型選抜は2021年から名称が変更され、前身のAO入試と比べ内容も変わってきました。 国公立・私立共に導入する大学・学部が年々増えてきており、文部科学省「令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜...
タグ一覧
おすすめ記事
-

近年の大学の選び方は?調査で判明した実態も紹介!
2024.05.16
大学にはそれぞれの特色があり、選択肢となる学部や学科も近年ますます多様化しています。また、志望校を選ぶポイントも知名度、偏差値、キャンパスの雰囲気など多岐にわたり、何を重視して志望校を決めればいいの...









