2021.08.26
大学受験の英語資格・検定試験優遇制度とは?重要になる英語4技能の学習方法

大学入試改革によって、大学入試の英語は大きく変化しています。中でも、多くの大学が採用する「英語資格・検定試験優遇制度」は重要な変化の1つです。
実用英語技能検定®(以下、「英検®」)の級を出願資格にしたりスコアに換算したりというように、英検®を入試に活用する大学が増えています。受験生は英検®を上手に取り入れることで、志望校の選択肢を増やし、大学受験の準備を有利に進めることができるでしょう。
そこで本記事では、大学受験における英語資格・検定試験優遇制度の中でも、特に高校生が活用しやすい英検®について取り上げます。また大学入試の英語対策のためにぜひ知っておきたい「英語4技能」や、大学入学共通テストとの関わりについても詳しく解説します。
大学入試には英検®などの資格・検定試験による優遇制度がある
まずは、英語資格・検定試験優遇制度はどのようなもので、これによって大学入試の英語にどのような変化が起きているのかを確認しておきましょう。
英検®などの資格・検定試験による優遇制度とは
英語資格・検定試験優遇制度とは、大学入試の英語において次のような優遇を受けられる制度のことをいいます。
こうした優遇制度は一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜で利用できます。
出願資格を得られる
大学によって指定された英検®の級に合格していると、その大学や学部への出願資格を得られます。
得点に換算される
大学受験の当日に英語の試験を受けなくても、英検®の取得級やスコアが得点に換算されます。
得点に加点される
大学受験の当日の英語の試験の得点に、英検®の取得級やスコアに応じた点数が加点されます。
判定で優遇される
入試の合否判定の参考として、英検®の取得級やスコアが考慮されます。
英語資格・検定試験による優遇制度に伴う変化
従来の大学受験の英語は、試験当日の得点によってのみ評価され、一発勝負の性格をもっていました。これに対し、英検®は時間をかけて準備し、よい級やスコアを獲得するため何度も挑戦することができます。英語資格・検定試験優遇制度の導入によって、大学受験の英語が一発勝負ではなくなったといえるでしょう。
英語資格・検定試験優遇制度は、英語が得意な受験生にも苦手な受験生にもメリットがあります。また、英検®対策は単に英検®の資格を得るためだけでなく、大学入学共通テストや一般選抜にも役立てられ、英語の実力を養うのに有効です。これらの点については、後ほど詳しく見ていきます。
大学入試対策に英検®を取り入れるメリット
英語資格・検定試験優遇制度が広がる中、英検®対策を行うのと行わないのとではどのような違いが出てくるのでしょうか。
大学入試対策に英検®を取り入れた場合のメリットについて見てみましょう。
志望校の選択肢が増える
英検®の級をもっていないと受験できない大学があります。特に、出願資格として英検®準2級~2級以上を求める大学は多数にのぼります。
多くの大学で指定されている英検®の級を取得していない受験生は、出願できる大学、学部、学科の選択肢が狭まってしまう可能性があります。反対に、英検®対策をしっかり行うことは、志望校の選択肢を増やすことにつながるでしょう。
英検®の活用法は大学によって異なるため、準1級をもっていれば英語の試験でかなり有利になります。自分が行きたい大学が英検®準1級を評価する試験制度であれば、英検®対策は必須です。あるいは、英検®準1級を先に取得しておいて、有利な試験制度のある大学の中から志望校を選ぶこともできるでしょう。
英検®は何度もチャレンジできる
大学の一般選抜の英語と英検®を比べると、大きな違いが1つあります。それは、一般選抜は1回しか受けられないのに対して、英検®は何度でもチャレンジできる点です。
一般選抜の場合、自分の調子の善し悪しや出題される問題との相性によって、思うように実力を発揮できないことがあります。その点において、英検®であれば初めての試験に失敗しても、2回、3回と挑戦を続けることで合格できる可能性は高くなるでしょう。一発勝負ではなく、努力が報われやすいところが英検®のよさといえます。
このように、あらかじめ英検®の準備をして早めに合格することができれば、入試シーズンに慌てなくて済むというメリットがあります。
英検®対策で学んだことを生かせる
大学受験では、2021年度入試から「大学入学共通テスト」が実施されています。このテストを受けることは国公立大学を受験する際に原則必須となっており、共通テスト利用方式を採用する私立大学の入試にも活用されています。
リーディング・ライティング・リスニング・スピーキングの「英語4技能」で評価される英検®の対策をしっかり行っていれば、大学入学共通テストの英語にも対応することが可能です。
自分のレベルに合わせた対策ができる
英語資格・検定試験優遇制度をうまく活用して受験対策をすることは、英語が得意な受験生にとっても、苦手な受験生にとっても有益です。
英語が得意な受験生であれば、早めに英検®2級をとっておいて、勉強時間をほかの教科に割り当てることができます。さらに、準1級に合格できれば、英語の試験で非常に有利な条件を得ることになります。
英語が苦手な受験生の場合でも、しっかり対策をして何度も挑戦すれば英検®2級に合格できる可能性は十分にあります。英語が苦手なのであればなおさら、一発勝負の一般選抜で高得点を狙うよりも、じっくり時間をかけて英検®に合格しておくほうが堅実な対策といえるでしょう。英語が苦手な受験生は、英検®を活用することで苦手分野をカバーすることができます。
英語資格・検定試験優遇制度を導入している注目の大学
英語資格・検定試験優遇制度を導入している大学は数多くあります。その中からいくつかの大学を紹介しながら、英語資格・検定試験優遇制度が具体的にどのようなものなのかを見ていきましょう。
英語資格・検定試験優遇制度の例
英語資格・検定試験優遇制度の内容は大学によって異なります。ここでは過去の入試情報の中からいくつか具体例を紹介します。
英検®に合格することで得られる恩恵が大きいのは、「指定された級に合格することで英語が満点扱いとなる大学」を受験する場合でしょう。例えば国際教養大学の一般選抜では、英検®準1級をもっていると共通テストの英語の試験が満点とみなされます。
一方、立教大学のように英語資格・検定試験の取得級やスコアによって一般選抜の英語が得点換算されるものの、換算表が公開されておらず、何級で何点に換算するのかを明示していない大学もあります。正確な得点は不明ですが、この場合も2級~準1級は取得しておいたほうがよいと予想されます。
また、早稲田大学の国際教養学部・国際教養学科の一般選抜では英検®の級によって加点があります。2021年度には英検®1級で20点加点、準1級で14点加点、2級で7点加点となっていました。ただし、早稲田大学では学部によって英検®の扱いは異なるため、他の学部では配点が違う場合もあることに注意が必要です。
このような換算や加点は行われない場合にも、出願資格として英検®が必要になる大学は数多くあります。
注意が必要なのは推薦入試の場合です。推薦入試は入試要項が出てから試験日までに日程の余裕がないことが多く、後から急に英検®が必要なことが分かっても準備が間に合わなくなる心配があるからです。
志望校への出願資格を獲得し、英語資格・検定試験優遇制度をうまく利用するためにも、早めに英検®対策を行うことが大切といえます。
募集要項でチェックすべき項目
大学受験における英検®の扱いは大学によって異なり、同じ大学でも学部や学科によって差があることもあります。志望校を決める際には、入試要項で必ず英検®に関する情報を確認しておきましょう。
まず、英検®が出願資格になっているのか、それとも点数の換算や加点が行われるのかをチェックします。また、評価基準は英検®の「級」なのか、「スコア」なのかも重要なポイントです。その際、求められる級やスコアについてもチェックしておきましょう。
多様化する大学入試
大学受験の多様化に伴い、英語の試験にも変更や多様化の傾向が見られます。
ここでは大学入学共通テストと英検®の出題傾向に注目してみましょう。
大学入学共通テストの傾向
2021年度入試から、従来の大学入試センター試験にかわって大学入学共通テストが実施されています。大学入学共通テストでは、どの科目においても大学入試センター試験に比べて知識の活用を重視され、思考力・判断力・表現力が問われるような設問が出題の中心となっています。
マーク式という点は従来と同じですが、知識や解法の暗記で回答できる問題は減っています。英語に関しては文法問題がなくなり、全て読解問題になりました。
また読解問題で扱う内容も、メールの本文や美術館の入場に関する文章といった、より生活に密着したものになっているのが特徴です。リスニングに関しても同様に、実用的で難しい問題になっています。
なお、大学入試センター試験は導入後の1990年以降に試験問題が長文化していった経緯があり、その2~3年後には各大学の一般選抜の試験問題でも長文化が進みました。このような過去の傾向から、大学入学共通テスト導入後には、同様に各大学の一般選抜においても複数資料読取問題や日常生活を題材にした問題などの出題傾向が強まるものと予想されます。今後、大学入学共通テストの対策を行うことは、一般選抜の対策としても役立つ可能性が高いでしょう。
英検®の傾向
英検®はリーディング・ライティング・リスニング・スピーキングの4技能の合計点によって合否が判定されます。配点の詳細は公開されておらず、採点後に統計的手法でスコアを算出するため、受験者が自分で正答数をもとにスコアを計算することはできません。ただし、4技能の満点スコアは均等となっており、4技能をバランスよく評価する内容といえます。
英検®には大学入学共通テストにはないライティングと、二次試験の面接形式でのスピーキングテストがあります。
英検®2級または準1級に合格できるリーディング・リスニングのレベルなら、大学入学共通テストに十分対応できます。そのため、英検®2級または準1級を目指して英語の勉強をしていれば、同時に大学入学共通テストの対策にもなるといえるでしょう。
英検®でも求められる英語4技能とは
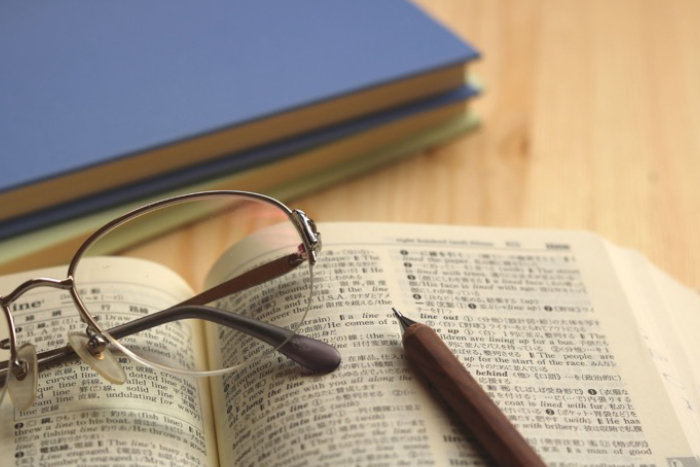
大学入試改革が進む中で、「英語4技能」の重要性が強調されてきました。この英語4技能は、英検®に合格するために必要な技能でもあります。詳しく見ていきましょう。
英語4技能とは
グローバル化が進む中、国際共通語である英語によるコミュニケーションの能力が求められています。これを可能にするのが読む(リーディング)、書く(ライティング)、聞く(リスニング)、話す(スピーキング)の4つの技能です。
高校・大学での英語教育、そして2つを結びつける大学受験の英語においても、英語4技能を軸とする改革が進められています。
この英語4技能をバランスよく評価するのは、英語4技能のうち「読む」と「聞く」を重視する内容となっていた従来の大学入試センター試験よりも、英語資格・検定試験のほうが得意分野といえるでしょう。
外部検定試験には英検®をはじめ、TEAP、GTEC、TOEFL iBT、TOEICなどがあります。
「聞く」「話す」への対策が必要
大学入試の英語では、今後ますます「聞く」「話す」が重要になると考えられます。大学入試センター試験における「読む」と「聞く」の比率は4:1でした。ところが大学入学共通テストにおいては「読む」と「聞く」の比率が1:1となっており、従来に比べて「聞く」の比重が高くなっていることが分かります。
英検®は一次試験において「読む」「書く」「聞く」が均等に評価され、二次試験のスピーキングテストで「話す」が評価されます。
このうち、「書く」に関しては以前から国公立の二次試験で出題されているため対策している人も多い分野ですが、「話す」に関しては英検®の受験を視野に入れていなければ、積極的に対策をしていない人が多いのではないでしょうか。
このように大学入学共通テストと英検®では出題内容に違いがあるものの、従来の試験に比べ「聞く」「話す」への対策がより必要になるといえるでしょう。
出願資格にもなる英検®2級のレベルとは
ここからは、数多くの大学で出願資格とされる英検®2級のレベルについて確認していきましょう。
日本英語検定協会によると、英検®2級は高校卒業程度の英語力とされ、海外留学にも対応できるようなレベルとなっています。
なお英検®準2級は2級よりもやさしく、高校中級程度とされています。2級も準2級も共に大学入試レベルとされる点は同じですが、2級では医療やテクノロジーといった社会性のある英文読解問題が出題されるのが特徴です。
大学入試に利用するためには、いつまでに英検®2級に合格すべき?
英検®を大学入試に利用する場合、いつ頃までに英検®2級に合格する計画を立てるのがよいのでしょうか。合格時期の目安と勉強を始めるタイミングについて考えてみましょう。
いつまでに英検®2級に合格すべき?
英検®は一度合格すれば生涯有効な資格です。高校2年生の夏までに合格しておくと、その後の受験対策が楽になります。
ただし、大学によっては「2年以内のスコアのみを認める」というように取得時期を限定していることがあります。一般的には高校2年生以降のスコアであれば認められることが多いといえますが、有効期間は大学によって異なるため、志望校がどのような期限を設けているか確認しておきましょう。
英検®対策を始める時期
高校2年生の夏までに英検®2級に合格することを想定し、まずは早めに準2級をとっておくとよいでしょう。
英検®は、準2級をとっていなくても2級の試験を受けることができます。ただし、いきなり2級合格を狙うよりも、まずは準2級を目標にする方が無理なく合格を目指せるでしょう。
高校中級程度の難易度とされる準2級であれば、高校1年生のうちに合格することも可能です。
多くの人が、高校入試の対策の際に英語のリスニングや英作文を学んでいます。英語学習を途切れさせないように、高校に入学した直後から英検®の勉強を始めるのが理想的です。
英語の速読力が武器になる
大学入学共通テストの英語は、従来に比べて長文化しています。そのため、すべての英文をじっくり読んでいたのでは時間内に問題を解くことができません。大学受験の英語を制するためには、英語の速読力をつけることが大切です。
一般的な英語の授業では、教科書の英文を丁寧に読んでいくことが多いでしょう。特に英文の和訳を中心とする勉強法の場合、1文ごとに英文を日本語に置き換えながら読んでいく「返り読み」の癖がつくことがあります。しかし、この方法に慣れていると、長文を読むのに膨大な時間がかかってしまいます。
明光では英文の速読に力を入れています。明光で教える速読は「斜め読み」や「飛ばし読み」とは異なり、文章の内容をしっかり理解しながら読むスピードを早くするのが目的です。
速読力を高めるためには、英文を英文の順序のとおり、そのまま理解する読み方に慣れる必要があります。例えばスラッシュリーディングは、意味のかたまりごとにスラッシュを入れながら、英文を文頭から順に理解していく方法です。スラッシュリーディングを続けることで、英文を読むスピードが早くなります。
このほかにも、知っておくと便利なコツがいくつかあります。例えば、「but」「however」「for example」といった文と文のつながりを示す言葉の後は、書き手の主張が述べられることが多い、といったテクニックです。明光では、こうした英文を読むときのポイントを学習しながら、長文を素早く正確に読む練習をします。
英文を早く読むのに慣れてくると、長文に対する苦手意識がなくなります。また、知らない単語が出てきても前後の文脈から意味を予測できるようになり、文章の理解力も高まります。試験の際は短時間で長文を読み終えることで、じっくり考えてから回答できるようになり、さらには見直しをする余裕も生まれます。
英検®対策の一環として英文の速読力を磨くことは、大学入学共通テスト対策としても有効です。
明光だからできる大学入試の英語対策
明光では英検®が大学入試に多く利用されるようになる以前から、中学生、高校生を対象とした英検®対策を行ってきました。さまざまなレベルの受験生に対する個別指導の経験が豊富なので、英検®の試験においてよい結果を出すための指導方法が確立しています。
前述のとおり、英検®は従来の大学受験の英語に比べ、リスニングとスピーキングの力が求められます。また大学入学共通テストではリスニングの比重が高くなっています。
学校でもリスニングの授業は行われていますが、平均的なレベルに合わせて授業を進める傾向があり、受験生一人ひとりに合わせた指導までは難しいのが現実ではないでしょうか。
明光では受験生一人ひとりの課題に合わせて英語対策を行うことができます。例えば英検®の二次試験で行われる面接形式のスピーキングテストでは、まずは面接に慣れることが大切です。面接対策までしっかり行えるのは個別指導のよいところです。
大学受験の英語は大きく変化しています。常に最新情報を入手して素早く変化に対応できるかどうかが、大学受験の成功を左右するといってもよいでしょう。各大学がどのような形で英検®を採用しているのかも重要な情報の1つです。
明光では最新の入試情報をもとに、志望校選びの相談から効率のよい出願方法、そして英検®をはじめ英語資格・検定試験を取り入れた、早期からの試験対策で受験生をサポートしています。
まとめ
大学受験を見据えて英検®の対策を行っておくことは、受験を有利に進めるうえで重要です。
英検®準2級~2級以上を受験資格としている大学は多いので、英検®2級に合格しておくことで志望校の選択肢を増やすことができるでしょう。
大学によっては英検®の級をスコアに換算したり、加点したりするところもあります。特に英検®準1級以上は満点扱いの評価をする大学もあり、一発勝負となる当日の試験と比べてかなり有利です。
また英検®は一般選抜と違って何度でも挑戦することができます。高校2年生の夏頃までに英検®2級に合格できれば、入試シーズンになってから慌てずに済むでしょう。
大学入学共通テストの英語は長文化が進み、リスニングの比重も高くなっています。こうした傾向を踏まえて勉強を進めることが大切です。
英検®は英語4技能をバランスよく評価する試験です。英検®合格のための勉強は、大学入学共通テストや一般選抜の英語にも役立つため、早めに英検®対策を始めることをおすすめします。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

塾なしでも大学受験に合格できる!?自力学習のポイント5つ
2021.03.03
「塾に通わないで大学受験をしたい」「大学受験をするけど、塾に行かなくても合格できるのかな?」などと思っている人はいませんか? 大学受験に向けて塾に通っている子どもは少なくないため、塾に通わな...
-

大学受験の勉強は何から始めればいい?成功させる勉強法を解説
2021.02.24
「大学生になってキャンパスライフを楽しみたい」「もっと勉強したいから大学生になりたい」と、高校生活の中でぼんやりと大学受験をイメージしている受験生もいるでしょう。しかし、いつから、何から始め...
-

2026年(令和8年)の共通テストで知らないとまずい情報を紹介!
2025.07.08
2020年度まで実施されていたセンター試験に代わって、導入されるようになった試験である大学入学共通テスト(以下、共通テスト)。2026年度の共通テストからは出願がwebになるなど変更点がいくつかあり...
タグ一覧
おすすめ記事
-

近年の大学の選び方は?調査で判明した実態も紹介!
2024.05.16
大学にはそれぞれの特色があり、選択肢となる学部や学科も近年ますます多様化しています。また、志望校を選ぶポイントも知名度、偏差値、キャンパスの雰囲気など多岐にわたり、何を重視して志望校を決めればいいの...









