2021.10.21
中学生におすすめの英語の学習法は?単元別のポイント、テスト対策を解説
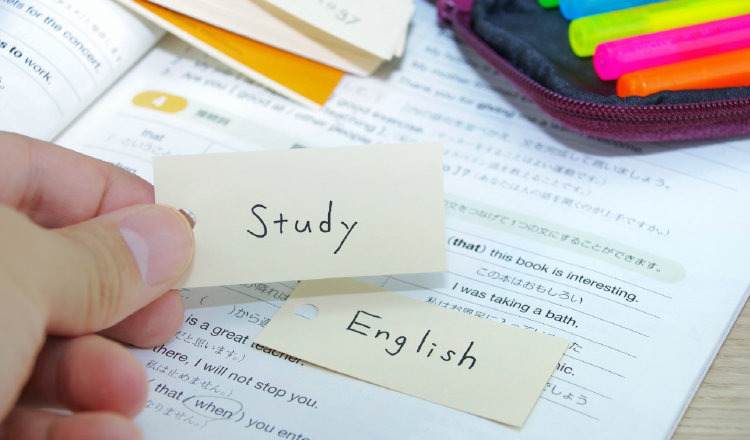
中学校で学習する英語は、学びを積み上げていくうえでの土台となる単元が多く、先々の英語学習においても重要になる要素が詰まっています。
それぞれの単元を深く理解して学び進めていくことが大切ですが、一度つまずいてしまうと苦手意識が強く根づき、英語が得意な生徒との差が開いてしまうことも、中学英語の特徴です。
本記事では、中学生が難しさを感じやすい英語の単元の学習ポイントや、中学生が受ける英語のテスト対策について詳しく取り上げます。また、グローバル社会に必要な力を育む明光こだわりの英語学習方法についても紹介します。
小学校と中学校、それぞれの英語学習の特色
「学習指導要領」の改訂により、小学校から高校までの英語学習にはこれまで以上に一貫性を持った指導が求められるようになりました。
とはいえ、学習内容にはそれぞれ特色があります。ここでは小学校と中学校の英語学習の特色を解説します。
小学校と中学校の英語学習の特色
小学校では2020年度より新しい学習指導要領が実施されています。これまでとの大きな違いは、小学3年生から「外国語活動」として英語を使ってコミュニケーション能力の素地を養う活動が行われる点です。小学5年生からは「外国語科」として教科化され、英語でのコミュニケーションの基礎を形づくります。
たとえば「Do you like Sushi?」という文章をもとに、「Sushi」の部分を児童それぞれが好きな食べ物に変えてコミュニケーションを取りつつ「Do you like~?」という表現を学んでいく、といったような練習をします。
中学校では、小学校で培ったコミュニケーションを通した学びを基盤に、単語や文法学習が加わります。
小学生から本格的な英語学習が始まったことで、保護者の中には「中学校で学んでいた内容が小学校に下りてきたのではないか」と思う方もいるかもしれませんが、上記のように小学校で行う英語学習はコミュニケーションが主であり、be動詞や一般動詞などの文法学習が追加されたということではありません。
中学1年生の英語が難しいといわれる理由は?
「中学1年生の英語が難しく感じる」といわれることがあります。その理由として、be動詞、一般動詞、現在形、過去形など「言語の土台」となる文法学習が大きく詰まっていることが挙げられます。そのため、中学1年生の単元をきちんと理解しないまま2・3年生の学びを積み上げると、つまずいてしまうケースが多くあります。
しかし反対に考えると、中学1年生の単元をきちんと理解していれば、2・3年生で新しい単元を学ぶ際にもそれほど難しさを感じることなく学習を進められるということになります。
小学校では楽しみながら英語に親しみ、さまざまなフレーズに触れ、中学1年生からは文法に紐づけて学ぶことで、英語を習得する流れにスムーズに乗ることができるでしょう。
2021年4月の教科書改訂で中学英語はどう変わった?
新学習指導要領に伴い、中学校の教科書も2021年4月より改訂されました。中学英語で大きく変わった点は2つです。
1つ目は、学習するべき単語数が改訂前の約2倍になったことです。単語数の学習の目安は、改訂前は中学校で1,200語程度でしたが、改訂後は小学校で600~700語程度、中学校で1,600~1,800語程度となっています。 小学校と中学校とを合わせた単語数を改訂前と改訂後とで比べると、およそ2倍に増えているのが分かります。
ちなみに高校に関しても、改訂前は1,800語程度だったのに対し、改訂後は1,800~2,500語程度となっています。小学校から高校までをトータルで見ても、学習するべき単語数は大幅に増加しているのです。そのため、これまでと同様の学習方法では習得が難しくなります。
2つ目に変わった点は、学習単元が全体的に前倒しになったことです。
これまで中学生の最初の英語学習はアルファベットでしたが、改訂後の今は小学生のうちに触れている前提のもとで授業が進められます。教科書でも、新しく学習する単元というよりは復習という位置づけで扱われています。
アルファベットが復習という扱いになると、今まで中学1年生の2学期に学習していた内容が1学期に前倒しされ、そして2年生、3年生の単元も同様になります。さらに高校で学習していた仮定法や原形不定詞などの一部の単元が3年生に前倒しされたため、これまでよりも速いスピードでプラスアルファの学習が必要となることが考えられるでしょう。
中学生におすすめの英語学習法
学習量が増えたことで、授業のスピードも速くなる中学英語。授業以外の時間に効率よく学びを深めることが習得のカギといえそうです。
「どうやって学習すればよい?」と悩む人のために、中学生におすすめの英語学習法を具体的に紹介します。
英語力を高めるためにどんな学習にも必要なのは「音読」
これから、英語力を高めるために必要な要素である「文法」「長文」「リスニング」「単語」の学習法を解説しますが、そのすべての基礎となる学習は「音読」です。意味を理解している英文の音読を繰り返すことで、英語力を総合的に高めることができるため、中学生にぜひ取り入れてほしい学習法です。
音読に使用する教材はどんなものでもかまいません。手元にあるテキストを使い、英文を声に出して読みましょう。ただし、単純に音読するだけでは声を出すだけの作業になってしまうため、意味を理解している英文で実践することがポイントです。
文法の学習法
文法の誤った学習法として陥りやすい例は、分からない問題を長い時間考え込んでしまうことです。しばらく考えて分からないものに時間をかけるのは非効率的なので、分からない文法が出てきたらその場で解説を読むようにします。
明光では、生徒が一人でできた問題には〇を、分からなかった問題のうち解説を読んで理解できたものには△を、講師が解説をしないと分からなかった問題には×をつける「〇△×式」を提案しています。つまずいた問題に印をつけ、復習の際に振り返るポイントを明確にすることで、効率的に学習を進められます。
長文の学習法
長文問題の攻略にはスピードが重要ですが、解答に時間を要してしまうのは「返り読み」と、長文すべてを翻訳しようとする癖の2つが原因であるケースが多いといえます。
返り読みとは、英文に最後まで目を通してから後ろから訳しつつ前に戻っていく読み方のことです。長文を最後まで翻訳しようとすることにも共通しますが、すべてを翻訳しなければ問題に取りかかれないと思ってしまうのは日本人特有といえるかもしれません。
この2つを解決するためにおすすめなのは「スラッシュリーディング」という読解方法です。スラッシュリーディングでは、たとえば「I know /a girl /who can speak English.」といったように、英文のまとまりごとにスラッシュで区切り、語順のままに訳していきます。前から訳すと「私は知っている/女の子を/英語を話せる」と自然な日本語にはなりませんが、頭の中で意味は整理できるはずです。
スラッシュリーディングの癖をつけると返り読みの必要がなくなり、すべてを翻訳せずともある程度の意味が理解できるため、長文読解のスピードが上がります。
リスニングの学習法
読み上げられる音声を受動的に聞いているだけでは、リスニング力を上げるのは難しいでしょう。リスニング学習におすすめの方法は「シャドーイング」です。シャドーイングとは英文の音声を聞き、追いかけるように発音する学習法のことで、音声と同じ発音、同じスピードで、内容をイメージしながら声に出すことがポイントです。
この場合もただ聞こえたままを発音するのは正しい学習法ではありません。短い文章からでもよいので、必ず英文の意味をきちんと理解し、頭の中で意識しながら行いましょう。
単語の学習法
単語の学習法としてよく実践されるのは「何度も書き写す」というものですが、覚えたい単語をただノートに書くだけでは記憶に定着しにくいといえます。書いて覚えるときには、音と一緒に覚えることがポイントです。たとえば「apple」という単語を書くときは、英語と日本語の意味を「apple=りんご」と頭の中でイメージしつつ、「りんご」と声に出していいます。
また分からない単語の学習の仕方としては、インターネットの画像検索機能を活用する方法もおすすめです。画像検索では単語の意味に合わせて画像が表示されるので、視覚から理解することで記憶に残りやすくなります。
学習するべき単語数が増えたこともあり、今後は単語の意味を頭の中で具体的にイメージできることがより重要になってきます。
中学生がつまずきやすい英語の単元をポイント解説
中学英語は学年が上がるにつれて徐々に難しくなりますが、3年間の学びの中でも中学生がつまずきやすい単元と克服のポイントをお伝えします。日々の学習に難しさを感じている中学生は参考にしてください。
be動詞、一般動詞
be動詞と一般動詞は、中学生が最初につまずきやすい単元です。英語は学習の積み上げに合わせて難しい単元へと学びが進んでいきます。中学1年生で学ぶbe動詞、一般動詞の時点でつまずいてしまうと、その先の文法学習も理解しにくくなってしまいます。
英語に苦手意識のある中学生は、主語と動詞の位置づけが理解できているかどうかをまず確認しましょう。be動詞、一般動詞を反復してみると、つまずきを発見できる場合が多くあります。
不定詞、受動態、完了形
中学2年生、3年生になると、英語の単元は内容が難しくなってきます。中でもとくに苦手な生徒が多いのが、不定詞、受動態、完了形です。これらは高校受験での出題率が高いため対策が必須ですが、習得すべき用法が多く、苦戦する受験生が多いことも特徴です。
不定詞、受動態、完了形の学習のポイントとして共通することは、英文の意味が瞬時に分かるようになるまで理解を深めることと、意味と時制をセットで確認することです。ただ解けるようになるだけではなく「なぜその答えになるのか」を説明できるようになれば、空所補充問題にも対応できるようになります。
また、テキストで特定の単元のページを学んでいると、該当の単元の問題ばかりが出てきて「理解したつもり」になりがちです。ただ問題をこなすのではなく、きちんと解答・解説ページを読み込み、間違えた問題には印をつけて復習しましょう。
「すぐに解答・解説ページを見るのはよくない」というイメージを持っている生徒は多いものですが、英語に関しては分からない問題を考えていても答えが出てくることはありません。しっかりと解説と日本語訳を読んで理解し、次に出題されたときに答えられるよう備えることが大切です。
中学生が受ける英語のテスト対策

中学生は3年間で英語に関するテストをいくつも受けることになりますが、その対策方法はテストの特性によってさまざまです。
ここでは、普段からコツコツ続けておきたいことと、テストが近づいてから重点的に行いたいことについて具体的に解説します。
英語の定期テスト対策
英語の定期テスト対策で普段からコツコツやっておきたいことは、単語学習、音読、シャドーイングです。これらを重点的に行い、英語技能そのものの底上げを図ります。定期テストだけではなくすべてのテストに活かせるスキルですので、家庭学習に積極的に取り入れてみてください。
また、学校指定のワークは授業進度に合わせて学習することで、定着率が向上します。テスト範囲が提示されてから取りかかるのではなく、詰め込み学習では対応できないボリュームであることを考慮し、計画的に学習を進めていきましょう。
定期テスト1週間前までには、授業やワークで間違えた問題を中心に解き、説明できるレベルにまで理解を深めておくことが大切です。このとき、学習した時点で分からなかった問題を記録に残しておく「〇△×式」の習慣が活かされます。
テスト直前には範囲表をあらためてチェックしてみましょう。「このプリント」「ワークの何ページから何ページまで」と指定されている範囲は出題率が高いです。提示された範囲を漏れなく学習しておくことで、確実に点数を取ることができます。
英検®対策
実用英語技能検定®(以下、「英検®」)は、学校の定期テストとは異なる観点から英語技能を試すことができる機会として、多くの中学生が受験しています。
英検®対策として日ごろからコツコツ続けたいことは、定期テスト対策と同様に単語学習です。1つでも多くの単語を知っていることでさまざまな問題に対応でき、合格率が上がります。
単語学習に並行して、明光が提唱する3つの学習法を継続的に進めることで、英語技能のレベルアップを図ることが可能です。
3つの学習法とは、リスニング力を高めるためのシャドーイング(英文の音声を聞き、追いかけるように発音する学習法)、ライティング力を高めるための音読筆写(意味を理解している英文を声に出して読みつつ書き写す学習法)、それからスピーキング力を高めるための「Read &Look up」です。
Read &Look upとは、英文を読んでいったん目を離し、その文を音読する学習法のこと。英検®突破に必須であるスピーキング力を伸ばすため、大変重要になる練習です。これらは長期的に継続することで力がつきますので、根気よく取り組んでいきましょう。
試験日の1ヶ月前頃からは技能を伸ばす学習と併せて、過去問を活用しながら時間配分を意識した学習を繰り返しましょう。受験する級の出題傾向の把握をきちんと行い、万全の状態で当日に備えます。
過去問は巻頭ページを読み飛ばして問題ページに入ってしまいがちですが、実は巻頭ページには級ごとの出題傾向が分かりやすくまとめられています。これはいわば定期テストの範囲表のようなものですので、必ず先にチェックしてから問題に取りかかる癖をつけましょう。
高校受験の英語対策
高校受験の英語対策として必要になる継続的な学習法は、定期テスト対策と同様です。単語学習、音読、シャドーイングに普段からコツコツ取り組むことで成果が出てきます。しかし、これまで以上の単語数を習得するためにはより多くの学習時間の確保が必要になることを念頭に置いておきましょう。
「スピーキングテストがないのに音読の学習が必要なの?」と思う人もいるかもしれません。しかし聞き取れない単語や文章は理解をするのが難しいといわれているため、音と意味とをセットで覚える必要があり、継続は必須です。
シャドーイングについても、リスニング問題が2~3割出題されることを考えれば対策として有効な学習法といえるでしょう。
さらに高校受験特有の長文問題を克服するために、普段からスラッシュリーディングの練習をしておくことが大切です。
試験前には模擬試験や受験校の過去問題など、より実践に近い形式の問題を制限時間内に解く練習を行います。出題傾向や配点、1問あたりにかけられるおおよその時間を把握しておきましょう。
それから、私立高校受験では学校の授業では対応しない単元が出題されることもあります。学校独自の問題のチェックも忘れずに行ってください。
英語が苦手な中学生に学習法をアドバイス
英語は一度つまずいてしまうと苦手意識が強くなってしまう生徒が多い教科です。苦手意識を克服する第一歩は、英語の面白さを少しでも感じられるようなきっかけ探しを行うことです。好きな洋楽の意味を知りたい、外国人の友だちとコミュニケーションを取りたいなど、興味を持ったことから英語学習への意欲が湧くケースは多いものです。
明光では過去に、英語が苦手な生徒が唯一好きなリスニングに注力して学んだところ、テスト結果に成果が表れ、それをきっかけに他の単元も自発的に学習しはじめたという事例もあります。このように生徒自らがきっかけを掴んで学びはじめたときには、身近な大人が意欲を認め、褒めて伸ばしてあげることが重要なサポートとなります。
明光が重視する英語4技能とは
明光では、英語によるコミュニケーションの能力向上を可能にする「英語4技能」を重視した学習プランを作成しています。英語4技能とは、聞く(リスニング)、読む(リーディング)、話す(スピーキング)、書く(ライティング)のことをいいます。
英語4技能を伸ばすためには、この記事で紹介している単語学習、シャドーイング、音読筆写、Read &Look upのやり方を中学生のうちに理解し、繰り返し実践することが大切です。
この学習法を定着させるポイントは家庭学習にあります。なぜなら、英語が身についたと実感できるまでにはおよそ3,000時間という膨大な時間が必要といわれているからです。しかし学校で実施されている英語の学習時間は1,000時間ほど。そのため、家庭学習でどれだけ学びを深められるかが大切です。
そのため、明光では授業内だけでなく、家庭学習の習慣をつけるサポートも行っています。
【明光のこだわり】中学生の英語を伸ばす授業と家庭学習
明光では中学生の英語力向上のため、定期テストの点数を伸ばすこと、英語技能そのものを伸ばすことの2つを大切に、生徒一人ひとりにマッチした学習カリキュラムを組んでいます。そして、その2つを伸ばしていくためには、授業だけでなく家庭での取り組みもとても大切になります。
例えば、定期テストに関しては指定された範囲の対策を行うのはもちろんのこと、授業だけでは点数が伸びにくい部分の対策強化を家庭学習で行います。具体的には、単語やリスニングの学習量を増やし、リスニングやリーディングの力をつけることで、ダイレクトに点数として反映させます。
また、英語技能の向上は、今後ますますグローバル化する社会で生きていく中学生にとって、テストのために限らず必須になることでしょう。先のとおり、英語4技能を伸ばすための学習法を身につけるには時間を要します。しかし、正しく学ぶことで効率的に身につけることができます。そのため、明光では家庭でも自ら正しく学ぶ習慣がつけられるようフォローを行っているのです。
このように、定期テストの点数を伸ばすこと、そして英語技能を伸ばすことのどちらにも重要なのは家庭学習の習慣ということが分かります。
明光では、高校受験を見据えて生徒が一人で学習する環境づくりをサポートしています。通塾時には家庭学習の進捗状況を確認し、生徒が今何をすべきか分かるようにフォローしていきます。
目標達成への道筋を一緒に考え、生徒が前向きに学びを進められる態勢をととのえることが、英語だけでなくトータルで学力向上を実現させる近道といえるかもしれません。
まとめ
学習指導要領の改訂により単語の学習量が増え、学習単元が前倒しになった中学生の英語学習。授業のスピードも速くなっているため、これまで以上の対策強化が必須です。
英語の点数がなかなか伸びない、家庭学習が習慣づかない…このようなお悩みがある方は、ぜひ明光にお問い合わせください。
高校受験を見据えつつ、明光が重視する「英語4技能」対策を中心に、本物の英語力をつけていきましょう。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは
2025.07.03
「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...
-

歴史の勉強法のコツを紹介!楽しく覚える方法も解説します!
2024.04.30
歴史の勉強について、どんな印象を持っていますか? 「覚えることが多い」「つまらない」「勉強する意味がわからない」。 歴史の勉強に苦手意識を持っている人は、このように捉えていることが多いです。...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
2025.06.26
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...









