2021.01.08
テスト勉強・受験勉強中に眠くなったときはどうすればいい?正しい対処法を教えます!

勉強中に、急な眠気に襲われたことはありませんか?
受験生の中には、「夜遅くまで勉強した日の翌日、睡眠不足で勉強になかなか集中できなかった」という経験がある人も多いでしょう。
眠くなってしまう理由は、睡眠不足以外に拒否反応やストレスなども考えられるため、根本的な原因を知ることが大切です。
この記事では、勉強中に眠くなる原因や、受験生なら知っておきたい正しい眠気対策を紹介します。
よい眠りは勉強の味方!
受験勉強を効率よく進めていくためには、適切な睡眠が不可欠です。
勉強のために睡眠時間を削っていては、集中力が低下して思うように勉強が進められず、逆効果になってしまいます。
ここでは、きちんと睡眠を取ることで得られるメリットを紹介します。
記憶は睡眠中に定着する
人間は目や耳から得た記憶を、すべて脳内の大脳皮質に蓄積します。このプロセスがスムーズであるほど、記憶は定着しやすくなります。
ここで重要になるのが、ノンレム睡眠とレム睡眠の作用です。
人間は、脳を休めるノンレム睡眠と身体を休めるレム睡眠を繰り返しながら、睡眠を行います。
ノンレム睡眠には不要な情報を消去し、必要と判断される情報を記憶として定着させる働きがあります。一方、レム睡眠では記憶を整理して、必要なときに引き出しやすいよう、記憶同士を関連付けます。
つまり、ノンレム睡眠とレム睡眠の質を高めるほど、勉強の記憶は定着しやすくなります。
脳は睡眠中に発達する
睡眠中は、脳そのものも成長します。
睡眠中は、体内で成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンには、身体だけでなく脳を発達させる働きもあります。脳が発達すれば記憶を蓄積できる能力も高まるため、より多くの情報を記憶できるようになるでしょう。
特に小中学生の脳は、成長段階にあります。今後受験勉強をするにあたって多くの物事を学ばなければならないため、脳に無理な負荷をかけるのではなく、スムーズな成長を促すことに注力すべきです。
良質な睡眠が集中力をもたらす
心身が疲労したままでは、勉強への集中力を保つことができません。集中して勉強に取り組むためにも、まずは心身をしっかり休めることが大切です。
長時間の勉強や激しい運動をしていなくても、脳は常にさまざまな思考をめぐらせているため、1日中フル稼働しているのです。休息を取らなければ、脳が働きっぱなしになるため、集中力や記憶力が低下してしまいます。
良質な睡眠によって心身と脳が回復すれば、勉強への集中力も高まるはずです。効率よく受験勉強を進めていくためにも、睡眠を味方につけることが重要といえます。
勉強中に眠くなる原因は?
眠気対策を行うにあたっては、まず勉強中に眠くなる原因を把握することが大切です。
ここからは、勉強中に眠くなる原因を紹介します。
睡眠不足
日中に眠くなる場合は、夜の睡眠時間が十分に取れていない可能性が高いです。
夜遅くまで受験勉強に取り組んでいる人はもちろん、ベッドに入ってからもスマホを触っていたり、寝る間際までゲームをしたりしている人も多いのではないでしょうか。
質のよい睡眠が十分に取れていないと、身体が自動的にそれを補おうとするため、日中に眠くなってしまうのです。勉強中に眠くなってしまう場合は、まず睡眠時間そのものを見直しましょう。
生体リズム
十分な睡眠を取っていても、日中に眠くなってしまうこともあるでしょう。
人間の身体には、生体リズムというものがあります。人間の身体は、起床8時間後と22時間後に眠気を感じる仕組みになっているため、例えば朝6時に起きて活動を始める人は、14~15時頃に眠くなりやすい傾向にあります。
これは人間に備わった生体リズムなので、理解した上でうまく付き合っていく必要があります。1日でどの時間帯に眠気の波がくるのかを把握し、自分の生体リズムに合わせて勉強スケジュールを立てるのがおすすめです。
脳への刺激不足
勉強以外でも、楽しければ眠くならないのに、退屈だと眠く感じることはありませんか?
脳は楽しんだり興奮したりすると刺激を受け、活性化します。一方、興味がわかないものや理解できないものに対してはストレスを感じやすく、脳に強い負荷がかかってしまうため、眠気を覚えるのです。
脳の成長のためには適度な負荷をかけて鍛えることも大切ですが、脳に負荷をかけるよりも、脳を適切に刺激する方法を考えるほうが効果的でしょう。
脳のエネルギー不足
脳のエネルギー源であるブドウ糖が不足すると、眠気を感じやすくなります。
勉強に没頭して食事を抜いたりせず、まずは1日3食をしっかり食べることが大切です。
3食の食事だけでなく、勉強中にもエネルギー補給をする必要があります。
ブドウ糖が多く含まれているラムネやアメは手軽に摂取できるので、勉強中に眠くなる人は活用しましょう。
ブドウ糖を効率よく補給できるゼリーやサプリメントを摂るのもおすすめです。
また、集中して呼吸が浅くなり、脳に酸素が足りなくなると、眠気のほか頭痛・めまいの症状が出る原因になるので注意しましょう。
勉強中に眠くなったときの対策
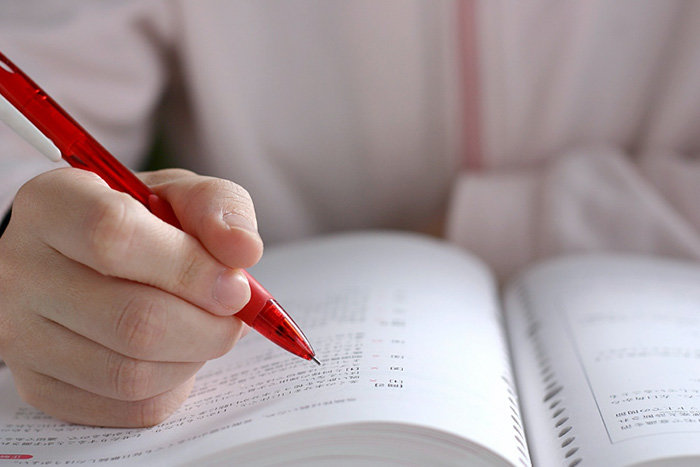
受験生にとって勉強時間は貴重なので、眠いからといって勉強を放棄することはできないでしょう。そこで、勉強中に眠くなったときのおすすめの対処法を紹介します。
軽い運動・ストレッチ
勉強の合間にストレッチなどの軽い運動を挟むと、身体がリフレッシュすると同時に脳も刺激されて、その後の勉強がはかどります。
あまり時間をかけず、気持ちよいと感じる程度に身体を動かすだけでOKです。
他にも、受験勉強の息抜きとして、軽いジョギングやウォーキングを取り入れるのもよいでしょう。
場所を変えてみる
勉強場所を変えると、簡単に脳を刺激することができます。
環境が変わると気分がリフレッシュするだけでなく、「勉強を頑張ろう」という意欲も高まり、やる気が眠気に勝つようになるのです。部屋で勉強していて眠いと感じたら、リビングやダイニングなど家の中で場所を変えるだけでも効果があります。
より集中できる環境が必要な場合は、図書館やカフェ、塾の自習室を活用しましょう。
科目や教材を切り替える
勉強への集中を切らさずに眠気対策をするなら、勉強の科目や教材を切り替えるのがおすすめです。
同じ科目ばかりを勉強していると飽きてしまい、眠気を感じてしまいます。
勉強にリズムをつけることで、勉強に対するモチベーションを維持しやすくなると同時に、脳にも新しい刺激を送ることができるため、眠気に負けることなく勉強に集中しやすい状態になります。
計算問題をやっていて眠くなったら英単語の暗記に切り替えるなど、眠くなるタイミングで勉強内容を切り替えましょう。
夜食など軽食を摂る
机に向かって勉強することは、体力とエネルギーが必要です。エネルギー不足だと脳が休もうとするため、勉強に集中しにくくなります。
勉強中に空腹を感じたら、軽食を摂って適度におなかを満たせば、眠くならずに勉強に取り組めるでしょう。
軽食は、ブドウ糖に変わりやすいラムネやバナナがおすすめです。ただし、摂りすぎは逆に眠くなるので注意しましょう。
机に突っ伏して仮眠
眠さがピークに達したときは、思い切って20~30分程度の仮眠を取りましょう。
無理に頭を働かせようとしても、眠いままでは脳の働きが鈍いため、勉強を効率よく進めることはできません。
短い仮眠を取ることで、眠気を解消できることがあります。短時間の睡眠でも自律神経が休まり、疲労も回復します。
布団に入ると長時間寝てしまう可能性があるため、机に突っ伏すように仮眠を取る「パワーナップ」がおすすめです。
パワーナップとは30分未満の短い仮眠のことで、欧米では手軽にできる疲労回復法として企業や学校などで取り入れられています。
カフェイン類には頼らない
眠たいとき、コーヒーなどのカフェインを多めに摂る受験生は多いでしょう。
しかし、カフェインなどの眠気覚ましは一時凌ぎにはなっても、長期的には悪影響をもたらす可能性があります。寝たいときになかなか寝つけなくなるなど、睡眠の質を下げる原因にもなりかねません。
カフェイン類に頼って強制的に身体を起こそうとするのではなく、自然に脳を働かせるようなアプローチを心がけましょう。
勉強中に眠くならないための抜本的な対策
勉強中に眠くなってしまうと勉強に集中できなくなってしまいます。勉強時間にはしっかりと起きて勉強するのがよいでしょう。そこで、勉強中に眠くなったときのおすすめの対処法を紹介します。
十分な睡眠時間を確保する
まずは、十分な睡眠時間を確保することが大切です。
前述のとおり、夜更かしをして勉強に取り組んでも、その内容を記憶するための睡眠時間が少ないと記憶が定着しにくいため、勉強時間が長くても効率がよいとはいえません。
睡眠時間として最低でも6~7時間は必ず確保するようにして、勉強時間を長めに取る場合も、睡眠時間を削るのではなく、「起きている時間を無駄なく使う」という発想にシフトしましょう。
夜の睡眠の質を高める
単に睡眠時間を確保するだけではなく、睡眠の質を高めることも必要です。
睡眠時間が長くても、睡眠の質が低ければ日中に眠くなってしまうでしょう。
一方、睡眠の質が高ければ、その日に勉強した情報を整理して記憶するレム睡眠、記憶した情報を関連付けるノンレム睡眠の効果も高まります。
静かに眠れる状態を作り、寝る間際にスマホを触らないようにするなど、質の高い睡眠を取れる環境を整えましょう。
朝型の生活習慣をつける
夜更かしをして勉強する習慣がついてしまうと、朝起きることができず、昼から夜中にかけて勉強せざるを得なくなるなど、生活リズムが崩れてしまうことがあります。
人間の身体には生体リズムがあり、夜中の勉強はあまり効率的とはいえません。
受験の本番も朝から昼にかけて行われることが多いため、夜型の生活をしていては不利になります。
本番に備える意味でも、朝型の生活習慣に切り替えましょう。
規則正しく充実した食事
脳を正常に機能させるためには、質が高く規則正しい食事が重要です。
食事をきちんと摂ることで、脳へのエネルギー供給が安定し、生活リズムも整いやすくなります。
エネルギー不足が起こりにくくなるため勉強中に眠くならず、高い集中力をキープしたまま勉強に取り組めるでしょう。
健康を維持することも、受験生の務めです。3食の食事できちんと栄養を摂り、受験勉強に励みましょう。
適度な運動習慣
受験生の中には、勉強に追われて運動する機会が減っている人も多いのではないでしょうか。
脳や身体をリフレッシュするためにも、適度な運動は必要です。運動することで脳が活性化し、勉強中に眠気が起こりにくくなります。
自宅でできるストレッチや柔軟体操といった簡単な運動でも構わないので、定期的に行うようにしましょう。
段階別の眠気対策
勉強中の眠気対策を覚えておくことは大切ですが、年齢によっては眠くなる原因が異なり、ときには勉強よりも睡眠を優先したほうがよいケースもあります。
高校生、中学生、小学生それぞれのシチュエーションに合わせた眠気対策を紹介します。
高校生
高校生になると自由に使える時間が増えるため、夜型の生活になりがちです。大学受験に向けて、長い学習時間を確保することを意識する人も多いですが、単に時間が長いだけでは不十分です。
「集中して勉強に取り組める時間が何時間あるか」がポイントになります。
集中力が続くなら勉強を続けてもよいのですが、集中力が切れたときや眠気がピークに達したときは、勉強を切り上げてしっかり睡眠を取るようにしましょう。
また夜型の生活が定着しないように、受験勉強期間中も規則正しい生活を送るようにしてください。
中学生
中学生は思春期にあたり、身体の仕組み上眠くなりやすい時期です。さまざまな眠気対策を講じても眠くなってしまうことがあるため、無理に自分を追い込まず、適度に仮眠を取りながら勉強に取り組むとよいでしょう。
最近はスマホを持つ中学生も多く、寝る前につい長時間触ってしまうかもしれません。スマホは適度に制限し、質のよい睡眠を取れるよう生活を見直すことも必要でしょう。
小学生
小学生の身体は、成長段階にあります。
心身を健やかに成長させるためにも、十分な睡眠は不可欠です。無理やり眠気を覚まして勉強に取り組むのではなく、睡眠時間の確保を優先したほうがよいでしょう。
小学生の時期に生活習慣が形成されるので、目先の受験だけに囚われず、総合的な成長も考慮してよい生活習慣を身につけておきましょう。
まとめ
勉強中に眠くなってしまうのは、人間の身体の仕組みによるところが大きいため、無理に矯正することはできません。
しかし、眠いからといって勉強を中断することが多ければ、その分周りの受験生に遅れを取ってしまいます。「自宅ではつい眠気に負けてしまう」という人は、学習塾で「必ず勉強に集中する時間」を設けるのがおすすめです。
明光義塾では、受験生一人ひとりに合わせたカリキュラムを用意しており、対話式で積極的に取り組める授業を行っております。十分な睡眠時間と規則正しい生活習慣を維持しながら、ぜひ明光で効率のよい受験勉強を始めてみませんか。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは
2025.07.03
「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
2025.06.26
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...









