2021.04.01
復習のタイミングはいつがベスト?俗説に惑わされない正しい方法
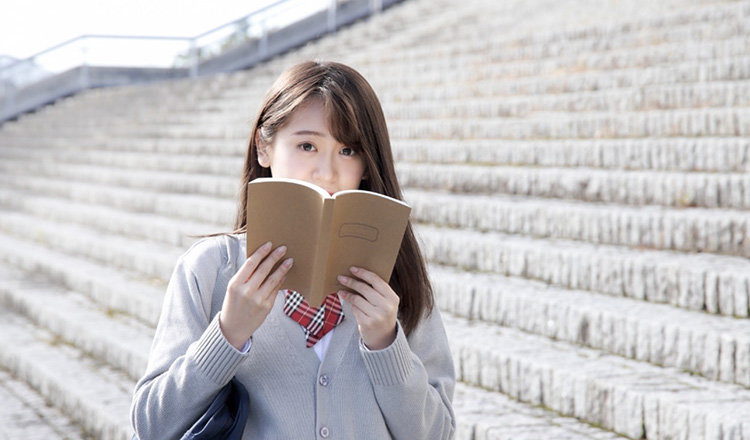
受験に向けた復習は、どのタイミングで行うのがベストなのでしょうか。
脳科学においてはエビングハウスの忘却曲線が有名ですが、実際のところそれに基づいて復習をすれば、本当に成果は上がるものなのでしょうか。
普段の授業や定期試験・模試などのタイミングと、エビングハウスの忘却曲線による復習のタイミングが必ずしも合うとは限りません。
そこでこの記事では、受験生が受ける実際の授業や試験に即した、成果の上がる復習のタイミングとその方法について解説します。
復習のタイミングを脳科学の定説にあてはめると?
復習のタイミングといえば、脳科学においてはドイツの心理学者エビングハウスによる「忘却曲線」が有名です。
ただし近年の研究では、復習の間隔を少しずつ広げていくことが、最も効果的な復習方法とは限らないことがわかってきました。
徐々に間隔を広げていく復習方法は短期学習には効果があるかもしれませんが、長期的な記憶の保持をむしろ阻害するという研究結果も出ています。
まずは、エビングハウスの忘却曲線の概要や、復習する間隔の考え方について確認していきましょう。
エビングハウスの忘却曲線
エビングハウスの忘却曲線とは、エビングハウス本人が意味を持たない3つのアルファベットの羅列を大量に暗記し、記憶と忘却が時間とともにどのように進むのかを調べ、結果をグラフに示したものです。
これによると、人は時間の経過とともに暗記したことを以下のように忘れていくといいます。
・20分後……記憶した内容の42%を忘却
・1時間後……記憶した内容の56%を忘却
・1日後……記憶した内容の74%を忘却
・1週間後……記憶した内容の77%を忘却
・1ヶ月後……記憶した内容の79%を忘却
これに基づいて、20分後、1時間後、1日後、1週間後、1ヶ月後と、徐々に間隔をあけて復習を行うのがよいとされるようになりました。最近ではそのような仕様の復習用スマホアプリも登場しています。
学術的な裏付けは得られていない
エビングハウスの忘却曲線に関する論文は、確かに存在します。
しかし、被験者はエビングハウスだけであり、暗記の対象は無意味な3つのアルファベットの羅列のみです。
その後、別の研究者も同様の研究を重ねましたが、時間の間隔を徐々にあけていく復習方法の有効性については、いまだ学術的な裏付けが得られていません。
脳に「重要な情報」と認識させる
脳は、「海馬」と呼ばれる部分で情報の仕分けをしています。そして、重要な情報だと判断されたものだけが「大脳皮質」で記憶として長期保管されます。
海馬は、「生存に必要かどうか」「今後も使うかどうか」という基準で情報を仕分けしているとされています。記憶を定着させるためには、何度も復習して覚えようとすることで、海馬に「これは重要な情報である」と認識させる必要があるのです。
間隔をあけて何度も復習することが大事
徐々に間隔をあけて復習をすることの有効性は実証されていませんが、適当な間隔をあけて何度も繰り返し復習することで記憶が定着するという人は多いものです。
どれくらい反復すると定着するかは人によって違いますので、時間をかけて根気よく復習を繰り返すことが大切です。
授業内容を復習するタイミング

普段の授業の内容を復習するにあたって、どのようなタイミングで行うのが効果的なのでしょうか。
普段の学習に取り入れたい、「復習に最適なタイミング」について解説します。
授業の直後
授業の直後は、新しいことを学んだばかりですので、まだ授業内容が頭に残っている状態です。頭に残っている間に復習すれば、思い出す時間の短縮ができ、短時間で復習をすることができます。
授業を受けた直後の休憩時間に復習するのがベストですが、次の授業の準備や教室移動もあるため、実際はなかなか難しいものです。
状況に応じて、可能な範囲で授業の直後に復習するとよいでしょう。
寝る前のひととき
人の記憶は、夜眠っている間に整理されます。寝る前の1~2時間は記憶が定着しやすい時間帯とされているため、復習する際に効率がよい時間帯といえます。
寝る前なので、論理的な思考が必要な科目(理数系)だと目が冴えてしまうかもしれませんが、地理や歴史、英単語などの暗記学習は寝る前の時間帯が最適です。
ただし、睡眠時間を削ってまで復習の時間を確保する必要はありません。
寝る前の時間帯にこだわって、夜更かしして覚えようとするのであれば、早寝して朝すっきりと目覚めてから復習に取り組むほうが効率は格段に上がります。
時間の取れる土日
「平日は忙しくてほとんど時間が取れない」という人もいるでしょう。
そのような場合は、週末のまとまった時間にじっくり復習するという方法がおすすめです。
週末のまとまった時間に復習すると、平日に習った範囲の全体の流れを確認しながら復習できるというメリットがあります。また、程よく間隔があいてから復習することになるため、「何をどのくらい忘れているか」がわかり、効率よく復習を進められます。
テストの直前
テストの直前は、復習が最も重要になる時期です。テスト前になると、すでに何度も復習をしていることになるため、記憶の定着自体が総仕上げの段階に入っている人も多いでしょう。
そのためテストの直前は、どの範囲の復習に重点的に取り組むかが大切になります。
テストの前日は、テスト範囲の中でも特に自分が苦手なところを重点的に復習し、しっかり記憶に定着させましょう。
結果的にエビングハウス曲線に沿う
授業で学習したことを、授業を終えた直後に短時間で復習し、その日の夜にサッと見直し、さらに時間の取れる土日にじっくり復習して、テスト直前には記憶の定着の総仕上げをするとよいことがわかりました。
これらの基本的な復習のタイミングを逃さずにこなした場合、自然とエビングハウスの忘却曲線に沿ったタイミングで復習ができていることになります。
試験内容を復習するタイミング
学校の定期テストや模試などが終わると解放感があるものですが、試験が終わったからといって気を抜いてしまっては、せっかく勉強した内容を忘れてしまうことにつながります。
記憶の定着のためには、試験そのものを復習ととらえることが大切です。試験内容を復習するタイミングやその方法について見ていきましょう。
定期試験の直後
定期試験の答案が返却されると、テストの点数に注目してしまいがちです。しかし、大切なのは点数や解答の正誤ではなく、「なぜ失点したのか」です。
そこで重要になるのが、定期試験後の復習です。
定期試験はそれ自体が授業の復習にもなるため、定期試験で正解できなかったところを重点的に復習すると、徐々に基礎学力が身についていきます。
まずは間違えた問題をチェックし、なぜ間違えたのか確認してください。
授業でテスト問題の解説が行われたら、間違えた問題の解説をしっかり聞き、その日のうちに理解できたかどうかを試すため、実際に同じ問題を解いてみましょう。
模試の直後
模試は受けることそのものよりも、復習することに大きなメリットがあります。
模試は定期試験よりも範囲が広いため、覚えられていないところや、理解できていないところを洗い出すことができます。
模試を受けたら、必ずその日のうちに自己採点し、1回目の復習をします。そして、次の週末にはまとまった時間を取って、模試で間違った問題を解いてみましょう。
間違えた問題は、模試専用の復習ノートを作って書き込んでいきます。
模試で出題されるのは良質な問題ばかりですので、専用ノートを作って誤答した問題を蓄積していけば、自分の苦手部分を克服するためのオリジナル問題集を作ることもできます。
模試の数週間後
模試で間違った問題は、数週間後にまた解き直し、さらに模試の直後に作ったノート(オリジナル問題集)を開いて繰り返し復習します。
このように何度も問題に取り組むことで、確実に知識が定着していくでしょう。
入試の直前
入試の直前は、総復習を行うタイミングです。新しいことを覚えるのではなく、これまでやってきたことを確実に思い出せるよう最後の復習をします。
入試の直前は、模試の後に作ったノート(オリジナル問題集)が役に立つでしょう。
自分の苦手な問題が詰まったノートで、効率よく苦手範囲を復習して入試に備えましょう。
復習はどう行うべきか
ここからは復習を行う方法と、復習するときのコツを紹介します。
効果的な復習を行うには、「反復」「アウトプット」「完全な理解」「危機感」の4つの要素がポイントになります。
短時間ずつ繰り返し行う
1回の復習に長い時間をかけたからといって、記憶に残るわけではありません。
短時間でもよいので、何度も繰り返し復習することが大切です。集中して繰り返し覚えることで、脳がそれを重要な情報だと判断し、記憶に定着していきます。
小テストなどを行って「知識を使う」かたちで定着させる
やみくもに教科書を読み、ただ覚えるというのは難しいものです。
知識をインプットしたら、それをアウトプットすることで記憶に定着しやすくなります。
インプットした知識を使うために小テストなどを行って、実際に問題を解きながらアウトプットしてみましょう。そうすることで、質の高い復習になります。
覚えたい内容は完全に理解しておく
復習する際は、完璧に理解しているかどうかが重要なポイントになります。
「なぜそうなるのか」がわかっていない公式などの暗記には限界があり、理解していないものの記憶は長期的には定着しません。
記憶違いや抜け漏れがないか確認し、使い方や理論を完全に理解した状態で覚えるようにしましょう。
「危機感」をうまく利用する
危険な目に遭ったときや、失敗したときのことほどよく覚えているという人もいるのではないでしょうか。
危機感や不快感が生じる状況は命にかかわる場合もあるため、記憶に残りやすい感情です。これらの感情をうまく利用すると、記憶は定着しやすいといえます。
テストで解けない問題に直面したときの焦燥感や、失点したときの悔しさをうまく利用しましょう。「一度間違った問題」を記憶しておくと、その問題の解き方はもちろん、類似する問題の解き方のヒントになることもあります。
まとめ
受験に向けて学力を上げていくためには、復習を繰り返すことが大切です。
人間の脳は時間の経過とともに一度覚えたことを忘れてしまうため、脳科学においては、復習は間隔をあけて繰り返し行うのがよいとされています。
実際に授業内容や試験内容を復習する際は、復習の適切なタイミングを押さえて、短時間でも集中しながら効率よく復習を進めることが大切です。
特に定期テストや模試の後は、テストが終わったからと気を抜く時間は最小限にとどめ、すぐに復習に取り組むようにしましょう。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは
2025.07.03
「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
2025.06.26
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...









