2022.05.31
GIGAスクール構想とは? ICT時代の教育は学校任せでいいの?

「GIGAスクール構想」とは、文部科学省が掲げる教育改革案の一つで、ICT教育を推進することを指します。新たな時代を生きていく子どもたちに必要な教育ということは理解できても、具体的な内容や目的がわからない人は多いでしょう。
本記事では、GIGAスクール構想とはどのようなもので、何を目的とし、何が課題になっているのかを解説します。
GIGAスクール構想とは?
まずは、概要を理解するためにもGIGAスクール構想とはどのようなものなのか詳しく解説します。
そもそもGIGAスクール構想って?
先述したように、GIGAスクール構想とは文部科学省が推進するICT教育実現に向けた構想のことです。GIGAとは「Global and Innovation Gateway for All」の略称で「すべての人にグローバルで革新的な入り口を」という意味が込められています。また、ICTとは「Information and Communication Technology」の略称であり、ICT教育は情報通信技術を活用した教育方針のことです。
GIGAスクール構想は、日本のICT教育の遅れを取り戻し、社会情勢の変化に対応するための取り組みの1つとして打ち出されました。生徒1人につき1台の端末の支給や、クラウド活用を踏まえたネットワーク環境の整備を行い、個別最適化された教育環境の実現を目指すものです。
GIGAスクール構想はいつから開始される?
文部科学省は新学習指導要領の実施を見据え、2018年度にICT教育に向けた目標水準を定めた「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画」を策定しています。そこから2019年12月に「GIGA スクール構想」として方針が打ち出されました。
2019年当初は、2022年度までにインフラ整備を終わらせて2023年度からGIGAスクール構想をスタートする見込みでしたが、コロナ禍による一斉休校が繰り返されていることから、教育に支障が生じる事態に備えて前倒しが進んでいます。
GIGAスクール構想の実現に向けた取り組み
GIGAスクール構想を実現するためには環境を整えることが必要です。ここでは、GIGAスクール構想の実現に向けた具体的な取り組みについて解説します。
1人1台の端末提供
GIGAスクール構想実現に必要不可欠なのが、情報端末を使用できる環境を整えることです。生徒1人に1台ずつ学習用端末(主にタブレット)を提供します。端末の基本スペックは定められているものの、具体的な選定は自治体が行うことになっています。
GIGAスクール構想の目的である「子ども一人ひとりに合わせた教育」や「教員と生徒、子ども同士など双方向のコミュニケーション」を実現するためには、1人1台の端末確保は必須といえるでしょう。
さらに、端末を活用するためのネットワーク環境の整備についても並行して確保する必要があります。動画を教材に使った授業や、複数の生徒によるネットワークへの一斉接続には、安定したネットワーク環境の完備が欠かせません。特定の場所だけでなく、どの教室にいてもインターネット回線が安定してつながる環境を整備することが重要です。
授業でのICT活用
GIGAスクール構想の実現に向けて、上記で説明したような端末の導入のほかにも、2020年度からはプログラミングなどのICT教育もスタートし、2024年度からはデジタル教材が導入されます。
さらに学習指導や校務へもICTが導入されるため、子どもへの指導体制が変化するでしょう。
課外・校外での学び
ICT教育は学校の授業だけで身につくものではなく、学校外や家庭での自主学習が必要とされています。
GIGAスクール構想は、端末を活用して生徒一人ひとりが最適な学びを得られることが前提となっています。そのため学習用端末を自宅に持ち帰り、学びの機会を増やすことが求められるでしょう。
今後、学習用端末は、ICT教育以外の学習ツールとしても重要なものになります。そのため、学びの機会を最大化させることや、それを支える態勢作りが急務といえるでしょう。
GIGAスクール構想が抱える課題について

GIGAスクール構想の実現にあたり、課題についても知っておく必要があるでしょう。大きく4つに分けて解説します。
教員側の対応の遅れ
課題の一つとして挙げられるのが、指導する教員側の対応の遅れです。ICTに関して知識が足りない教員であっても情報教育を行う必要があるため、GIGAスクール構想を実現するためには教員にICTについて教えることから始めなければなりません。
しかし、教員は生活指導など生徒と向き合う時間が必要であることから仕事量の多さが問題となっており、研修に多くの時間を割くことが難しく、なかなかICT教育まで手が回らないというのが現状です。また、GIGAスクール構想の対応に時間を取られてしまうことで、2020年度から必修化されたプログラミング教育が計画通りに進んでいないといった課題もあります。
学習用端末の利用に制限がある
自治体により学習用端末の利用に制限があることも、GIGAスクール構想の実現が進んでいない要因の一つです。
本来は校外での活用を推奨し、創造的な学びを目指すために端末が導入されましたが、実際にはタブレットを教室に置いて帰るルールがあることや、利用できるアプリに制限があるなど自由度が低い状況です。使用制限やルールが多いほどタブレットを活用した学習の機会は制限されてしまいます。
今後、学習用端末を活用した学習を進めるなかで、どのようにルールを定めていくかが重要となるでしょう。
お子さまに学習用端末を使わせるうえでの問題
GIGAスクール構想を実現するには生徒1人1台の学習用端末の活用が必須ですが、多くの問題があり、さまざまな議論が挙がっています。
お子さまにタブレットを自由に使わせることについては、自治体によって見解が分かれます。学習系コンテンツ以外にアクセスしてもよいのか、破損・故障時の対応はどうするのかなど、解決するべき課題は山積みです。
またインターネットを安全に使うためのITリテラシーへの意識づけは、お子さまだけでなく保護者にも浸透させていく必要があります。同時にペアレンタルコントロール(子どもが使用できる範囲を保護者が決めて制限する)も活用し、セキュリティリスクに備えることが重要です。
これからの教育とGIGAスクール構想
ここまでGIGAスクール構想の実現を目指した取り組みと課題について解説しました。お子さまを取り巻く教育現場は、ICT化を重視することによりどのように変化するのでしょうか。
コロナ禍によりさらに高まった重要性
冒頭で解説した通り、GIGAスクール構想が発表されたのは2019年12月です。取り組みが進められるなかでコロナウイルスが蔓延し、ICT化の重要性は再認識されることとなりました。
感染対策のために全国的に臨時休校が相次いだことで、一部の学校でリモート授業が実施されています。GIGAスクール構想そのものについても実質的に前倒しが進められ、2020年度には補正予算が計上されました。
今後、コロナウイルスによる感染者数が拡大すれば、集団感染防止対策も兼ねて、端末を使用したリモート授業が大きな役割を果たすことになるでしょう。
VUCA時代に必要な教育とは
近年、コロナ禍や少子高齢化、国際情勢の変化など不測の事態が起こりました。そんななか、教育やビジネスの場では「VUCA(ブーカ)」という新しいキーワードが意識されています。
VUCAとは、Volatility(変動性)Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(あいまい性)の頭文字をとった造語であり、「予測困難な」という意味を持ちます。未来を見通しにくくなった現代社会の状況を表す言葉として使われます。
テクノロジーの飛躍的な進歩により、多様なサービスやシステムが誕生しているVUCA時代においては、知識の詰め込みではなく、創造的に思考し、問題を解決していけるICT人材がますます求められるでしょう。
義務教育終了後、プログラミングが必修化
こうした状況のなか、GIGAスクール構想と並行してプログラミングが学校教育に組み込まれてきています。義務教育終了後は2022年度から「情報I」として必修化されており、2025年度からは受験科目にも追加されます。
小学校でもプログラミング教育が必修化され、すでに導入が始まっています。ICT化に対応できる問題解決能力や論理的思考力を伸ばしてVUCA時代を生き抜く力を養うためにも、プログラミングは今後の教育に欠かせないものになり得ます。
GIGAスクール構想をフルに生かした教育が大切
2019年から進められてきたGIGAスクール構想は、端末確保や通信環境などの整備は進んでいます。しかし、指導する教員側の対応の遅れやタブレットの利用制限などで、学校での教育はまだ進んでいないといえるでしょう。
ICTの能力は、これからの時代を生きるお子さまにとって必要なものです。構想と実際の教育現場が抱える課題のギャップを埋めるためにも、学校任せではなく、習い事としてプログラミングを学ぶのも選択肢の一つでしょう。
小学生にいくつ習い事をさせるべきなのか、お悩みのときにはこちらの記事もチェックしてください。
小学生の習い事はいくつがよい? メリット・デメリットから選び方まで
まとめ
将来を見通しにくいVUCA時代、ICTはこれからのお子さまに必要な能力です。しかし、教育現場では対応の遅れにより、ICT教育が思うように進んでいないのが現状です。さらにGIGAの対応に時間を取られていることで、プログラミング教育推進にも影響が出ているといった課題があります。
学校の取り組みだけでなく、家庭での学びや習い事を通じて、子どもたちが楽しくICTスキルを身につける環境を整えることが大切です。未来を生き抜く力を育むために、今からできることを始めていきましょう!
この記事を家族や友人に教える
関連タグ
あわせて読みたい記事
-
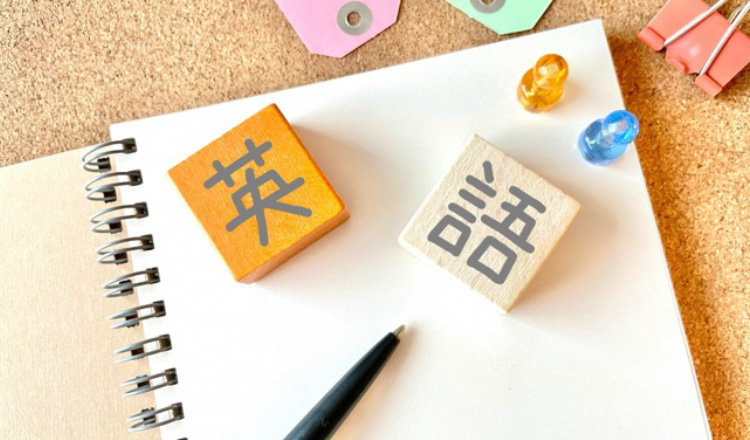
小学校で英語教育を受けるメリットとは?デメリットを克服できるベストの教え方
2022.07.13
2020年に学習指導要領が改訂され、学校教育の内容は大きく変化しました。小学校においては英語教育の義務化が大きなポイントですが、小学生が英語教育を受けることでどのような効果があるのでしょうか...
-

学校でのSDGs教育とは?受験生にSDGsって関係あるの?
2022.05.02
近年、「SDGs」や「持続可能性」という言葉を耳にする機会が増えましたが、実は教育現場にも、SDGsが取り入れられることが増えています。本記事では、SDGsが具体的に何を指しており、学校では...
-

VUCA時代とはどんな状況?VUCA時代を生き延びるための教育とは
2022.02.24
現代社会の状況を示した「VUCA時代」とは、どのような意味かご存じでしょうか。VUCAは近年、教育の新キーワードとしても注目を集めています。 お子さまの教育や将来に、VUCA時代がどう影響す...









