2022.06.15
テスト勉強してない!不安な中でも前日・当日にできることとは?
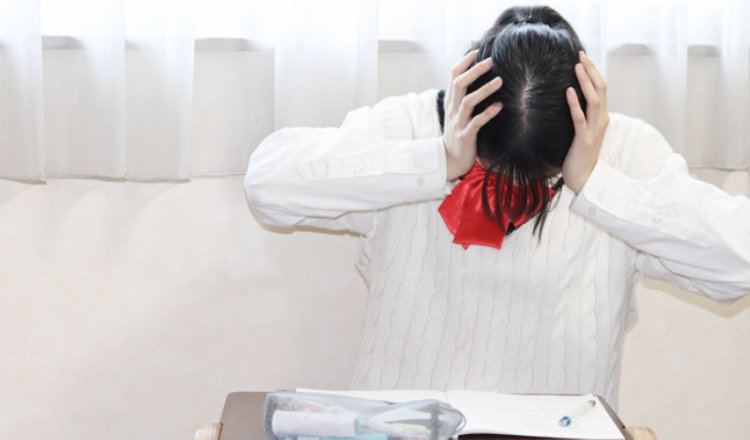
翌日に迫ったテスト。「勉強してない!」と焦り出したとき、一体どのように対策すればよいのでしょうか。
勉強は日ごろの積み重ねによって力がついてくるものです。テスト勉強もスケジュールを立てて計画的に取り組むことで知識として定着します。
この記事では「それでも明日のテストを落とすわけにいかない」という人に向けて、前日・当日にできることと本来のテスト勉強のやり方を解説します。
テスト勉強をしていないときに前日でもできること
テスト勉強が進んでいない人が前日からでもできることを紹介します。せめて少しでもよい点数を取りたい気持ちがあるなら試してみましょう。
残された時間の使い方を計画する
残された時間がわずかだからこそ、最大限に活用する必要があります。ノープランでやみくもに対策を始めるのではなく、テストまであと何時間勉強できるのか、あえて時間を取って明日までの学習計画を立てます。
これによって少しでも点数を上げられそうなところに労力を集中することが可能となります。残された時間は多いほうがよいに越したことはありませんが、睡眠時間はきちんと確保したうえで計画を立てましょう。
勉強の妨げになるものを完全排除する
一刻を争う事態のため、集中の妨げになるようなものは可能な限り遠ざけるようにします。漫画やゲームなどの誘惑は視界に入らないように片づけてください。
さらに、音楽やラジオも勉強のクオリティを下げるため、できるだけ避けるようにしましょう。特に歌詞やトークなど言葉が入るものは気が散ってしまいます。
また、スマホはテストが終わるまでは電源を切っておきます。より徹底するなら保護者に預けることで、意識から完全に排除できるためおすすめです。
ただし時間がないからと長時間休みなしで勉強を続けると疲れてしまいます。立ち上がったり、体を伸ばしたりと、短い休憩を定期的に入れたほうがはかどります。
最低限の睡眠時間は確保する
時間が足りないからといって、徹夜をするのは避けましょう。徹夜をすれば時間こそ捻出できますが、睡眠不足ではテスト本番で頭が働かなくなってしまいます。数学のように思考力が必要となる科目では特に、パフォーマンスの低下を招いてしまいます。
脳は睡眠中に新しい情報を整理し、定着させています。前日の勉強を活かすためにも睡眠時間の確保は大切です。
テスト勉強をしていない人がテストの前日にすべき勉強内容とは
ここからは、テスト勉強をしていない人が前日にするべき勉強について解説します。残された時間を有意義に使いましょう。
基礎と重要項目に的を絞る
時間が限られるため、ポイントを押さえて勉強します。出題ウェイトの大きい基礎と重要項目に絞り込んで対策するのがおすすめです。
もっとも大事なことは教科書にコンパクトに書いてあるので、教科書を見直すのが効率的です。全体に目を通しつつ、太字になっているキーワードを中心に頭に入れていきます。
定期テストの場合は先生が「テストに出る」と示してくれていることがあります。授業中やテスト範囲が出たタイミングで伝えられていることも多いため、聞き逃すことなく素直に従って対策にあたりましょう。
暗記と基本問題に徹する
深く考える問題や応用問題は、時間のないテスト直前の勉強には向きません。前日には「暗記で対応できること」と「基本ができていれば解ける問題」を徹底的にこなしていきます。社会、国語、英語など、暗記部分の多い科目に重点を置いたほうが点数を上げやすいでしょう。
とはいえ数学も理科も、公式が覚えられていなければ対応できません。直接点数につながると考え、ある程度の時間を割きましょう。
暗記ができたら基本問題を解いてみます。暗記した内容が頭に入っていれば、解ける問題も増えるはずです。また、テストで応用問題が出題されたとしても、基本問題の解き方を覚えておけば対応できるかもしれません。
アウトプットを重視する
テスト直前の勉強ではインプットよりアウトプットを重視するようにしてください。本来テスト前日は情報を仕入れるのではなく、出すことを意識した勉強が向いています。
それでもまだインプット作業が終わっていないときには、アウトプットを意識したインプットで知識を出す作業に備えましょう。頭に入れるとき、書いたり口に出したりすることで、使える知識として定着します。見て覚えるインプットのみの暗記よりも効果的です。
新しいことには手を出さない
テスト前日で新しい教材や問題集などに手を出すことはやめましょう。直前になって慌てて多くの知識を詰め込むと記憶が混乱し、情報を出すことが難しくなってしまうからです。
残された時間が限られているため、広い範囲に手をつけようとせず目の前のことに専念しましょう。暗記も記憶の呼び起こしと定着に専念し、やったことのない範囲まで覚えようとしない、ある程度の諦めも大切です。
テスト勉強をしていない人がテストの当日にできること

テスト勉強に手をつけられていなかったとしても、当日の朝はやってきます。テスト直前まで諦めることなく、できることに取り組んでいきましょう。
早起きして復習
先述のとおり徹夜せず睡眠時間を確保し、そのぶん早起きして復習の時間を作りましょう。眠い中で夜遅くまで勉強するよりも、体力が回復した朝に取り組むほうが効率的です。
また早く起きてウォーミングアップすることで、テストの時間に脳をフル回転させられます。早起きに自信のない人は保護者に起こしてもらえるよう頼んでおくのもおすすめです。
寝る前と起きてからの二度復習することで記憶がより残りやすくなるため、昨晩覚えた範囲をおさらいするのがよいでしょう。時間の許す限りアウトプットを意識しながら教科書を読み込みます。
食事はしっかり摂る
人間の体は寝ている間にもエネルギーを消費しています。エネルギーが足りないと脳が働きにくくなるため、栄養補給は必須です。時間が惜しい状況でも、食事は抜かずにエネルギーになるものをしっかり食べましょう。
できるだけいつもと同じメニューを食べるのもポイントです。多すぎたり少なすぎたりするとパフォーマンスに影響してしまいます。保護者と相談して、普段から消化がよく食べやすい朝食メニューを心がけてください。
緊張でどうしても食欲が出ないときは、栄養補助飲料を活用するのも1つの方法です。何も食べずにテストに臨むよりはよいでしょう。
休み時間を最後の復習にあてる
各科目のテスト前の休み時間が復習のラストチャンスです。記憶の定着と活性化には繰り返しが重要なので、この最後の短時間の復習は効果が高いといえます。まずはトイレに行ったり水分補給をしたりして、次の科目に頭をシフトしていきましょう。
休み時間には知識や暗記項目などのおさらいに徹し、難しいことや新しいことはしないようにします。友達と一緒に一問一答式で問題を出し合うのもよい復習方法です。
前向きな気持ちを維持する
気分が落ち込むと結果にも響くので、テスト当日には無理にでもポジティブな気分を維持しましょう。準備不足だった以上は、当然悔いが残る結果になることが想定されます。しかしまだ他の科目があるのにくよくよしていても仕方がありません。
終わった科目のことは一旦忘れ、気持ちを切り替えて次の科目に全力で臨むことが大切です。だたし全科目が終了したら、悔しさの残るうちに復習することを忘れないようにします。
テスト直前に慌てないためには
テスト前日・当日にできることはいくつもありますが、本来であれば目標に立てて計画的にテスト勉強を進めていくのが理想です。今後テスト直前に慌てないためにはどうすればよいでしょうか。
本来はいつからテスト勉強すべき?
「気がつけばテストが直前に迫っていた」ということがないように、テスト勉強のスタート時期を決めておくことがポイントです。実は、テスト勉強のベストな開始タイミングは学校が教えてくれています。それはテスト範囲の発表日です。
学齢により差はあるものの、概ね2週間前には準備ができるでしょう。目標を立て、それに必要な勉強時間を逆算して勉強を開始するタイミングを決めるようにしてください。
普段から少しずつ勉強しておくのが一番楽
テストでは知識をしっかり定着させ、引き出せるようにしておくことが求められます。そのためには継続的に勉強・復習を積み重ねるのが効果的です。
分からない箇所は疑問が出た時点で克服し、あとに残さないようにしておくとよいでしょう。テスト前に集中的に勉強するよりも、普段から勉強しておくほうが結局は楽で成果も上がります。
そう考えると、「優秀な子ほどテスト前に勉強していない」というのは必ずしも嘘ではないかもしれません。
学習習慣を身につける
普段からの学習習慣が身についていればテスト前に慌てるということ自体がなくなります。習慣化の方法は各種ありますが、自分だけで勉強を習慣化できるなら誰も苦労しないでしょう。
習慣化に苦労しているなら学習塾、特に個別指導塾にて自分で勉強できる習慣を身につけるのもおすすめです。教育のプロが目標や学習進度に合ったアドバイスをしてくれるはずです。
まとめ
テスト勉強をしていない人に向けて前日・当日にできることを紹介しました。前日になって焦ることは避けたいものの、本番直前までできることはいくつもあります。パーフェクトを目指すことは難しくても、ポイントを絞って効率よく対策していきましょう。
テストが終わったらすべての科目を復習することはもちろん、学習習慣を身につけられるよう工夫してみてください。
一人では難しい場合には、学習塾でプロにアドバイスしてもらうのが近道です。個別指導の明光では問題の解き方を教えるだけでなく、自分自身で学ぶ意欲を引き出す指導を行っています。テスト勉強がうまくいかず悩んでいる人は、お気軽にご相談ください。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは
2025.07.03
「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
2025.06.26
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...









