2021.03.02
勉強を習慣化するコツとは? 習慣を武器にする方法を紹介

勉強の習慣化は、勉強を効率的に進めるうえで大きな武器になります。特に小・中学生などの早い時期から勉強を習慣化させておくことで、次第に勉強に対して積極的になり、義務的に勉強をすることがなくなります。
しかし勉強の習慣化は、実践しようと思ってもなかなかうまくいかないことが多いのも事実です。そこで今回は、勉強の習慣化を実践する方法や、うまくいかないときのコツを解説していきます。
そもそも「習慣」とは?
まずは、習慣という概念について、意味や仕組みを見ていきましょう。普段の生活の中で当たり前のように口にする、習慣という言葉には、そもそもどのような定義があるのでしょうか。
「習慣」とは何か
習慣とは、日常生活の中で決まりのように行う動作や行為をいいます。意識しなくても毎日のように行っていることは、私たちの生活の中でさまざまあるものです。
・朝起きたときに部屋のカーテンを開ける
・ご飯を食べる前に「いただきます」という
・学校から帰宅後すぐにお風呂に入る
以上のように生活の中で決まりきった行動のことを習慣といいます。
ちなみに心理学上の定義における習慣とは、同じ行動の反復によって脳が行動パターンを習得し、少ない心的努力で繰り返すことが可能になっている、固定した行動のことをいいます。
脳にとっての「習慣」
では、脳にとって、習慣とはどのようなことをいうのでしょうか。
一般的に、脳は感情や反復によって行動をインプットするといわれています。習慣化された行動は、脳が無意識のうちに行動に移せるため、行動の時間短縮や効率化が期待できるでしょう。
勉強を習慣化するメリットとは?
では、勉強を習慣化するメリットについて見ていきましょう。勉強は習慣化させて効率的に進めていくのが一番といわれますが、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
勉強時間を確実に積み重ねられる
勉強は繰り返し積み重ねて行うことで成果が得られます。勉強が習慣化すれば、毎日少しずつでも必ず勉強に取り組めるようになり、確実に成績アップにつながるでしょう。学んだことを復習する習慣がつくため、授業で習ったことも記憶として定着しやすくなり、試験勉強をスムーズに進められます。
勉強を楽しむ感覚が自然に身につく
早い段階から勉強を習慣化しておくことで、勉強を苦痛だと感じにくくなるというメリットがあります。習慣化によって義務的・ノルマ的に勉強をする、我慢しながら勉強をするという感覚がなくなるため、自主的に勉強に取り組むサイクルが生まれます。勉強を楽しむ感覚も自然と身についていくでしょう。
自信が得られる
勉強を習慣化できれば、本人の自信につながります。継続してきたことは確かな成果を生むため、「できるようになった」「続けてきた」という達成感が自信になります。それがさらなる継続のモチベーションへとつながっていくのです。
勉強を習慣化する方法
習慣化実践の際には、正しい方法を押さえることが重要です。ただ漠然と意志を持とうとするだけでは、習慣化はなかなか実現しません。習慣化のために正しい方法を押さえて、自然と毎日机に向かう生活を作っていきましょう。
場所と時刻を固定する
脳に勉強を「これは習慣だ」と認識させるためには、脳が習得しやすい反復性を意識することが大切です。そのためには、勉強の際には明確な条件を設定し、それを繰り返すことが重要なポイントになります。
おすすめの方法は、場所と時刻を固定することです。いつ、どこで勉強をするのかをあらかじめ決めることで、習慣化しやすいパターンが作れます。
・夕食後に1時間机に向かって勉強する
・放課後に図書館で1時間勉強する
このように行動のパターンを作ると、勉強は習慣化しやすくなります。
トリガーを設定する
勉強の習慣化には、行動のきっかけ作りも重要になります。トリガー(引き金)となる行動をあらかじめ設定しておけば、自然と机に向かうスイッチも入りやすくなります。
勉強時間を1日のスケジュールの中にむやみに入れようとすると失敗しやすいため、勉強も含めた1日の行動の流れを意識しましょう。
夕食を食べる
↓
後片付けを手伝う
↓
1時間勉強をする
↓
お風呂に入る
といったように行動の流れを決めることで、「夕食の後片付けをしたら次は勉強だ」と脳が行動をインプットしやすくなり、習慣化につながります。
内容や時間は問わず「やる」ことを最優先
習慣化は、まずは続けていくことが肝心なので、最初のうちは内容にこだわりすぎないようにしておきましょう。
前述の例では勉強を1時間として解説しましたが、習慣化をスタートさせたばかりの時期なら、勉強時間は5分や10分でもよいのです。また、内容も「宿題をする」「英単語を覚える」など、実践しやすいもので十分です。
習慣化は続けていけるかどうかが肝心なので、まずは「やる」ことを最優先にしましょう。短い時間でも習慣が身につけば、あとから時間配分や取り組む内容を変えていくことは容易です。
夜の時間帯の勉強法
今度は、夜の時間帯に適した勉強法を見ていきましょう。学校から帰宅したあとの夜は、受験勉強の時間に充てる受験生も多いです。効果的な勉強法はぜひ身につけておきましょう。
質の高い睡眠を十分に取ることを優先
勉強を優先して夜更かしをすることは避けるようにしましょう。質の高い睡眠をしっかりと取ることが翌日の集中力アップにつながり、勉強がはかどります。しっかりと眠ることは知識の定着にもつながるため、覚えたことも忘れにくくなります。
夜の勉強は遅くならないうちに
夜の時間帯の勉強は、基本的に遅くならない時間のうちに済ませることが大切です。就寝前のぎりぎりまで勉強すると、思うように集中できないことも多いです。
また、寝る寸前まで勉強に集中するあまり、アドレナリンが多く分泌されて寝つきが悪くなり、結果として、毎日の勉強の効率を下げてしまいます。
21日間は続ける
行動心理学における法則の1つ「インキュベートの法則」では、行動を21日間続けることで習慣化ができるといわれています。まずは1つの目標として、21日間継続することを意識してみましょう。
ある程度の期間続けなければ行動は習慣化しないため、「1日目はこれをする、2日目はこれをする、…」といったように簡単な目標を立てながら、まずは21日間実践していきましょう。
習慣化を成功させるコツ

勉強を習慣化させるためには、習慣化しやすいコツを押さえることも大切です。前項で紹介した習慣化の方法を実践してもうまくいかず苦労したときは、以下のコツも積極的に取り入れましょう。
他の習慣と結びつける
既に習慣となっている行動をきっかけにすることで、勉強をスムーズに習慣化できる場合があります。たとえば起床後に運動する習慣があるのなら、運動後に軽く勉強する習慣を作るとよいでしょう。
特に朝の運動後は脳が活性化しやすいといわれているため、短時間でも集中でき、効率的に勉強を進めることができます。
習慣化の妨害になる要素を取り除く
習慣化の邪魔になる要素は、あらかじめ取り除くのが鉄則です。スマホやテレビ、ゲームなどは勉強の際には遠ざけるようにしましょう。スマホの通知が気になるという場合は、勉強のときは通知を切っておくのがおすすめです。
また、すぐに勉強に取り組めるように、机にはテキストや単語帳をそろえておくとよいでしょう。
人の目を利用する
「一人だとどうしても怠けてしまう」という場合には、習慣化したいことを家族や友人に宣言するのが効果的です。人の目を気にする状況になれば、ある程度の強制力が生まれ、勉強にも向き合いやすくなります。
また、一人では集中しづらくなければ、家族がいるリビングで勉強するのもおすすめです。怠けたくなっても家族の目が気になり、自然と勉強をする姿勢が保てます。
記録をつける
勉強の記録をつけてモチベーションアップにつなげるのも、習慣化の際にはおすすめです。勉強の達成状況を記録として残せば、「これだけ続けてきている」という達成感が生まれます。
また、記録することそのものが習慣の1つに加わることで、勉強はより習慣化されやすくなるでしょう。
アプリを利用する
スマホのアプリを使った習慣化の方法もあります。スケジュール管理アプリを使って勉強の意識づけをしたり、勉強の記録を残したりすれば、管理がスムーズにできるうえに習慣化することに難しさを感じにくくなります。
アプリの場合は記録の可視化もしやすく、目標がある場合には今どの程度達成できているのか、何日間続けられているのかなどもすぐに確認することができます。
やる気に頼らない
勉強を習慣化させたいときは、やる気や意志だけに頼らないことが大切です。脳が無意識のうちに行う行動として勉強をインプットさせるためには、「やる気がでたらやる」といった考え方をしていてはいけません。
やる気に頼っていると、あらゆる行動が感情の起伏に左右されてしまい、サイクルが乱れて勉強の習慣化は実現しません。
勉強と一緒に習慣化したいこと
勉強を習慣化させる際には、基本的な生活習慣を正すことや勉強に効果的な心がけを一緒に習慣化させることも重要になります。ここからは勉強と合わせて習慣化しておきたいことを見ていきましょう。
早寝早起き
勉強の習慣化に効果的な生活リズムは、早寝早起きの朝型です。朝は脳がリフレッシュした状態になるためコンディションがとてもよく、勉強に集中しやすいことで知られています。朝型の生活リズムが定着すれば、勉強も自然と日々の習慣にしやすくなります。
朝食
朝食を抜くことは、勉強を習慣化させるうえでとても非効率的です。午前中に脳を活性化させるためのエネルギー補給として、朝食は欠かせません。勉強の習慣化と合わせて、朝食を取る習慣も大切にしましょう。
運動
脳を活性化させて勉強の効率を上げるためには、ある程度の体力も必要です。そのためには運動の習慣化も忘れないようにしましょう。軽い運動は気分転換にもなるので、勉強に集中しやすい脳を作る近道になります。
読書
読書は、知識や思考力の向上に大いに役立ちます。通学時に本を読むなど、習慣化しやすい行動パターンを作っていきましょう。
焦りは禁物
これまで述べた行動習慣はいずれも勉強との相乗効果が非常に高いものですが、焦って急に全てを習慣化させようとすると、許容量を超えてしまい挫折につながります。
習慣作りに焦りは禁物です。早寝早起きができるようになったら今度は運動の習慣を作るなど、1つずつ習慣化させてゆっくり整えていくとよいでしょう。
まとめ
勉強を習慣化することができれば、意識しなくても自然と毎日勉強することができ、成績アップなどのよい結果につながります。勉強を毎日続けているという事実は本人にとって大きな自信にもなり、勉強を楽しむきっかけにもなるでしょう。
ただ、意志だけで勉強を習慣化することは意外と難しいのが現実です。まずは勉強をするという行動パターンを作ることを意識して、短時間でもよいので継続することを目指しましょう。
さらに早寝早起きや運動などのよい生活習慣をプラスすることができれば、相乗効果でより勉強に打ち込めるようになります。健康的な習慣を取り入れながら、無理なく勉強を続けられる環境づくりをしていきましょう。
この記事を家族や友人に教える
関連タグ
あわせて読みたい記事
-

勉強しない子を放っておくとどうなる?リスクや効果的な対処法を紹介
2021.12.11
保護者のお悩みとして多いのが「子どもが勉強しない」ということです。本来であればお子さまが自らすすんで机に向かってくれるのが理想的ですが、難しい場合はどのように対応すればよいのでしょうか。 本...
-

中学生は塾へ行くべきか?塾に通うことで得られる本当のメリットとは
2021.12.07
中学生のお子さまの周囲で塾に通っている子が多いと聞いたり、お子さまの成績がよくないと感じたりして、塾に通わせたほうがよいのではないかと不安になる保護者は多いものです。 実際、塾に通っている中...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...
タグ一覧
- #保護者向け
- #高校受験
- #アンケート
- #大学受験
- #勉強法
- #中学受験
- #勉強効率
- #接し方
- #集中力
- #インタビュー
- #勉強計画
- #塾
- #数学
- #勉強時間
- #教育改革
- #英語
- #日常生活
- #勉強環境
- #夏休み
- #進路選択
- #体調管理
- #定期テスト
- #習慣化
- #食べもの
- #学生生活
- #復習
- #費用
- #部活
- #面接
- #模試
- #モチベーション
- #推薦
- #教室紹介
- #習い事
- #記憶力
- #進学
- #スマホ
- #偏差値
- #受験前
- #国語
- #新学年
- #算数
- #総合型選抜
- #自由研究
- #褒め方
- #ルール
- #一般入試
- #内申点
- #叱り方
- #料理
- #理科
- #通知表
- #個別指導
- #学校生活
- #小論文
- #春休み
- #社会
- #自分らしさを仕事にする
- #計画
- #読書感想文


おすすめ記事
-
夏休みの宿題で学校から自由研究の課題が出されたけれど、「テーマが思いつかない」、「何をすればいいかわからない」と悩んでいるうちにどんどん夏休みが終わりに近づいていく・・・ そんな悩みを持つご家庭も多...
-
ほとんどの小学校で夏休みの宿題として出される自由研究。 自由研究は何をすればよいのか定まっていない分、「テーマが決まらない」、「何をしたらいいの?」と悩んでいるうちにどんどん夏休みが終わりに近づいて...
-

総合型選抜とは?AO入試との違いや受かる人の特徴をわかりやすく解説!
2024.03.28
総合型選抜は2021年から名称が変更され、前身のAO入試と比べ内容も変わってきました。 国公立・私立共に導入する大学・学部が年々増えてきており、文部科学省「令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜...
-

高校見学に必要な持ち物とは?服装やマナーについて解説
2021.07.26
自分が行きたい高校を決めるポイントの1つとして「高校見学」に参加することも挙げられますが、いざ参加するとなると何を持って行くべきかわからない人も多いでしょう。 申し込んだものの、当日になって...
-
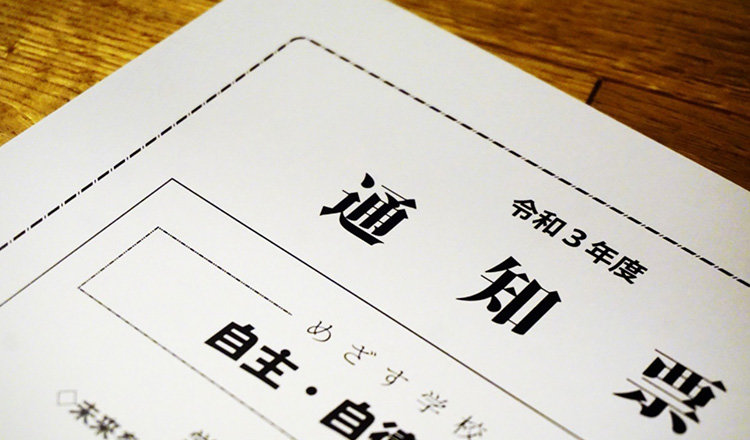
小学校の通知表の見方と活かし方とは? 評価項目を正しく読み解く!
2018.07.18
小学校の通知表は評価項目がさまざまで、どう見たらよいのか戸惑われる方も多いでしょう。通知表にはお子さまの成長を促すヒントが詰まっているため、評価だけを見て叱るのではなく、内容を正しく読み取っ...








