2025.06.26
【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
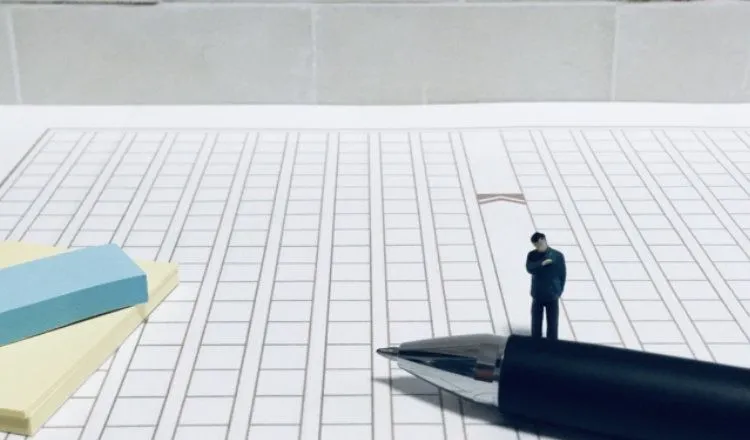
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」
というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。
小論文には書き方や構成の仕方のコツがあり、型を学び、例文を見ながら理解を深めることで、うまく書けるようになります。
本記事では、小論文がスラスラ書けるようになる「構成の型」や「話の広げ方」などを具体例付きで丁寧に解説します。
小論文を書く際に見直せるように、このページをブックマークに保存することをおすすめします。
📌この記事の活用方法
・最初から通して読むことで、小論文の基礎が身につきます
・書き方に詰まったときは「話を展開させるテクニック」セクションを参照してください
・提出前のチェックリストとして使えます
小論文とは?作文・感想文との違い
作文・感想文と小論文の違いがわからないという高校生も多いのではないでしょうか。
この違いを理解していないと、小論文を求められているのに作文・感想文を書いてしまいかねません。まずはこの違いを意識しましょう。
| 内容 | 構成 | |
|---|---|---|
| 作文・感想文 | 体験やその「主観的」な感想 | 特別決まりはない |
| 小論文 | 「客観的」な視点からの意見や主張 | 序論・本論・結論 |
作文が「主観的」に自分の思ったことや感想を述べる文章であるのに対して、小論文はデータや資料に基づいて、「客観的」な視点で相手を説得する説明文のような文章です。
小論文で難しい点は、自分の意見を含めつつ客観的に書くことを求められることです。
自分の意見を提示したら、その意見の妥当性を客観的な事実やデータなどの根拠をもとに述べる、という構成を意識しましょう。
例文から理解する作文と小論文の違い(例文)
作文と小論文の内容について、簡単な例文で違いを理解してみましょう。
作文
「私はかまぼこが大好きだ。ほどよい弾力と香ばしい風味が食欲をそそる。家では正月にしか出てこないが、できればもっと食べる機会を増やしたいと思っている。」
好きや食べる機会を増やしたいという個人の感想や意見を述べているため小論文の内容とは言えない。
小論文
「かまぼこは、健康を意識する人が積極的に摂取すべき食物の一つである。体内の免疫細胞や抗体などは、タンパク質からできている。かまぼこはタンパク質を豊富に含んでいるため、積極的に取ることで健康的に免疫力を高めることができる。」
個人の感想や意見はなく、客観的な事実を述べているため小論文の内容と言える。
知らなければ書けない小論文の構成とは?
小論文の書き方で最も重要なのは、「構成」です。
小論文はいきなり内容を書き始めるのではなく、必ず最初に構成を考える必要があります。
小論文の構成は大きく4部に分かれ
・問題提起→意見提示→論拠提示→結論
・序論→本論①→本論②→結論
のいずれかで呼ばれます。
| 問題提起(序論) | 与えられた設問に対して問題点を見つけ出し、小論文のテーマと結論を決める。 |
|---|---|
| 意見提示(本論①) | 決めたテーマに対する自分の意見を述べる。 |
| 論拠提示(本論②) | 自分の意見を掘り下げ、自分の意見の妥当性を示す体験談や客観的な事実、データを提示し、論理を展開していく。 |
| 結論 | もう一度自分の意見と結論を述べて、締めくくる。 |
文字数の割合は
■序論:2割
■本論:6割
■結論:2割
程度で割り振るとよいです。
小論文の一般的な字数制限である600~800字で書く場合、
■序論120~160字
■本論①180~240字
■本論②180~240字
■結論120~160字
が目安になります。
小論文を書く際は「構成の4つの要素」と「その文字数比」を意識しながら書くようにしましょう。
小論文の書き方を3ステップで紹介!
小論文の書き方のコツは次の3ステップに分けていくことです。
ステップ1. 出題の主旨を理解する
まずは出題の主旨、「何を聞かれているか?」をしっかりと把握します。
例えば、「雇用減少による格差拡大について論じなさい」という出題に対して「雇用減少」に触れず「格差拡大」について論じてしまうとどんなにしっかり書けていてもNGとなってしまいます。
また、「賛成・反対の立場をはっきりと示したうえで」「具体例を挙げて」などの条件がある場合、それに沿って解答しなければ減点の対象となるため注意しましょう。
ステップ2. 主張したい内容を決めて小論文の骨組みを作る
「何を聞かれているか」を理解できたら、次は「自分が主張したいこと」を決めましょう。
これは小論文の結論にあたり、構成に不可欠な要素です。
ステップ3. メモを使って整理し、構成の骨組みを作る
主張が決まったら、序論・本論・結論の構成の骨組みを作っていきます。それぞれの構成に必要となる要素を集めて整理します。
その際、「メモ」を活用するのがおすすめです。
紙に構成を書き、その周りにどんどんメモを書いて構成を膨らませます。メモを書く際は「キーワードだけ書いていく」「図や記号を使って視覚的に見やすくする」など、自分に合った方法で行いましょう。
十分メモが書けたら、構成の要素ごとに字数が収まるように文章をまとめていきます。
小論文の書き方を構成ごとに例文でチェック!

ここからは実際の問題を想定して、構成を意識した小論文の書き方を例文とともに紹介します。
「SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の利用について、あなたの考えを600字以内にまとめてください」という問題が出題されたとします。
小論文の序論の書き方|書き出しは主張につながるように
序論では、自分の主張の背景や前提を簡潔に説明し、主観を抑えて冷静に問題提起を行います。
自分の立場と反対の意見を紹介し、それを乗り越える形で主張を展開してもよいでしょう。
逆説的に構成するだけでなく、主張をストレートに膨らませて書き出す形も有効です。大切なのは結論につながる流れを意識することです。
【例文】
SNSには誹謗中傷や個人情報の流出といった危険がある。しかし、情報収集や交流の手段として現代社会に欠かせないツールであるのも事実だ。だからこそ、子どもがメリットを享受できるよう、大人が正しい使い方を教える責任があると私は考える。
小論文の本論①の書き方|意見提示は客観的な理由につながるように
本論①では、自分の立場に立った意見を述べ、その意見の内容を丁寧に広げて説明していきます。ここで大切なのは、後に続く本論②で客観的な根拠を述べやすくなるように意識することです。つまり、「なぜそう考えるのか?」をさらに深掘りする準備をここで整えます。
【例文】
SNSの最大の利点は、時間や距離を超えて人とつながれることだ。遠方の友人と連絡を取り合えたり、学校や趣味の情報交換にも役立つ。また、災害時の安否確認や行政の情報発信など、迅速な情報伝達の手段としても有効だ。使い方次第で、SNSは豊かな人間関係や社会的つながりを育む道具となる。
小論文の本論②の書き方|客観的な事実や経験を通じて主張の妥当性を述べる
本論②では、本論①で述べた意見の妥当性を、事実・体験・観察などの客観的な視点で補強します。
公的なデータが使えれば理想的ですが、なければ周囲の事例や経験談でも大丈夫です。ここでは、本論①と同じことを繰り返さず、根拠や具体例の「質」を重視しましょう。
【例文】
私の周りでも、SNSを上手に活用している友人は多い。たとえば、同じ趣味を持つ人とつながったことで、新しい挑戦を始めたり、自分に自信を持てるようになったという話をよく聞く。また、学校で孤立しがちな生徒が、SNSでは自分の気持ちを素直に表現できるというケースもある。このように、SNSは人との関係を広げたり、自分の居場所を見つける手助けになることがあるのだ。
小論文の結論の書き方|反対意見に触れつつ、自分の主張を再確認する
結論では、もう一度主張を簡潔に示し、その妥当性を認めさせるまとめ方が効果的です。このとき反対意見に軽く触れつつ、自分の立場を論理的に再提示すると、説得力のある締め方になります。
【例文】
SNSには危険性があるのは事実だが、それ以上に得られるメリットは大きい。使い方を誤らなければ、情報収集や人とのつながりを広げるための大きな助けになる。だからこそ、大人がリスクを予防する方法を教え、子どもたちが安心してSNSの利点を活かせる環境を整えるべきだと私は考える。
小論文の書き出しのコツや話を展開させるテクニック
小論文の構成を理解していても、いざ書き始めようとすると「何から書けばいいのか分からない」「文字数が足りない」と手が止まってしまうことがあります。
そんなときは、次のようなテクニックを活用してみましょう。
自分の主張の反論を入れる
反論を入れることで、書き出しを思いつきやすくなったり、広い視野をもっていることを伝えられたりします。また反論をカバーできる解決策を提示できれば、結論に説得力が増します。
そこでよく使われるのが次の2つです。
・確かに~という面もあるが、一方で、
・一般的に⚪︎⚪︎と言われているが、
疑問を投げかけて話を広げる
小論文を書いていて手が止まったときは、自分の意見に対して「なぜそう思うのか?」という疑問を投げかけていくと、話題を広げるヒントが見つかります。
例えば、
「本を読むことは大切だ」
→「なぜ大切なのか」
→「インターネットでは得られない深い知識を得られるからだ」
→「なぜ本だと深い知識を得られるのか」
というように「なぜ?」を繰り返すことで内容が掘り下げられ深めていくことができます。
この習慣を身につけると、話題を広げたり説得力のある文章を書いたりする助けになります。
大幅減点の元!小論文でやってはいけないタブー
小論文を書くうえで、やってはいけない書き方や構成がいくつかあります。
かなりの減点になる可能性があるので気をつけましょう。
文字数不足や大幅な文字数オーバー
求められる文字数に足りない、あるいは大幅にオーバーすると減点の対象になります。
以下を参考に文字数以内に収めるようにしましょう。
■必要な文字数の目安
・○○字以内:〇〇字の9割以上(例:800字以内→720字~800字)
・○○字程度:○○字の前後1割以内(例:700字前後→630~770字)
・○○字~●●字:その範囲内
小論文に慣れない間は、必要な文字数に達しないことが多々あります。
先に述べた話題を展開させるテクニックやメモをしっかりと活用しましょう。
逆に文字数がオーバーしてしまう場合は、
・簡単に表現できる箇所
・省略できる箇所(優先度が低い、繰り返し)
を修正し、指定文字数内におさめましょう。
論理に一貫性がない
小論文は、読んだ人を納得させられるかどうかが重要で、必要なのは「論理の一貫性」です。
論理の一貫性がない文章の例を見てみましょう。
【例文】
勉強の効率を上げるためには、十分な睡眠時間を確保することが重要だ。しかし、早い時間からベッドに向かえばいいというわけではない。ベッドの中でスマートフォンを使っていると脳が刺激されて睡眠に至るまで時間がかかってしまうし、睡眠の質も低下する。眠りにつく際にはスマートフォンを手が届く場所に置かない方がいいだろう。
この文では主張が「勉強の効率を上げるためには、睡眠時間を確保することが重要」だったのに、最後には「眠りにつく際はスマートフォンを手が届く場所に置かない方がいい」になってしまっています。
短い文章だと気づきやすいですが、長い文章だといつの間にか主張がすり替わってしまうことがよくあるため、小論文を書く際には自分の主張がぶれていないかを確認しましょう。
減点をされないために!小論文のルールを理解しよう
せっかく小論文が書けたとしても細かいところで減点されるのはもったいないです。
気をつける点が多いため、小論文を書く際には何度も見直して徹底できるようにしましょう。
1文字下げや段落分けのタイミングを守る
書き出しでは最初の1文字を空けます。
また意味や内容が区切れるようなタイミングで段落を分けるのが一般的で、段落が変わったら、必ず行頭を1文字下げます。1つの段落で伝えるメッセージは1つに絞ることを意識しましょう。
また、段落は2文以上でなければなりません。
促音や句読点、「」などの記号は1マス使う
「っ」や「ゃ」、「ぅ」などの促音や拗音も1文字として扱い、1マスを使って記入しなければなりません。
同様に、句読点やかっこなどもそれぞれ1文字として扱います。
ただし、句読点や閉じかっこ、閉じかぎは行頭に置くことができません。その場合は前行末のマスの文字とあわせて、2文字を1マスに書きます。
「だ・である」調に統一する
丁寧に書こうとして「です・ます」調にしないようにしましょう。
「誤字脱字」や「い抜き・ら抜き言葉」
誤字・脱字があると国語力がないと判断され、減点の対象になります。
また、「い抜き言葉」「ら抜き言葉」も厳禁です。
「い抜き言葉」は、「している」「走っている」などから「い」を抜いた言葉です。
同様に「ら抜き言葉」は、「食べられる」「見られる」などから「ら」を抜いた言葉を指します。
文学的表現を避ける
「文学的表現」とは、詩歌や小説に用いられる倒置法や体言止め、比喩表現などを指します。
小論文は説明文なので、作文のような文学的表現を使ってはいけません。
また、鍵かっこも、引用以外では使えません。会話文や格言を文中で使いたい場合は、英語で言うところの間接話法を用いる必要があります。
×直接話法:父は「お前が悪い」と言った。
〇間接話法:父は私が悪いと言った。
カタカナの使い方に気をつける
カタカナは、日本語で表現できない外来語に用いるのが基本です。適切な表現がある場合は、日本語を使いましょう。
また、もともと日本語だった言葉をカタカナで書くことも避けましょう。
例:「ショック」→「衝撃を受ける」、「ウソ」→「うそ」など
略語を使わない
省略表現や略語を使ってはいけません。公的機関や条約名などを書く際は特に注意してください。
略する場合は先に説明した上で断るようにしましょう。
例:「コンビニ」→「コンビニエンスストア」、「WHO」→「世界保健機関」など
口語体を使わない
小論文では話し言葉は使わず、書き言葉を使いましょう。
例:「~だと思う」→「~だと考える」、「だから」→「したがって」など
もちろん、「マジで」「ガチ」などの若者言葉も避けるべきです。
採点者は言葉の使い方もよく見ているので、細心の注意を払いましょう。
オノマトペを使わない
擬態語や擬音語のことをオノマトペといいます。
小論文ではオノマトペを使ってはいけないので、適切な言葉に書き換えましょう。
例:「コツコツ」→「堅実に」、「スラスラ」→「流暢に」など
近接同語や重複表現を使わない
文章内で同じ言葉を繰り返す「近接同語」を使うと、単調で無駄の多い文章になってしまいます。
また、繰り返しを避けるという意味では、「重複表現」も使ってはいけません。
「頭痛が痛い」「まず最初に」などは重複表現の代表例です。
事実と推測は区別する
客観的な事実と自分が推測したことは、区別して書く必要があります。
以下のような表現を用いると、事実と推測を区別できます。
■事実を述べるときの表現
・~である
・~という結果が出ている
・実際に~
■推測を述べるときの表現
・~と考える
・~ではないだろうか
・~と推測する
まとめ
小論文は作文とは異なり、客観的な視点で書くことが求められる「説明文」です。
書き方・構成の基本的なルールを理解することで、誰でも簡単に小論文を書けるようになりますが、上達に必須なのは「書くこと」と「添削してもらうこと」です。
一般的に2〜3ヶ月は小論文の訓練をした方がいいと言われているため、小論文を書くことと添削してもらうことを自主的に取り組むようにしましょう。
明光義塾で小論文対策!
明光義塾では小論文の個別指導を行っています。小論文の基本となるのは、読解力と表現力。一朝一夕で身につく力ではないため、早い段階から対策することが重要です。
小論文に自信がない場合、サポートが必要な場合は、お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。
明光義塾は 教室数・生徒数No.1の個別指導塾!
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-
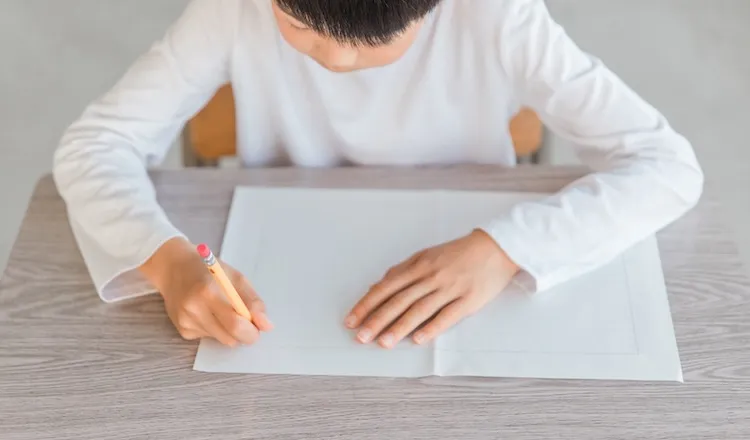
読書感想文の書き方|書き方のコツからおすすめ本まで丁寧に解説!
2025.06.30
読書感想文の課題はやり方を1から教わったことがなく、長文を書く習慣がないため苦手なお子さまが多いのではないでしょうか。 読書感想文はやり方やコツを学ぶだけでとても取り組みやすくなり、仕上がりも良くな...
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...









