2020.04.10
【高校受験】いつから始める?効率的な受験勉強法とNG行動を紹介

高校受験は多くの中学生にとって、初めての受験勉強になります。部活動や学校行事などが忙しい中で、慣れない受験勉強に頭を悩ませる人も少なくはありません。
高校受験で志望校合格を勝ち取るためには、効果的な勉強方法やしっかりとした勉強スケジュールが重要になります。
今回は、高校受験の受験勉強のポイントや、NG行動、勉強スケジュールの目安などを解説します。
もくじ
明光義塾では一人ひとりに合わせた勉強スケジュールや学習方法を提案し、あなたの志望校合格をサポートします!
受験勉強はいつから始めるべき?まず初めにやっておくべきことを紹介!!
高校受験の勉強はいつから始めるのがよいのでしょうか?一般的には、中学3年生の夏から始める場合が多いです。これは部活動をしている多くの中学生が6月から夏休み前に引退するので、それに合わせて本腰を入れて受験勉強を始めるためです。
しかし、受験勉強をいつ始めるべきかについては、その人の学力や志望校、周りの環境によって異なります。高校受験の勉強計画の立て方や、受験勉強を始める前にやっておくべきことについて、詳しく解説します。
・まずは志望校を決めよう!
受験勉強を始める前に、まずは志望校を決めることが大切です。志望校を決めることで、具体的な目標が明確になります。
志望校が決まらないまま無計画に受験勉強を始めると、何をどの程度、どのように勉強すればよいのかがわからずに時間と労力を無駄にしてしまいます。
志望する高校によって、勉強するべき範囲や難易度も異なるため、志望校を決めることは非常に重要です。
また、志望校は難易度だけでなく高校の授業内容や校風、課外活動なども踏まえて考えてみましょう。偏差値だけで決めてしまうと、「この高校、自分に合っていないかも…」と後悔してしまうかもしれません。
後悔しない高校の選び方は「後悔しない高校の選び方とは?高校選びの考え方とチェックポイント」の記事で紹介していますので、志望校をまだ決められていない方はぜひ参考にしてみてください。
・模試を受けて現在の立ち位置を知ろう!
志望校が決まったら、まずは自分の現在の立ち位置を把握することが大切です。
そのために、まずは模試を受験しましょう。模試を受験すると、自分の現在の偏差値が出ます。偏差値から、志望校合格までどれくらい距離があるのかを知ることができます。
また、各教科の成績から自分の強み、弱みを把握することができます。受験に向けて強みを強化していくのか、弱みを克服していくのか、など、勉強計画を立てる際に役立てることができます。
・勉強計画をしっかり立てよう
志望校が決まったら、その高校の入試日程を確認しましょう。
私立高校の場合は基本的に、推薦入試が1月の中旬から1月の下旬に、一般入試が2月の上旬から2月の中旬に行われます。
公立高校の場合は基本的に、推薦入試が1月の下旬から2月の中旬に、一般入試が2月の中旬から3月の中旬に行われます。
公立高校入試の最新情報はこちらよりご確認いただけますので、ぜひご活用ください。
地域別公立高校入試情報はこちら
入試日程を確認したら、そこから逆算して勉強計画を立てるようにしましょう。勉強計画をしっかりと立てることで、受験に必要な内容を明確にして効率的に勉強をすることができるようになります。
勉強計画の立て方については、「勉強計画表の作り方とコツとは?マスターすれば効率よく勉強が進められる!」の記事に詳しくまとめていますので、ぜひご参照ください。
・受験勉強は今日から始めよう!勉強計画に余裕をもたせるのがベスト
勉強計画を受験日から逆算して立てるとき、受験勉強を始めるのが早ければ早いほど余裕をもったスケジュールを組むことができます。
スケジュールに余裕がない場合、うまくスケジュール通りに勉強を進められなかったときに、取り返しがつかなくなり、受験に間に合わなくなってしまいます。
できるだけ余裕をもって勉強を進めるためには、受験勉強をなるべく早く始めるようにしましょう。
受験勉強の始める時期について、「高校受験の勉強はいつからはじめる?勉強の進め方とポイント」の記事に詳しく書いていますので、ぜひご確認ください。
周りと差をつける!高校受験の効率的な勉強法
受験勉強を始める前にするべき、重要なことについて紹介しました。ここからは、効率的な受験勉強の方法について考えてみましょう。
受験勉強にあてられる時間は人によって限界があります。そのため、高校受験勉強において重要になってくるのは、いかに効率的に勉強をするかです。
ここでは、効率的に勉強をするために押さえておきたいポイントについて紹介いたします。
・最初は毎日30分だけでも机に向かう
高校受験で重要なことは、勉強の習慣づけです。毎日の積み重ねが学力アップにつながるので、少ない時間でも勉強をする習慣を身につけましょう。極端な例ですが、1日にまとめて10時間勉強するよりも1日1時間の勉強を10日間続けた方が効果的です。
しかし、普段から勉強する習慣のない人にとっては、毎日机に向かうのは大変なことです。すぐに飽きてしまったり、机に向かってもやる気が起きなかったりするときもあるでしょう。
対策としては、最初は30分でもよいので毎日机に向かうことからスタートし、徐々に時間を延ばしていくのが有効です。
勉強習慣がうまく身につかない方は明光義塾へ
明光義塾では、単純な学力アップだけでなく、勉強を習慣化し、勉強が好きになるような指導を行っています。
「なかなか勉強のやる気が起きない」
「やっと勉強しだしたと思ったらすぐに飽きてしまっている」
「いつも三日坊主で勉強の習慣がつかない」
など、お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。
・基礎をしっかり固める
受験対策としては発展問題や応用問題に取り組みたくなるかもしれませんが、受験のうえでは基礎を固めることが大切です。理由は、以下の3つになります。
1つ目は、高校入試問題の大半は基礎問題だからです。基礎がしっかりと備わっていれば7~8割程度の問題には正解することができ、十分に合格圏内の得点を取ることができます。
2つ目は、基礎知識があいまいだとケアレスミスを起こしやすいからです。理解が十分でも起きてしまうケアレスミスを減らすには、何度も問題に取り組み、徹底的に覚える必要があります。
3つ目は、発展問題であっても土台は基礎からできているからです。難しい問題に遭遇しても、基礎さえしっかり身についていれば、基本に立ち返ることでスムーズに解答できることがあります。
以上のように、受験対策をするうえで基礎固めは非常に大切です。何度も繰り返し学習して確実に身につけましょう。
・インプットだけでなくアウトプットもする
受験勉強は知識のインプット(情報を入れること)に意識が向かいがちですが、アウトプット(情報を出すこと)も必要です。英単語や数学の公式など、どんなにがんばってインプットをしても、アウトプットを怠っていると、実際の問題でその知識を活用できない場合があります。
英単語の例でいえば、「information」という英単語を見て単語の意味を理解することはできても、実際の問題でスペルがわからなかったり、「information」という単語を使って英文が作れなかったりする場合、アウトプット不足であるといえます。
ただ暗記をするのではなく、暗記したものがどのように出題されるのか?を意識し、実際に暗記した知識を使って問題を解いてみたり、自分の言葉で話してみたりするなど、アウトプットに取り組むことは非常に大切です。
・間違えた問題を大切にする
受験勉強において、間違えた問題に対する徹底的な振り返りは最も効果的な勉強法の1つです。間違えた問題に対してしっかりと向き合い、「なぜ間違ったのか」を考察することで、自分が何を理解できていないのか、どの部分に課題があるのかを把握することができます。
このようにして自分の弱点を見つけ出し、それを克服することで、間違えた問題だけでなく、今まで解けなかった問題にも取り組めるようになり、学力が飛躍的に向上します。
定期テスト、問題集、模擬試験などで間違った問題があれば、「なぜ間違ったのか」を徹底的に考え、対策しましょう。
・志望校の過去問を解く
中3の11月頃から、志望校の過去問にチャレンジしてみることが効果的です。
同じ問題が出ることは期待できませんが、過去問から大まかな出題傾向をつかむことはできます。
また、過去問を解くことで自分の現在の立ち位置を知ることが可能です。
得意な問題・苦手な問題を把握し、合格するために何を勉強すればいいかの参考にすることが出来ます。さらに、時間を測って解くことで、本番を想定した時間配分の感覚をつかむこともできます。
これだけはやるな!受験勉強のNG行動
効率的な勉強方法で勉強できていたとしても、受験勉強におけるNG行動をとってしまうと、成績が伸び悩んだり、合格が遠のいてしまったりする可能性があります。
ここからは、受験勉強において注意すべきポイントについて紹介していきます。
・いろんな参考書・問題集に手を出してしまう
受験勉強をしていく中で、多くの参考書や問題集に手を出してしまう受験生がいますが、この行為は、かえって学習効果を下げてしまいます。
これは、多くの参考書に手を出してしまうと、反復学習にかける時間が減ってしまい、1冊あたりで学べることが大幅に減ってしまうためです。
参考書を買うことで満足してしまい、どの参考書も中途半端になってしまうということがあります。1つの参考書を何周もし、記憶に定着させることで大きな学習効果が得られるということを頭に入れましょう。
参考書であれ、問題集であれ、受験において重要なのは、1冊を何回も繰り返して完璧にすることです。基本的には、どの参考書でも必要な知識や考え方は網羅されているので、無理に何冊もこなす必要はありません。
・まとめノートを作るのに時間をかけてしまう
受験勉強をする際に、まとめノートを作る受験生は多いですが、きれいにノートをまとめることはあまり効率のよい勉強とはいえません。というのもまとめノートを作るのには莫大な時間がかかる割に、教科書や参考書の方がわかりやすくまとまっている場合がほとんどのためです。
まとめノートを作るとその行為自体に達成感を得てしまったり、勉強をした気分になったりしますが、受験対策としてはノートや参考書をしっかりと読み込むようにした方が効率的です。
・学校のテストや提出物で手を抜いてしまう
受験勉強に没頭するあまり、学校のテストや提出物に手が回らなくなり、おろそかにしてしまう人がいます。しかし、こういった態度は、内申点を下げてしまい、進路や志望校の選択肢を減らしてしまう可能性があります。
そのため、受験勉強だけでなく、学校での勉強もしっかりと取り組めるよう余裕をもって勉強計画を立てるようにしましょう。
しかし、うまく内申対策をしながら受験勉強を進めるような勉強計画が立てられないと悩んでしまう方も多いかと思います。そこで、最後に理想的な勉強スケジュールの例を紹介していきます。
【目安を知ろう】高校受験の勉強スケジュール
最後に高校受験の勉強スケジュールの一例を紹介していきます。高校受験対策は余裕をもった勉強計画が重要です。ぜひ今から紹介するスケジュールを参考に勉強計画を立ててみてください。
・中3の4月~夏休み前
この時期から、多くの生徒が高校受験を意識し始めます。しかし、その一方で部活動が忙しくなったり学校行事があったりするなど、勉強時間を取りづらくなる人も多いです。だからこそ、毎日コツコツと学習をしていくことと、学校の授業を集中して受けることが大切になります。
この期間には、学校での勉強を軸に定期テスト対策を行うことで、基礎的な学力を身につけるようにしましょう。定期テストが終わった後は、問題の解き直しをしたり、間違った問題をやり直したりするなどの基礎固めが大事になります。定期テスト対策を重点的に行うことで、内申点アップにもつながります。
・中3の夏休み
この時期になると、いよいよ受験勉強が本格化します。部活動を引退して、自由に使える時間が増えてくる方も多くなるでしょう。
この時期においてのポイントは、中1・2で習った内容の総復習を5教科すべて、夏休み中に終わらせることです。
高校入試の問題の約70%は、中1・2までの学習内容から出題されます。秋以降は内申対策や総合演習などを中心に行う必要があるので、中1・2で習った内容は夏休みまでに終わらせておくとベストです。教科書や参考書の見直し、過去の定期テストの振り返りなどを中心に進めていくとよいでしょう。
・中3の9月~冬休み前
夏休みが明けると、部活動も完全に終了しているので、平日でもしっかりと勉強時間を増やす時期になります。また、内申点を上げたり、志望校を確定させたりする大切な時期でもあります。
とくに、中3の2学期の学習内容は受験でも大切な単元が多いです。そのため、学校の授業内容をしっかり学習していくことが、内申点アップと受験対策の両方につながります。
そのうえで、定期的に実施される模擬試験を受けましょう。模擬試験を受けるメリットは、自分が現時点でどの程度の実力なのかを把握できることです。目標までの道のりを再確認し、自分の弱点を確認することもできます。
もし、苦手な分野が見つかったら可能な限りこの時期に克服しましょう。模試で得点の低かった教科を集中的に見直すなどの対策も効果的です。
・中3の冬休み以降
いよいよ受験本番間近となるこの時期は、受験対策も大詰めです。本番と同じ環境で過去問を解いて、自分の実力を最終確認しましょう。
1点の違いが合否を分ける場合もあるので、点数を伸ばせる教科を徹底して勉強するのがおすすめです。
いかがでしょうか。ここで紹介した勉強スケジュールを参考に、勉強計画を立ててみてください。
勉強スケジュール通りに受験勉強に取り組むのは簡単ではありません。そのため、勉強スケジュールから外れてしまったときに、調整をかけていくことが重要です。
また調整がしやすいように余裕のあるスケジュール感で勉強計画を立てていくようにすることも大切です。
うまく勉強計画が立てられない方や、スケジュール通りに勉強を進められなくて悩んでいる方には、明光義塾がおすすめです。
学習計画をサポートする
明光義塾では、生徒一人ひとりに寄り添った定期的なカウンセリングによって、それぞれに合った学習計画をご提案します。また、進捗度合いに応じて学習計画を調整しながら、効果的な学習をサポートいたします。
お近くの明光義塾までお気軽にご相談ください。
まとめ
高校受験はとても大きな関門です。志望校に合格するためには長期間にわたり計画的に勉強を進めていくことが重要になります。
そして、計画的に勉強することと同じくらい大切なことは、効率よく勉強をすることです。この記事でご紹介した方法を参考にして、ぜひ着実に学力アップが目指せる勉強方法を実践してみてください。勉強に行き詰ってしまう方や1人ではなかなかやる気が起きないという方は、学習塾の利用もおすすめです。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-
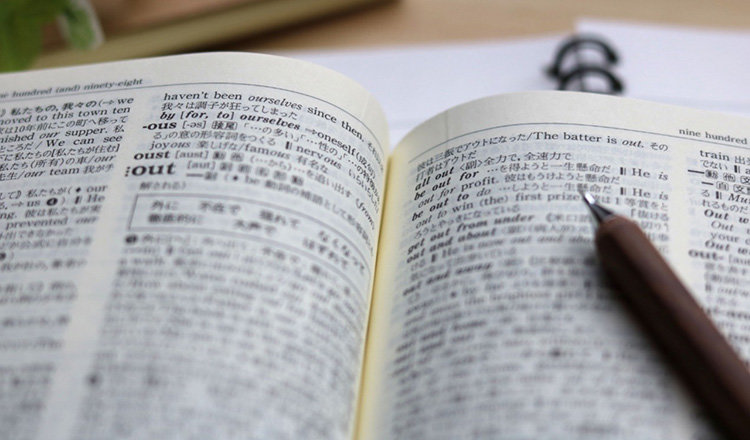
高校受験で英単語の暗記は必要?効率よく覚える方法とは
2021.03.08
英語は高校受験における必須科目の1つであり、受験結果を大きく左右する重要な科目です。 高校入試における英語では、受験する高校によって違いはあるものの、基本的にはリスニング、英作文、長文読解、...
-

高校受験対策に役立つ勉強方法を解説!おすすめの勉強方法は?
2021.02.10
高校受験に備えて早くから受験勉強を始める学生は多いものの、やる気が出ない、あるいは教科ごとの適切な勉強方法がわからないと悩む人も少なくありません。 高校受験に合格するためには、受験当日に向け...
-

受験生は入試対策、他学年は復習中心で冬の時期を有効に過ごそう
2017.12.25
2学期の期末テストが終われば(3学期制の場合)、受験生は入試に向けたラストスパート時期に入ります。一方受験生以外にとっても、冬休みは年明けの期末試験に向け対策に時間を割ける機会。保護者として...
タグ一覧
おすすめ記事
-

高校受験の面接頻出の質問8選 | 合格力がグッと上がるコツと回答例を紹介!
2025.07.03
高校受験で合格を勝ち取るには、面接の質問に対し準備することが不可欠です。この記事では、高校面接でよく聞かれる代表的な質問8つと、それぞれに対する回答のポイントや好印象を与える例文を紹介します...
-

高校説明会・高校見学に必要な持ち物、服装やマナーについて解説
2025.07.01
「高校説明会って、どんな服装で行けばいいの?」「持ち物って何が必要?」 そんな不安を感じる中学生や保護者の方も多いのではないでしょうか。 実は、高校説明会には必須の持ち物や好印象を与える服...









