2021.02.16
中学数学を制す!数学を復習するために効果的な方法とは

中学から始まる「数学」は、高校3年生まで、6年間に渡って学んでいく重要な科目です。しかし、小学生の頃は算数が得意だった人が、数学になった途端につまずき、不得意科目になることも少なくありません。
学年が上がるにつれてどんどん難しくなる中学数学は、復習を重ねて理解を深めることが大切です。中学数学は、どのように復習をすればよいのでしょうか?今回は、中学数学を制するために必要な復習方法や、つまずきやすいポイントについて詳しく解説します。
中学校で習う「数学」と小学校で習う「算数」の違いとは?
「数学」と「算数」は、どちらも計算を主とした科目であることは間違いありません。しかし、内容が複雑になるにつれて、明確な違いが生じるのもまた事実です。まずは、中学校で習う「数学」と小学校で習う「算数」の違いについて見ていきましょう。
計算する目的が異なる
算数では、主に日常生活で必要になる計算を用いて、正確な答えを出すことを目的とした授業が展開されます。出題される問題も、身近な事象が取り上げられることが多く、実用的な計算方法や知識を学びます。
一方で、数学は世の中で観測されるあらゆる事象を、数字を使って表す方法を理解することを目的とした授業が展開されます。授業では、負の数や平方根といった日常生活では使う機会が少ないものも見られます。
2つの科目の違いをまとめると、算数では正確な答えを出すことが求められますが、数学では答えが出るまでの過程を正しく理解し、表すことが求められるといえるでしょう。
中学数学で必要になる算数もある
数学と算数は目的や内容が異なりますが、共通点もあります。特に小学校で習う「比例」は、中学数学で習う「一次関数」や「二次関数」につながるため、深く理解していないとこれらを理解できないでしょう。
中学数学を理解するためには、当然ながら算数で習うことをマスターしておかなければなりません。
中学数学を制するには日々の復習が大切!
数学は小学生から中学生になるときに、得意科目から苦手科目に変わりやすい教科です。数学では算数を解く感覚では解けない問題も多く、中学数学をきちんと理解するためにも日々の復習が欠かせません。
ここからは、中学数学を制する必要性について考えてみましょう。
高校受験には数学が必要
高校受験では、入試を通じて学力検査が行われます。数学は入試の必須科目であり、高校を受験する中学生は、必ず通らなければならない門といえます。
公立と私立の入試制度の違いや、志望校の入試科目によっては、数学以外の科目の点数を上げることで合格することもありますが、主要科目である数学を深く理解しておく方が、確実に合格に近づくでしょう。
高校の数学についていけなくなる
高校で習う数学の内容のほとんどが、中学数学の応用です。難しくなるうえに、授業が進むスピードも速くなるため、中学数学のすべてをきちんと理解していないとついていけなくなります。
中学数学を完全に理解しないまま高校数学が始まると、その分大学進学を目指すための受験勉強の準備が遅れてしまう可能性もあります。数学は高校受験の後も学び続ける科目だからこそ、中学生のうちから日々復習を行い、きちんとマスターしておくことが大切です。
中学数学でつまずきやすいポイントと復習方法
中学数学では、算数に比べて難しく感じられる分野がいくつもありますが、その中でも「方程式」「図形」「関数」でつまずく中学生が多いようです。ここでは中学数学でつまずきやすい3つのポイントと、それぞれの復習方法を紹介します。
方程式
方程式では、1や2のような具体的な数字を用いるのではなく、未知数であるxやyといった文字を用いて計算します。文字式は方程式の基本であり、これを理解できていないと高い確率でつまずきます。まずは、文字式をしっかり理解するところから始めましょう。
方程式に慣れるためには、何度も繰り返し問題に取り組むことが大切です。方程式は計算の応用であることが多いため、基本的な計算問題と同じように、数をこなして慣れるのがベストです。教科書や問題集でつまずいた問題があれば何度も復習し、確実に正解できるようにしましょう。
図形
図形問題に苦手意識を持つ人も少なくありません。図形問題は1問の配点が大きいため、試験で高得点を狙うために確実にマスターしたい分野です。
図形問題では、図形の面積や角度を求める計算問題が多いため、計算力が求められます。他の分野と同じように、計算問題を早く正確に解けるよう、繰り返し問題を解きましょう。
図形にはそれぞれ定義や性質があるため、図形ごとの特徴を把握することで問題が解きやすくなります。図形問題のパターンを覚えて、問題を解く際に思い出せるようにしておきましょう。
関数
中学3年生になると、「関数」という分野が登場します。一次関数や二次関数、相似、三平方の定理といった難しい内容が続くため、頭を悩ませる人も多いでしょう。
関数を解くためには、まず定義を理解することが大切です。関数では、xの値が決まるとyの値が自ずと決まります。これをベースに、関数であるか関数でないかを判断することから始めます。
問題において、変域が何を表しているのかを理解することで、正解までの道筋が見えてきます。問題を解くカギは、たいてい問題文に隠されており、問題文から「何がxで何がyか」を見いだし、適切な計算方法を用いて正解を導きます。
問題文の中からカギを見つけられない場合は、教科書や参考書の例題をひたすら解き、問題に慣れることが大切です。
高校入試対策にも効果的!中学数学の復習方法とは

中学数学は、先ほど紹介した「つまずきやすい3つのポイント」以外にもさまざまな分野があり、そのすべてが高校入試に関係します。
中学3年生になってから焦って復習するのではなく、日頃から復習する習慣をつけ、高校受験に備えましょう。ここからは、中学数学を効率よく復習する方法について解説します。
演習量を増やす
中学数学の本質を理解するためには演習量を増やし、問題に慣れる必要があります。問題と向き合う時間を増やし、一定の演習量を確保しましょう。
「何となく解ける」レベルで満足するのではなく、解答を人に説明できるくらい深く理解することを心がけましょう。繰り返し演習をすることで、問題のパターンを把握できるようになります。
計算力をつける
中学数学では、どの分野においても計算力が基本になります。例えば方程式の立て方を理解していても、計算を間違えれば得点につながりません。高校入試で配点が多い図形や関数においても計算力を問われるため、それが合格を左右することもあります。
また、1つの問題で計算する時間を少しでも短縮できれば、入試でも有利になるでしょう。日々の復習を積み重ねて、計算問題は確実に解けるようにしておきましょう。
基礎を固める
これは数学に限りませんが、基礎が固まっていないと問題は解けません。応用問題も基礎を組み合わせて作られているため、やはり入試では基礎力がものをいいます。総合的な数学力を高めるためにも、応用力をつける前に基礎を固めることを優先しましょう。
まずは基礎問題を積極的に解き、深く理解することが大切です。わからない問題があれば解答をくまなく読んで、最終的には何も見なくても正解できるよう、繰り返し演習を行いましょう。基礎問題を確実に正解できればある程度の点数を取れるため、偏差値も格段にアップします。
公式は暗記ではなく問題を解いて覚える
中学数学に登場する公式は「暗記しないと始まらない」と思われがちですが、実は実践的に取り組む方が覚えやすいです。中学数学では、さまざまな公式を問題に合わせて使い分けることが大切なので、ただ公式を覚えているだけではほとんど意味がありません。
問題をこなして、公式を使う方法も一緒にマスターすると、実践力がアップします。公式を使用する問題のパターンを理解すれば、暗記しようとしなくても自然と公式が頭に入るようになります。
解説が豊富な参考書や問題集を選ぶ
復習のために参考書や問題集を購入する際は、つい問題の量に目が行きがちですが、高校入試に向けて必要なのは、1つ1つの問題を丁寧に解き、深く理解することです。
闇雲に問題をこなしていては理解が追いつかず、結果的に学力が身につきません。解説が少ない問題集や参考書は、わからない問題があっても理解できないまま終わってしまう可能性があります。
1つ1つの問題を深く理解するためにも、解説が豊富でわかりやすい問題集・参考書を選ぶようにしましょう。
過去問を解く
中学3年生で本格的に受験勉強をスタートしている人は、高校入試を突破するための学力に焦点を立てて勉強を進めていく必要があります。受験を視野に入れて中学数学を復習する際は、過去問を利用しましょう。
過去問には実際の高校入試で出題された問題が記載されており、繰り返し解くことで入試に通用する数学力を養えます。問題は中学で習う数学から出題されているので、復習としての効果もある勉強方法といえます。
わからない問題は必ず原因と突き止めて解決する
数学でわからない問題を放置しておくと、のちのち他の問題も解けなくなるでしょう。中学数学でつまずいていると思っていたら、実は小学校で習う算数の時点でつまずいていたというケースもあります。
数学は一朝一夕で理解できるものではなく、日々の学習の積み重ねが理解度につながるのです。わからずに放置した問題が増えれば増えるほど、解決の糸口が見つからないまま新たな問題に取り組むことになり、ついには受験結果にまで大きく影響してくることも考えられます。
数学でわからない問題があれば、すぐに原因を突き止めて解決する癖をつけましょう。
中学数学でつまずきたくない受験生は、塾や家庭教師といった受験指導のプロに相談できる環境が必要かもしれません。
まとめ
中学で習う数学は算数に比べて複雑であり、日々復習を行わないとついていけなくなる可能性があります。「数学が苦手」と感じたら、なるべく早く対処することが大切です。
明光では苦手科目を改善するべく、生徒一人ひとりに合わせた授業カリキュラムをご用意しております。高校受験に向けた手厚いサポートも行っておりますので、高校受験に向けて中学数学をマスターしたい中学生は、ぜひ明光にご相談ください。
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

模試の勉強法とは?模試の成績の上げ方・年代別の受験への活かし方を紹介
2025.07.18
模試は志望校合格のための“羅針盤”とも言える存在です。しかし、「模試って結局どう活用したらいいの?」「成績がなかなか伸びない…」と感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、模試...
-
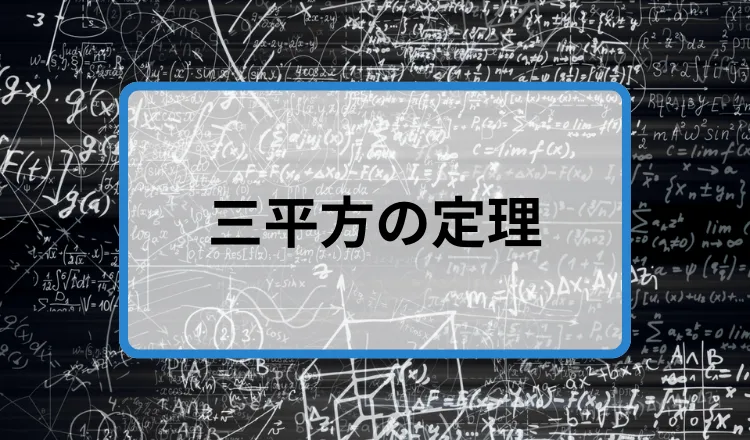
三平方の定理(ピタゴラスの定理)とは?計算の仕方と証明をやさしく解説!
2025.07.04
もくじ 三平方の定理(ピタゴラスの定理)とは? 三平方の定理(ピタゴラスの定理)の応...
-

ノートの書き方で成績が変わる!頭の良い人のノートの取り方とは
2025.07.03
「ノートって、ただ黒板を写していればいいんじゃないの?」 実はそれ、大きな誤解です。 ノートは、自分の理解を深め、記憶を定着させるための学習ツールです。 ノートの取り方・書き方ひとつで、成績の伸び方...
タグ一覧
おすすめ記事
-

作文の書き方|小中学生向けにコツと例文+原稿用紙の正しい使い方をわかりやすく解説!
2025.07.03
作文が苦手という方は多いです。「何を書いていいかわからない」「うまく書けない」といった悩みの多くは、書き方のルールや型を知ることで解決できます。この記事では、作文の書き方を4つのステップでわかりやす...
-

【無料テンプレート付き】勉強計画の立て方|効率的な学習を実現する勉強計画表とは?
2025.07.03
「勉強しなきゃ」と思っても、いざ机に向かうと何から始めればいいかわからない…そんな経験はありませんか? 実は、成績アップに欠かせないのが“計画的な学習”です。 目標に向かって着実に前進するに...
-

【小論文の書き方】構成・テクニックを例文付きで解説!高校生向け完全ガイド
2025.06.26
「受験科目に小論文があるけれど、どうやって書けばよいかわからない」 というように、小論文に苦手意識をもつ高校生は多いのではないでしょうか。 小論文には書き方や構成の仕方...
-

自主学習のネタの決め方・ノートの書き方を解説!
2025.05.29
学校から自主学習をするようにと言われて、「何をすればいいの?」「進め方があってるのか不安」と悩まれているご家庭も多いことでしょう。 そこでこの記事では、そもそも自主学習をする目的、ネタの探し方・決め...
-

定期テスト(中間テスト・期末テスト)の勉強はいつから始める?高得点を狙える勉強法とは
2021.02.22
定期テストの勉強はいつから始めていますか?定期テストの結果は、1年の成績を大きく左右するうえ、内申にも直結します。そのため受験を視野に入れた勉強では、学力を高めることと同時に、定期テストで高...









