2015.04.28
やっぱり気になる!子どもの友だち付き合い把握術
保護者のみなさんはお子さんが家庭の外でどのような友達や先輩と過ごしているのか気になりますよね。他のご家庭では、お子さんの友だち付き合いをどれくらい把握しているのでしょうか。また、友だち付き合いを把握するために工夫していることがあるのでしょうか。
本記事では明光義塾の保護者に聞いた、子どもの友だち付き合いの実態とそれを把握するための工夫をご紹介!お子さんの友だち付き合いとその把握について、考えるきっかけにしていただければ嬉しいです。
その1. お子さんの友だち付き合いの把握
Q. お子さんの友だち付き合いを把握していますか?(中学生のお子さんの場合)
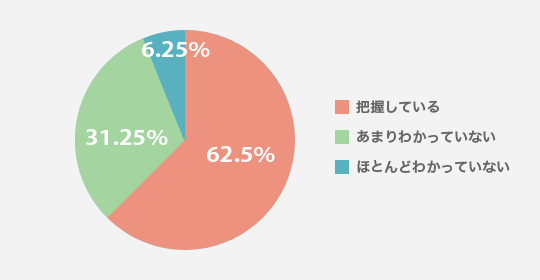
編集担当
回答いただいた保護者の6割が、お子さんの友だち付き合いを把握しているという結果が出ました。一方で「あまりわかっていない」「ほとんどわかっていない」と回答された保護者の方も4割弱いらっしゃいました。小学生のお子さんを持つ保護者のほとんどが「把握している」と答えたことを考えると、中学生になるにつれてお子さんの友だち付き合いを把握しにくくなる傾向があるようです。
その2. お子さんの友だち付き合いで気になること
Q. お子さんの友だち付き合いで気になることを教えてください
編集担当
次に、お子さんの友だち付き合いで気になることをメイコミュ保護者にお聞きしました。みなさんの声をご覧ください。
QOO(女性・40代) お子さんの年齢:中学3年生
人見知りが激しく、新しい友達を作るのが苦手。
ふ〜み(女性・40代) お子さんの年齢:中学1年生
グループに属するタイプでは無いが、孤立していないか心配。
myk88szk88(女性・30代) お子さんの年齢:中学1年生
新しい友達と仲良くやってほしい。
編集担当
友達ができているか、仲良くやれるかといった親心が見える回答をいただきました。
一方で、どのような友達と、何をしているのかわからないという不安の声もいただいています。
うきんこ(女性・40代) お子さんの年齢:中学1年生
友達の友達とも付き合っているようで、そうなると把握が難しい。
Ryo(女性・50代) お子さんの年齢:中学2年生
特定の友人のことはよく話しますが、複数の友人と会っている時(たまたま見かけました)があり、今日は誰と一緒にいたのかを質問すると1人でいたと答えるので真意がわからない。
しろうさ(女性・50代) お子さんの年齢:中学3年生
スケートボードや 3on3バスケットボールに夢中になっている。定期試験中でも遊びに出ることがある。「サボろう」でつるんでいるようでそれが気になる。
編集担当
中学生になると行動範囲も広がるので、友だち付き合いも複雑になるようですね。たくさん友達がいるのは良いことですが、それゆえに保護者が把握できないという不安もついて回るようです。
またスマートフォンなどの通信ツールへの不安の声もありました。
チューリップ(女性・40代) お子さんの年齢:中学2年生
最近、スマートフォンを購入したので、それによって友達との関係などに変化があるかもしれない...と少々気になります。
れい(女性・40代) お子さんの年齢:中学3年生
LINEで他校との友達も増やしているようで、そのへんが把握できないので心配です。
マスカット(女性・40代) お子さんの年齢:中学2年生
スマホなどを使う子どもが多く、陰口が気になっている様子です。
編集担当
スマートフォンは、保護者世代が学生の頃はなかったツールです。どのような使い方をしていて、友達とコミュニケーションをしているのか、想像がつきにくいですね。
スマートフォンの使い方のルールを決めるなどの対策が必要になってきそうです。
その3. お子さんの友だち付き合いの把握
Q. お子さんの友だち付き合いを把握するために工夫していることを教えてください
編集担当
お子さんの友だち付き合いについて、保護者からさまざまな声が寄せられました。お子さんの友だち付き合いを把握するうえで、保護者がしている工夫をみなさんに教えてもらいました。
のりちゃん(女性・40代) お子さんの年齢:中学2年生
遊びに行くとき、誰と一緒か聞く。
しろうさ(女性・50代) お子さんの年齢:中学3年生
誰とどこで遊ぶか聞くようにしているが 嘘だったりすることが多くあった。 帰ってきたら聞くようにしている。
よっき(女性・40代) お子さんの年齢:中学3年生
話に出てきた友人の名前や関係を聞いています。
編集担当
遊びに行くときや、会話の中で友達の名前を聞くようにすることがやはり基本のようですね。さらに具体的な対策をされている保護者の方もいらっしゃるようです。
ゆりえど(女性・40代) お子さんの年齢:中学2年生
名前と相手の最寄駅を聞いて、お互いが6時までには帰宅できるようにしている。相手の名前を聞いたら集合写真で顔を確かめる。
QOO(女性・40代) お子さんの年齢:中学3年生
【1】何でも話せる環境作り
【2】娘の友達と仲良くなる
うきんこ(女性・40代) お子さんの年齢:中学1年生
出かける際には、誰とどこに行くかを聞き、お財布にいくら入っているかをできる限り確認。
マスカット(女性・40代) お子さんの年齢:中学2年生
車での送り迎えやご飯の時などの会話の時の表情を何気なく見ています。
編集担当
「集合写真で顔を確認」「お子さんの友達と仲良くなる」「財布の中身を確認」「表情を観察する」など、みなさんいろいろな工夫をされているようですね。中学生となると、コミュニケーションを取りづらくなることも多いですが、お子さんをしっかりと気にかけてあげることが大切なようですね。お子さん自身も、気にかけてもらっていると感じることで、保護者の信頼に応えようとするのではないでしょうか?
保護者のみなさん、たくさんの参考になるお話をありがとうございました。お子さんの友だち付き合いで悩んでいる方は、参考にしてみてくださいね!
この記事を家族や友人に教える
あわせて読みたい記事
-

中3受験生の夏休み、親はどう支える?1,000人調査で見えたリアルな実態と不安とは?
2025.06.26
中学3年生の夏休みは、受験に向けた勉強時間をしっかり確保するための重要な時期です。 しかし、部活動も最盛期を迎える時期でもありますし、さまざまな誘惑に打ち勝ち十分な勉強時間を確保するのは容...
-

【2025年調査】980名の小中学生の保護者に聞いたPTA活動と必要性の意識の実態とは?
2025.02.26
もくじ PTAとは? PTAの活動内容と必要性について ...
-
YDKという言葉を聞いたことがあるでしょうか。「YDK」はY:やれば・D:できる・K:子の略語で、2014年から明光義塾が掲げるコンセプトです。これに関連する言葉として「自己効力感」があります。簡単...










